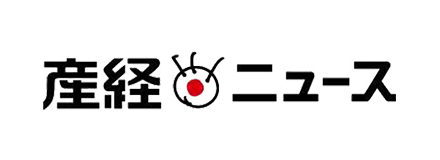■生きる意味教える「最期」とは
未曽有の被害を出した東日本大震災から間もなく5年を迎える。人智を超えた地震と津波に黙々と立ち向かい、悲しみに耐えながらも明るく振る舞う被災者の姿に多くの人が胸を打たれた。
だが、当時の日本には対照的な動きもみられた。その一つが東京電力の福島第1原発事故に伴い、全国でパニック的に広がった「反原発」の風潮だ。原発事故は周辺地域に深刻な事態を招いた。東電や政府の対応に非難が集中したのは当然だが、その矛先は各地の電力会社や原発にも向かい、国内の原発は段階的に稼働停止へと追い込まれた。
そこではイデオロギーと混然一体となった感情論が目立った。原発停止で電力不足に陥り、首都圏では計画停電まで実施されたが、資源小国・日本としてのエネルギー戦略などに関する議論はみられなかった。世論の反発を恐れ、原発の必要性を訴える識者は非常に少なかった。
その中で冷静な視点に立ち、日本を取り巻くエネルギー情勢や電力供給の重要性を説いたのが、21世紀政策研究所の澤昭裕研究主幹だ。経済産業省出身の澤は、経験を踏まえてエネルギー行政や原子力規制のあり方に注文をつけるなど、建設的な提言を続けた。産経新聞の正論メンバーとしても活躍したが、先月、58歳の若さで世を去った。膵臓(すいぞう)がんだった。
昨年秋に自分の人生が長くないことを知り、澤は仕事のスケジュールを組み直した。これまでの論考をまとめ、思い出の地への旅行に出かけた。医師と相談して副作用が少ない薬を使い、最後の原稿を書き上げた。そのチェックを終え、緩和ケア病棟に入ったのは亡くなる2日前だったという。
著名人らの最期の言葉を特集した文芸春秋は、51歳で亡くなったジャーナリスト、竹田圭吾の「がんになってよかった100のこと」と題する手記を掲載している。その中で竹田は「がん患者は必ずしも『闘病』するわけではないし、するべきでもない。膵臓にがんが見つかってから2年半を過ごした今、僕はそう感じている」と記している。
この文章は単行本のために執筆を始め、未完で終わった遺稿だ。竹田は昨年9月にテレビ番組で自らがんであると告白したが、「これで人生が終わりというわけではない。ちょっと種類が違う人生が続くだけのこと」とコメントし、大きな反響を呼んだ。
竹田が残した著作メモには「人生の残り時間を逆に気にしなくなった。いつ死んでもおかしくない(人生の残り時間が以前よりクリアに提示されている)のだから、気にしても仕方がない」という心境もつづられている。
文芸春秋の特集は「人生の終わりに何を遺すべきか」とのテーマによる対談も載せている。作家の平岩弓枝は「人の『死』は、遺された人の中で生かし得るものだということを、命の終わりに触れて初めて分かった」と振り返る。
ノンフィクション作家の柳田邦男は「人の最も核となるような言葉は、その人が亡くなると、受け取った人の中で突然、いぶき始める。いなくなったからこそ、その精神性の部分が純化される」と分析している。
人の死、そして残された言葉は、私たちに生きる意味を教えてくれるということだろう。
安倍晋三首相は1億総活躍社会に向け、施政方針演説で「同一労働同一賃金」の実現を表明した。ただ、日本の会社員は職務に明確な規定がなく、「同一労働」をどう判断するかが難しい。
「『正規』と『非正規』の線引きをやめよう」(中央公論)で玄田有史東大教授は、日本における正規雇用の曖昧さを指摘。そのうえで「働き方の違いを客観的に論じるために有効な指標は『無期・有期』雇用だ」と提案している。今後の雇用制度改革にあたって一考に値しよう。=敬称略
産経新聞社「産経新聞」のご案内
産経ニュースは産経デジタルが運営する産経新聞のニュースサイトです。事件、政治、経済、国際、スポーツ、エンタメなどの最新ニュースをお届けします。
関連ニュース
-
『藝人春秋2』発売記念 水道橋博士ミニトーク&サイン会
[イベント/関東](タレント本/ステージ・ダンス/演劇・舞台)
2017/12/06 -
93歳の著者による“日本最高峰”の大人気エッセイ 【エッセイ・ベストセラー】
[ニュース](エッセー・随筆)
2016/08/27 -
【話題の本】『102歳、一人暮らし。 哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方』石井哲代、中国新聞社著
[ニュース](家庭医学・健康)
2023/01/31 -
人体は「進化の失敗作」? 人体進化の「不都合な真実」を解説した一冊が話題
[ニュース](タレント本/心理学/生物・バイオテクノロジー/演劇・舞台)
2019/12/21 -
ジェーン・スーさんの『女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。』サイン会
[イベント/関東](エッセー・随筆)
2016/05/27