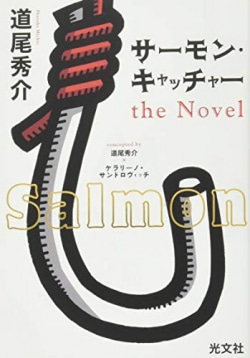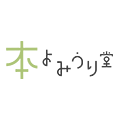『サーモン・キャッチャー the Novel』
- 著者
- 道尾秀介 [著]/concepted by 道尾秀介×ケラリーノ・サンドロヴィッチ [著、企画・原案]
- 出版社
- 光文社
- ジャンル
- 文学/日本文学、小説・物語
- ISBN
- 9784334911294
- 発売日
- 2016/11/16
- 価格
- 1,650円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『サーモン・キャッチャー the Novel』刊行記念インタビュー 道尾秀介

道尾秀介さん
――まずはKERAさんとの出会いからお聞かせいただけますか。
道尾 そもそもは、間違ってKERAさんの作品と出合ってしまったんです。8年くらい前、ニコルソン・ベイカーの『中二階』を読んだらすごく面白くて、ほかの著書も買おうと書店に行ったんですが置いてなくて。それでインターネットでベイカーの『室温』という本を買ったつもりが、間違ってKERAさんの戯曲『室温――夜の音楽』を購入していたんです。当時はKERAさんのお名前を知らなくて、別の外国人作家の本が届いちゃったと思いました。
ところが読み始めてみると、それまでの数年間で読んだ本の中でいちばん面白かったんです。それで、手に入るKERAさんの戯曲はぜんぶ読んで、舞台も観に行くようになりました。そのことをツイッターに書いていたら、関係者の方に声を掛けていただいて、2010年上演の『2番目、或いは3番目』の公演パンフレットに解説原稿を書かせていただいたり……。そのうち、KERAさんのほうから「ふたりで何かやろうよ」って言ってくれたんです。
――コンセプトはどのように決めていったのですか?
道尾 KERAさんと話していくうちに、“どうしようもない奴”を書きたいねっていう話になったんです。僕の作品では『カラスの親指』が似た印象ですけど、実はあの中には、ひとりだけバツグンにクレバーな奴がひそんでいたんですよね。でも今回は、本当にどうしようもない連中、何をやっても駄目な連中を書こうという話にまとまりました。
――登場人物それぞれの勘違いや思い違いが、ストーリーを動かしていきます。
道尾 映画になったときに、登場人物が少ないと面白くないなと思ったんですね。それで、群像劇の形になりました。ただ、群像劇の小説でありがちなのは、視点人物が変わっても、なかなかその人物として読めなくて、今自分が何を読んでるのか分からなくなってしまうこと。それだけは避けたかったので、きちんとその人のパートに切り替われるように工夫しました。
――物語の重要な舞台が、屋内釣り堀「カープ・キャッチャー」です。
道尾 もともと釣りは好きで、いつか釣りのシーンを書きたいと思ってました。「カープ・キャッチャー」のモデルとなる釣り堀が千葉県にあるんですが、システムも同じで、釣った魚がポイントとなって、景品と交換できるんです。パチンコ的で、すごく射幸心をあおるんですよね(笑)。
平日でも土日でも、いつ行ってもいろんな人がいるんですよ。そんなに繁盛してるわけじゃないんだけど、男性も女性も、大人も子どももいる。魅力的な場所だったんで、そこをスタート地点にして物語を書こうと思いました。
――過去の道尾作品と比べてみても、ここまでコメディに徹した作品は初めてではないでしょうか。
道尾 そうですね。でも実は殺されかける人もいて、コメディにしてはかなりシリアスな要素も入っているんですよね。名前のつけようのない、独特なテイストの小説を書けたなと思います。
かなりフィクショナルな世界なので、長身&長髪&長髭で“神”と呼ばれている人物や、お金持ちのマダムなど、「フェイクですよ」というのを前面に出して、やりたいことをやれたのが楽しかったです。ここまでカリカチュアライズな小説というのは、やはりこういう企画だったからこそ書けたと思います。
それと、時事性のある物語ではないので、古びる要素がゼロに近い。時代が変わっても、こういう駄目な奴っているんですよね(笑)。スマホも出さなくて良かったなと思いました。

――タイトルもインパクトがあります。
道尾 “まさか鮭を捕る人の話じゃないだろう”ということは、きっと僕の読者なら分かってくれると思うんですが(笑)。打ち合わせをしていく中で、意味のよく分からないタイトルをつけたいねって話してたんです。そうしたら、映画プロデューサーの小川さんが「サーモンっていう単語を入れましょう」って思いつきで発言して(笑)。そのとき既に、釣り堀の名前は「カープ・キャッチャー」に決まっていたので、その流れで、『サーモン・キャッチャー』という言葉が出てきました。語感も良いし、何か惹きつけるものがあったんですね。全員一致でタイトルに決まりました。
とはいえ、作品に鮭は出てこないし、さあどうしようかなと。結果的に、けっこうアクロバティックな方法で出てきますよ(笑)。
――道尾作品としては、初めてのソフトカバーです。中の紙も、通常より柔らかいものを採用しました。
道尾 いいですよね、軽やかで温かみがあって。イラストが入るのも初めてです。
月並みな表現ですけど、おもちゃ箱のような装幀で楽しいですよね。小説のなかに、白い箱が出てくるじゃないですか。一体何が入っているのか、一度でいいから開けてみたいと思わせる謎の箱。このカバーもそういうイメージですよね。この中を見たいって思わせる。大きな釣り針の先が、なぜか尖っていないのも面白いなと思います。
――ご自身の作品がドラマや映画になることについては、どのように考えられていますか。
道尾 正直言うと、自分ひとりで作るほうが楽だし、やりやすいんです。スケジュール的なこともそうですし、映像になることが前提だと、たとえば膨大な数の人間は出せないとか、ビル爆破はできないとか、やれないこともいっぱいあるんですよね。
でもお題をもらって書くのは得意なんです。ドラマ原作というオファーをいただいて書いた『月の恋人――Moon Lovers』もすごく好きな作品で、もし「何を書いても良いよ」と言われたら、あの小説はできなかった。いつも使わない部分の脳を使うことで、面白いものが出てくるんだと思います。
『サーモン・キャッチャー』も、今まで開けたことのなかった引き出しを開けてもらった感じがします。自分はわりと引き出しの多い方だと思ってたけど、まだこんなところにもあったのか! って。
――作家さんのなかには、自身で脚本を書かれたり監督を務められたりする方もいらっしゃいますが、挑戦してみたいお気持ちはありますか?
道尾 ないですね。基本的に餅は餅屋だと思っています。音楽関係や映像関係の知り合いも多いので、話を聞いていると絶対に敵わないなということが良く分かりますから。
小林亜星さんとお酒を飲んでると、よくそういう話になるんです。亜星さんは作曲家ですが、編曲はやらないと決めているそうです。自分で編曲をしてしまうと作曲のときに甘えが出るからとおっしゃっていて、すごく納得できました。僕も、「僕にできることを120%やるから、それに+αをつけてください」という気持ちで作品を渡しています。

――一方で、最近は音楽活動をアクティブにされていますね。
道尾 はい。ずっとライブに通っていた大ファンのアーティストと同じステージで演奏するなんて、数年前には想像もつかなかったことが次々起きて、とても楽しいですね。緊張もしますけど、世界がどんどん広がっていくのもわかるし、違う世界のプロの厳しさや真剣さを、1mの近さで見られるのはとても貴重な体験です。近頃は作詞を任せてもらえることが多くて、短い文字数の中で的確に表現する難しさと面白さを感じています。
Aメロ・Bメロ・サビっていう曲の創り方が、小説と通ずるところがあって。僕はやっぱりサビのある小説が好きだなって思うし、サビだからって手数を多くして賑やかにすればいいかっていうとそうでもない。単調なリズムにサビが載って、何を聴かせたいかハッキリさせるという方法もあるんです。その盛り上げ方は勉強になりますね。
――最後に、KERAさんとのコラボという、今までにない創作活動の感想をお聞かせください。
道尾 創作の世界の大先輩ですし、今回の企画をやるまではただの一ファンでしたが、最初から気負わないようにしようとは思っていました。遠慮したら、絶対つまらないものになってしまうと分かっていたので。
僕はこの作品で初めて、ためらいなく人を殺す人間を出したんですよ。今までも殺人者は書いてきましたけど、すごく葛藤している人物として描いていたので、これはたぶんKERAさんの影響を受けたんだと思います。
僕とKERAさんはぜんぜん似てないけど、水と油ではない気がします。界面活性剤みたいなものがあって、混ざり合うことで何か面白いものが生まれる関係性だと思っています。
道尾秀介(みちお・しゅうすけ)
1975年生まれ。2004年、『背の眼』で第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞。以後、『シャドウ』で第7回本格ミステリ大賞、『カラスの親指』で第62回日本推理作家協会賞、『龍神の雨』で第12回大藪春彦賞、『光媒の花』で第23回山本周五郎賞、『月と蟹』で第144回直木賞をそれぞれ受賞。近著は『スタフstaph』。