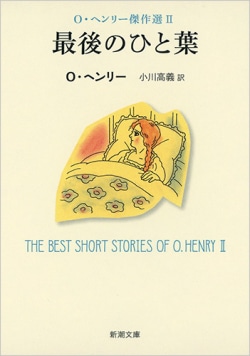『最後のひと葉』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
名作は何で出来ている?
[レビュアー] 倉本さおり(書評家、ライター)
名作と呼ばれるものはたいてい、すぐれた骨格を持っている。幼い私たちはその立派な、すこしカビ臭い骨の標本こそが物語の姿なのだと思い込み、各々のガラスケースにとりあえずしまっておく。やがて背丈が伸びるにつれ目に映るものが変わり、苦かったりしょっぱかったりする出来事の数々が胸の内側をひたひたに満たす。そうやってケースなど丸ごと押し流してしまう頃になって、ふいに驚嘆することになるのだ。その物語が、いつのまにか肉を伴って生きていたことに。
〈「最後の一枚が落ちたら、あたしも終わりね」〉。
病床の窓から見える蔦の葉を数えながら死を待つ娘を勇気づけるため、老画家が仕掛けた一世一代の大勝負。O・ヘンリーの名前を知らない人でも、「最後のひと葉」の話ならなんとなく知っているはず。けれど、ほれぼれするほど肌理のこまかい訳文の力を借りつつ、改めて「小説」として読み直してみれば、これまで取りこぼしてきた細部に思いがけないほどの示唆が詰まっていたことに気づかされる。たとえば会話。生きる気力を失っているジョンジーをどうにか前向きにさせるべく、医者が彼女のパートナーであるスーに「気になる男でもいないのか」と尋ねる場面がある。スーはすっとんきょうな声を出したあとに狼狽し、こんなふうに答えるのだ。〈「男?」「男なんてものは――あ、いえ、先生、そういうことはありません」〉。以前ひどい目に遭わされたことでもあるのか、あるいは最初から「男」を拒絶した生き方をしているのか。いずれにせよ、彼女の鋭敏な反応からは何通りもの意味や関係性を読み取ることができる。すると、偏屈なくせに彼女たちにだけは何かと目をかけてやろうとする隣人・ベアマンの心情も、社会的な問題を抱き込んだ複雑な厚みを備えて浮かび上がってくる。加えて色彩。レンガに張りついた蔦の葉に象徴されるように、おしなべて晩秋の深い色合いに染まった世界のなか、じつは二つの「青」がはっとするほどの鮮やかさで対比されていることに気づく。その明瞭なコントラストによってあぶり出されるのは「理想と現実」のあり方だけでない。
実際、この短篇集のなかには対照的な価値観を持った人間がたくさん登場する。「金銭の神、恋の天使」では、すがすがしいほどの成金おやじ(!)と、愛こそすべてだと信じる妹が、恋に悩める若者のため各々のやり方で手を差し伸べる。「感謝祭の二人の紳士」では与える者と与えられる者、双方の強烈な使命感がもたらすトホホな顛末があたたかい筆致で描き出され、「金のかかる恋人」では世間知らずなお坊ちゃまとしたたかで現代的なヒロインの生活感覚の食い違いがユーモラスな結末を連れてくる。だが最も大切なポイントは、どの価値観もけっして否定されないということ。虚構じみた役割を担った登場人物たちを待ち受けるのは、単純な悲劇でもハッピーエンドでもない。彼らが生きている場所は、一元的な教訓話の埒外にある。そこには「フィクションと人生」のあるべき関係に対する、O・ヘンリーの力強いメッセージが込められているのだろう。
さて、男女三人の古典的なドタバタ恋愛劇を見事な塩梅で描写してみせた「芝居は人生だ」の中に、こんな発言が出てくる。〈舞台はみんな世界で、役者だって人間なんだ。人生があって芝居になる。シェークスピアとは逆のことを言わせてもらうぜ〉。これは語り手自身が言及しているとおり、「お気に召すまま」に登場する一節――世界はみんな舞台で、すべての男女はその役者にすぎない、という内容の主旨をあえてひっくり返した主張になっている。ちなみに原題は “The Thing’s The Play”。これまたハムレット王子の有名な台詞、”The play’s the thing” の語順をきれいにひっくり返した形だ。
人生があって、芝居になる。すなわち、現実があるからこそフィクションに味わいが生まれる――その考え方は、「ある都市のレポート」に登場する魅力的な文筆家の言葉ともそっくり重なっている。退屈な風景が延々と続く平凡な町に住む彼女は、その退屈さと平凡さゆえに身を持ち崩した夫に手足をもがれ、代わりに想像の翼を広げているのだ。
ここに収められた作品が読み返すたびに新しい姿で語りかけてくるのは、そのつど現実を生きてきた私たちの胸の内側に新しい溶媒が満たされているからなのだろう。ただただしょっぱい思い出も、舌がひん曲がるくらい苦い経験も、この名作と向き合っている間は千両役者の声音で私たちを読書の愉楽へと誘ってくれる。