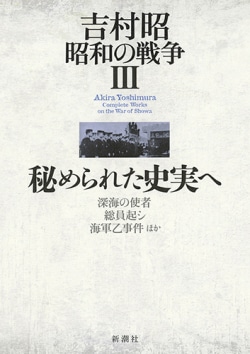『吉村昭 昭和の戦争3 秘められた史実へ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
文学者の眼
[レビュアー] 森史朗(作家)
一九七〇年(昭和四十五年)秋のことであったと思う。筆者が勤めていた出版社に吉村昭氏が訪ねてきたことがある。編集部保管の写真資料を見るためである。
それは、何とも異様な写真類であった。
戦時中に事故によって海没した潜水艦が戦後八年目にサルベージ会社によって引き揚げられ、浮上した艦内に飛びこんだ地元新聞社のカメラマンが兵員室の遺体を眼にして、とっさにカメラのシャッターを切った。乗員たちの遺体は六一メートルの海底で腐敗菌も発生せず、冷温状態で保存されていたので、まるで生けるが如く五体満足で横たわっていた。
吉村さんは写真を手に取り、食い入るように眺めていたので、私はいったん席を外し、見終わった頃合に応接室にもどった。
「おどろきましたねえ……」
吉村さんは深い吐息とともに、一枚の写真を指さした。
作業衣の胸をはだけ、両足を開いて仰向いている若い乗員の前に一人の水兵が佇立している。かすかに両足が浮いているのは縊死したためで、首に太い鎖が食いこんでいる。おそらくは、酸素不足で息苦しさに耐え切れなかったのであろう。
吉村さんに衝撃をあたえたのは、その筋骨隆々たる若者のがっしりした腰の下、下腹部の褌から男根が太く屹立していることである。どのような生理現象なのか、その遺体が生きているかのように立っているので生々しく、生命の息吹きすら感じさせる。
吉村さんは『文學界』の一挙掲載「逃亡」をすでに書きおえ、つぎのテーマを模索していた段階だったから、即座に「この海没した潜水艦をテーマに書いてみましょう」と快諾してくれた。
文芸作家吉村昭は、「少女架刑」「透明標本」など死を扱ったテーマが多く、四度の芥川賞候補となった。この若い水兵の悲惨な死は、吉村さん自身の相次ぐ家族の死、東京大空襲、左肺の大手術など生と死の極限を見つづけた作家の視点に何かしら衝き動かすものがあったにちがいない。
当時の出版状況といえば、第二次戦記ブームといわれる活況を呈しており、第一次の吉田満「戦艦大和ノ最期」、野間宏「真空地帯」、大岡昇平「俘虜記」など作家の私的体験を文芸化した作品群とちがって、新米作家やジャーナリストが手軽にまとめた体験記、小説読物の類が氾濫していた。
そんなノンフィクション作家や純文芸作家が見向きもしなかった戦争を主題に、人間ドラマとして本格的な記録文学を生み出したのが、吉村昭著「戦艦武蔵」なのである。
作品「総員起シ」は翌年春に完成し、一九〇枚の長篇小説として雑誌掲載され、評判も良く、即単行本化された。
ところで、「総員起シ」執筆時に、編集部側がおどろかされたことがある。吉村さんの、取材記者の拒否である。
私は前任の週刊誌取材の体験から、大がかりなテーマは筆者を中心に数人の取材記者の助力を得て、はじめて記事が成就するものと考えていた。これがいわゆる調査報道の核である。
文芸ジャーナリズムの世界では、その習慣がなく、相変わらず作家依存の作品群が目次を飾っていた。したがって、私小説が文芸の主流で、小ぢんまりした小説群が誌面におとなしくまとめられていた。
私はそんな文芸世界が不満で、もっと社会性のある大きなテーマに取り組んでもらいたいと願っていた。そんな期待に真正面から応えてくれたのが、作家吉村昭である。
「総員起シ」の次作となった月刊『文藝春秋』誌連載の「深海の使者」などは取材対象者一九二名、戦時中の日独潜水艦の交流を描いた壮大な歴史ドラマである。この取材の労力、経費、資料蒐集にどれほどの個人的献身が必要なものなのか。
吉村さんの下取材の経費は、すべて自弁である。「深海の使者」の場合、旧海軍関係者が日本全国に散らばっていて取材費用がかさみ、「預金通帳に手をつけて、家計が赤字になっちゃった」と後日、ご当人が苦笑いしながら告白したのを耳にしている。
最初にテーマが決まったとき、私が「取材記者は何人必要ですか」と問いかけると、吉村さんは「取材記者なんていりませんよ」とキッパリ断わった。
「作家は自分で歩き、自分でモノを見て書くものです。取材原稿を基にして、良い作品が書けますか。費用も自分の仕事だから、自分で払います。それが作家としての私の流儀です」
そして、こうも付け加えた。
「良い作品を書けば、かならず読者が随(つ)いてきてくれます。そうなれば、単行本として刊行され、印税収入があります。取材にいくらお金がかかっても、最後には収支トントン、いやそれ以上入るかな」
担当編集者としては一本参った、といわざるを得ない。
「海軍甲事件」「海軍乙事件」もテーマが壮大すぎて、ふつうなら二の足を踏むシロモノである。ところがこの意欲的な作家は、いともあっさりと引き受けた。
いずれも連合艦隊司令長官の戦死という歴史的大事件で、前者はとくに米側の暗号解読による謀殺の疑いが濃いだけに、真相解明をせまる吉村さんの取材は徹底をきわめた。と同時に、作家の視点は山本長官機護衛の任を果たせなかった隻腕の青年下士官――その後の空戦で右手甲を吹き飛ばされた――や、また偶然、基地にいたために古賀長官機と福留参謀長機操縦の役割を担うことになった二式大艇の搭乗員の存在に視点を当てる。
戦局を左右する大事件勃発のために、出版ジャーナリズムの焦点は政治の流れ、海軍中央の動静に心奪われがちだが、この作家の眼はこうした歴史の襞にともすれば隠れてしまいがちな下級下士官のその後の人生にふれて、心温かい。
とくに山本長官機を目前で撃墜された一下士官の半生は、己の任務を果たせなかった贖罪感と事件の重大さに身の打ちひしがれる思いをしたにちがいない。戦後も、職業軍人の生活は決して恵まれていたわけでもなく、結婚をし家族を抱えてどのように人生の辛酸をなめてきたことか。
「海軍甲事件」の冒頭、元戦闘機パイロットの日常がさりげなく紹介されて、取材をおえたあと件の元下士官は、息子が医科大学に進学していて、その日、成人を迎えたという。南海の地獄の戦場を体験した後、ようやく安穏の晩年を迎えていることが描かれて、読後感も快い。
吉村さんの人間を見る眼は文学者としての鋭い感性に裏打ちされていて、隻腕の人物の戦後をくだくだしく説明することはない。読者には、別れぎわ「頭をさげる私に左手をふった」の一行で充分だ。
さて、「海軍乙事件」では一転して、記録文学者としての徹底的な事件解明がおこなわれる。昭和十九年三月三十一日、古賀長官機は悪天候に巻きこまれて遭難。行方不明となるが、二番機搭乗の福留繁参謀長他司令部員二名はフィリピン、セブ島沖に不時着水し、比島人ゲリラの捕虜となった。
重大視されたのは福留参謀長、山本祐二参謀がそれぞれ携行していたZ作戦計画書二冊と暗号書の行方である。これは米軍の本格的進攻にそなえて、千島から内南洋にいたる連合艦隊の迎撃作戦を定めたもので、もし敵手に陥ちれば日本側の不利は決定的となる。
このような軍機書類の紛失は国家的大事件――事実、後のレイテ湾海上決戦の場合、日本海軍の作戦は米側に見破られていた――にもかかわらず、海軍中央は福留少将の「現地人に奪われたが、かれらはほとんどそれらに関心をいだいてはいなかった」との釈明を信じ、それよりも比島ゲリラに参謀長が捕虜になったという不名誉をどのように処理するかが大問題となった。
福留証言が偽りであることは、作中でも明らかにされているが、事件の本質は海軍の名誉を守ることではなく、爾後の艦隊決戦において何万という海軍将兵が作戦行動の手の内が米側に筒抜けとなった状況で、何も知らず祖国のために生命を賭けて戦ったという悲惨な事実である。その責任は問われなければならない。
戦史に挑む作家吉村昭の原点は、歴史的事実にたいして一歩も躊躇しない真摯な態度である。本書でも防衛庁公式戦史『南西方面海軍作戦』の戦史編纂官が、「当時、機密書類の紛失について、あまり問題にされなかった」として事実に肉薄せず、真相解明を避けている点を鋭く指摘して、米側資料の具体的反証をあげている。
こうして戦史上、今まで謎とされてきた数々の疑問を公的機関でなく、吉村さんの個人的努力によって徹底的に解明された。筆者はその血のにじむような努力を垣間見て、絶対国防圏マリアナの失陥、レイテ湾海戦での無惨な敗北によって、万斛(ばんこく)の涙を呑んだ声なき将兵の魂がその敗因の真相が明らかにされたことで、いくらかは慰められると思われて仕方がない。