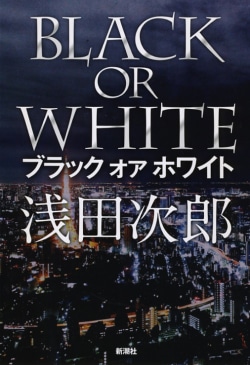『ブラック オア ホワイト』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
白い夢と黒い夢がくれるもの
[レビュアー] 中江有里(女優・作家)
人に話したくなるような夢を見ても、実際に話すとなると躊躇してしまう。内容があまりに個人的だと、気恥ずかしさが勝つ。自分の夢が、他人にとって面白く興味深いもの、という自信もない。
たとえば「龍の形をした雲を見たんですよ」と話したところで、実物のその雲を見ていない相手にとっては、まさに雲をつかむような話であろう。
そんなつかみどころのない「夢」を小説に取り込んだらどうなるか? これがとてつもなく愉快で、恐ろしい。小説の中の夢を脳内のスクリーンに映す快感を覚えた。
同級生の葬儀で再会した「私」と都築君。定年までの年数を相当残して会社を辞めた都築君から都心の高層マンションに誘われて、いつのまにか彼の夢の話を聞くことになる。エリート商社マンだった都築君から聞かされる幸福な「白い夢」と、グロテスクな「黒い夢」。その不思議な夢の話に引き込まれていく「私」。
夢の背景となるのは日本のバブル期。若い人が聞けば、昔話か、まるでよその世界の出来事だろうが、この国の土台には、向かうところ敵なしで経済大国を築き上げた日本人がいたのだ。そのひとりである都築君は、出張先のスイスの湖畔のホテルで、バトラーに硬い枕を注文する。そうして用意されたのが、それぞれ黒と白のカバーの掛かった二つの枕。
「ブラック・オア・ホワイト?」
この情景からすでに夢の世界が始まっているようだ。眠りの始まりは夢の始まりに通ずる、どこまでも曖昧で甘美な世界。筆で夢の世界に引きずり込まれたら、あとは行く末を見届けるしかない。
「白い夢」を堪能した後「黒い夢」を見ると、前者では味方だった人が、後者では悪意むき出しの顔を見せる。はたしてどちらが現実の顔なのか。ただし、これはあくまで夢なのだから、本当の顔などわからないのだ。そして魅惑的な女性も登場し、都築君を翻弄する。
自分の中にある自分でも気づいていない感情が夢にあらわれる、それはきっと誰にも覚えがあることではなかろうか。だからこそ都築君が見る夢の意味を考えてしまう。いったい何を暗示しているのだろう。たかが夢、されど夢。幻想と言い切れない自身の深層心理を探りたくなる。
一方で、「白い夢」と「黒い夢」を聞かされる「私」は、都築君がなぜ夢の話をするのか、と考える。都築君は自らの夢のせいで、順調だったキャリアを踏み外し、どんどん道を失っていく。それが「私」とどんな関係があるのか。「私」に語りながら、つまり読み手に語っている。やがて都築君の夢が、現実へと近づいてくるが、この先の夢の結末は見た(読んだ)人のもの。
ところで、夢を見ている時の感覚を思い出させる場面がある。都築君が京都で見た夢で、彼は武士になっている。それを夢だと自覚しながら、急に足に冷たい水がかかった際、「無礼者!」と水をかけた小僧を大声でしかりつける。
自分の立場も言葉使いも、時代と場面に合わせているのが面白い。たしかに夢を見ている自覚があるときには、その夢の世界のルールにいつのまにか自分を合わせている。その瞬間は、夢を楽しんでいるのだ。タイムスリップでもなく、異界に迷い込んだわけでもなく、あくまで自分の夢で。
一日は誰にとっても二四時間。「一日のうち、八時間を働き、八時間を眠り、八時間をそのほかのことに使っている。つまり、人生の三分の一は眠っているんだ」
人生の三分の一は、睡眠という誰とも共有出来ない孤独な時間の中にいる。よく考えてみると、夢と小説は似ている。小説は、作家の見ている夢のようなものだ。それを言葉というツールで読者に伝える。作家と読者はまったく同じ「夢」を見ることは出来ないけれど、よく似ている「夢」を見ているのだと思うと、三分の一の孤独が癒やされそうだ。