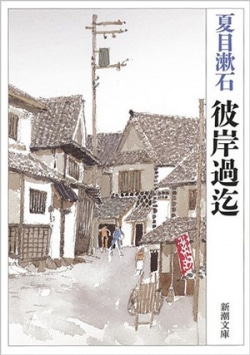『彼岸過迄』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
明治の東京を描いた「都市小説」――夏目漱石『彼岸過迄』
[レビュアー] 川本三郎(評論家)
漱石の作品のなかでは決して評価は高くない。しかし、明治末年の東京の町がよく描かれている都市小説として読むと他の作品にはない面白さがある。
敬太郎とその友人、須永という二人の青年が登場する。須永は「引っ込思案」で動きに乏しいが、敬太郎のほうは「浪漫趣味(ロマンチック)」があり、好奇心旺盛。地方出身者で東京を知るためによく歩く。
大学を卒業したばかりで目下、職を探しているのだが、時間の余裕はある。
本郷の木造三階建ての下宿に住んでいる。ある時、浅草へ遊びに行く。本郷から歩いてゆく。六区、浅草寺、雷門。雑踏のなかを歩く。現代風に言えば都市の遊歩者となる。
職探し中の敬太郎は、須永の叔父の実業家に就職を頼みに行く。そこで、神田小川町(おがわまち)の停留所で夕方に電車から降りる紳士を監視するようにと、探偵の仕事を与えられる。
敬太郎は夕方、小川町に行き、電車から紳士が降りるのを待つ。このくだりは探偵小説の妙味がある。十九世紀に誕生した探偵小説は都市小説でもある。
小川町は当時の繁華街。『坊っちゃん』(明治三十九年)の「おれ」はここに下宿していた。
本作は明治四十五年(一九一二)に書かれた。前年、東京史のなかで重要なことが起きている。それまで三社あった私鉄の路面電車が東京市に買い上げられ、市電になった。のちの都電である。三社のうちのひとつ、東京市街鉄道(街鉄)は『坊っちゃん』の「おれ」が東京に戻ってから就職した会社。
東京の町を市電が走る。漱石は新しく誕生した市電をいち早く作品のなかに取り入れたことになる。
とくに小川町は五つの路線が行き交う市電の町だった。紳士はどの電車から降りるか。敬太郎は目を凝らす。探偵は都市の観察者になる。
この小説には郊外も描かれる。敬太郎はある時、須永を誘って江戸川べりの柴又に行く。帝釈天のそばの川甚(かわじん)という店で鰻を食べる。いうまでもなく柴又はのち「男はつらいよ」の舞台となる。