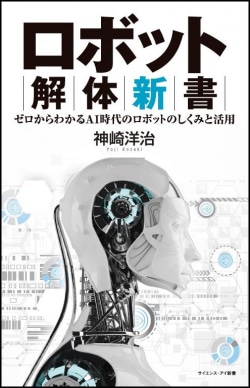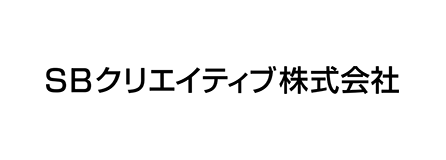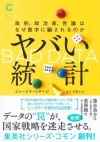-
- ロボット解体新書
- 価格:1,100円(税込)
掃除用ロボットや巡回警備ロボット、人型のコミュニケーションロボットなど、私達のまわりにはたくさんのロボットが存在しています。これら一般的なロボットよりもさらに人間に近いロボットの開発・研究を行う分野があります。「ヒューマノイド」や「アンドロイド」と呼ばれますが、どちらも造語で、「人のようなもの」という意味合いがあります。最近では、見た目が人間そっくりのヒューマノイドも登場してきていますが、メカメカしいロボットに比べて「怖い」「気持ち悪い」と感じる人も多いのではないでしょうか。『ロボット解体新書』(サイエンス・アイ新書)から、その理由を探っていきます。
「不気味の谷」とは何か
人間そっくりの姿を追求していくと、やがて周囲は不気味と感じる段階「不気味の谷」(uncanny valley)を迎え、その外観からさらに人間に近くなることで、人間同様のヒューマノイドのデザインにたどり着くとされています。
不気味の谷は1970年、東京工業大学名誉教授の森政弘氏が提唱したものです。ロボットは機械的なデザインから人間に近づけていくと、人びとの好感度は向上していきます。しかし、人間と同じデザインにいきつく手前において、好感度が急落して、不快感や嫌悪感を感じる段階があるとしています。
そっくりな人と会って「似すぎていて怖い」といいう感情に似ています。
その谷を超えて、さらに人間に近い、ほぼ同じだと認識できるデザインになると好感度がふたたび急上昇すると予測しています。好感度の動きをグラフにした際、好感度は人間と同様とみなす直前で大きな谷を形成することから、その落ち込みを「不気味の谷」と名づけました(図1)。
人型のロボットをデザインする場合、この概念を考慮して開発する必要があります。ロボットっぽい動きとデザイン、少し外観や動作が人間に近いアンドロイドは好感を感じますが、似すぎてしまうと不気味の谷によって、嫌悪感を抱かれる可能性が高くなります。
コンピュータグラフィックス(CG)を用いた映画やアニメーションでも同様の現象が起きるといえるでしょう。人間を描く際は不気味の谷に落ちないように、あえてリアリティを抑えたキャラクターデザインを行うケースもあるといわれています。

図1●不気味の谷
「マツコロイド」を監修した石黒教授の取り組み
ヒューマノイド研究の第一人者としては、大阪大学の石黒浩教授が知られています。テレビでお馴染みの「マツコロイド」も石黒氏の監修によるものです。
その石黒氏の「知能ロボット学研究室」(通称、石黒研究室)とATR(国際電気通信基礎技術研究所)のIRC知能ロボティクス研究所が共同で研究・開発しているアンドロイドが「ジェミノイド F」です。
「ミナミ」(通称)は、2012年11月に高島屋大阪店(大阪市中央区)で初公開された、人間の女性そっくりのロボットです。初公開された際は、タッチパネルで入力した質問に対してミナミが返事を返す仕組みで、精巧に創られた姿は肌の質感もリアルで、集まった多くの人たちはその外観に驚きました。
また、人間が遠隔操作によってミナミを動かして会話をすることもできます。2013年5月にふたたび高島屋に登場したときには、音声認識機能を追加し、簡単な会話ができる機能も搭載されたため、来店した人たちはアンドロイドとの会話を楽しんでいました。

2012年に高島屋で公開されたアンドロイド「ジェミノイド F」(通称、ミナミ)。(写真提供:株式会社国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所)
東京お台場にある日本科学未来館では、実際に見ることができるジェミノイドとして「オトナロイド」と「コドモロイド」が展示されていました。成人女性の見かけと表情、全身に40の自由度をもつ「オトナロイド」は、遠隔操作と音声合成による自律動作に対応しています。また、「コドモロイド」は見かけは子供の姿、全身30の自由度をもつニュースキャスターとして自律的に振る舞い、日本科学未来館に展示中は合成音声で科学ニュースなどをお知らせしていました。

オトナロイドは日本科学未来館で見ることができる。(写真提供:株式会社国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所)
石黒浩教授は自身にそっくりな「ジェミノイド HI」を開発したことでも注目されています。大阪大学が開発した「HI-4」は遠隔操作型アンドロイドで、コンプレッサーによる16個の空気アクチュエータで16の自由度(頭部:12、胴体:4)を実現しています。石黒浩教授が人間そっくりのアンドロイドを開発する理由は「ロボットらしいロボットだけでなく、人間らしいロボットを用いて、人間のもつ存在感の解明を目的」としています。
すなわち、人間のようなロボットを開発することで人間とは何か、人間の存在とはどういうものか、人の存在感は遠隔地へ伝達することができるか、などの疑問を解明するために研究しているのです。
石黒浩教授の挑戦はつねに「不気味の谷」と向かい合わせ、いつかこの谷を越える研究なのかもしれません。
──◆◇◆
これから数年は人工知能関連技術が社会に変革をもたらす時代になるともいわれています。それはロボットの能力の飛躍も意味しています。これから先の未来に、ロボットと人工知能がどのように進化していくのか、そして、どのように人間とかかわっていくのか、とても楽しみです。

石黒浩教授と京都大学大学院情報学研究科の河原たち也教授らが開発した自律対話型アンドロイド「ERICA」(エリカ)。人間そっくりの部分に、あえて人工的なデザインが取り入れられているように感じる。(写真提供:株式会社国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所)
SBクリエイティブ株式会社のご案内
SBクリエイティブが出版しているビジネス書、実用書、IT書、科学書籍の関連記事や、著者自身の解説による動画コンテンツなどを配信しています。
関連ニュース
-
夏休みの読書感想文にお勧め『「のび太」という生きかた』 「スネオ版」もあります
[ニュース](ビジネス実用/経営・キャリア・MBA/社会学/評論・文学研究)
2018/08/04 -
知の巨人・佐藤優はなぜ「手書きノート」にこだわるのか?
[ニュース](言語学)
2019/05/23 -
ビジネス戦略にも通じる「戦車の戦い方」とは?
[ニュース](軍事)
2016/11/16 -
トランプ大統領誕生という「非合理」はなぜ起こったか?
[ニュース](政治/映画)
2016/11/10 -
【話題の本】『22世紀の民主主義 選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる』成田悠輔著
[ニュース](経済学・経済事情)
2022/09/15