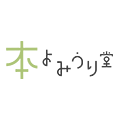5
-
- 1ミリの後悔もない、はずがない
- 価格:1,540円(税込)
自分だけ幸せではいけないような気がして、父に会いに行った。バス停まで迎えに来てくれた父は、想像よりふたまわり痩せていた。目がぎょろりと飛び出て、頬骨が高い。首には毛羽立ったタオル。汗なのか、酸っぱいような妙な匂いがした。
電灯の紐を引くと、心もとない光が四畳半を照らした。畳にマイルス・デイヴィスのCDとジョン・グリシャムの小説がちらばっている。ちゃぶ台の上には英字新聞。マグカップの跡が丸く残っている。室内に酒はなく、父ものんでいないようにふるまっていた。けれどわたしはのんでいると思った。それでどうということもなかった。父がわたしのすべてではなくなっていたからかもしれない。
「コーヒーのむか?」
袋入りコーヒーの粉末を空き瓶に移し替えながら父は訊いた。うんと答えて何気なく見ていると、父の手は陸に揚げられた魚のように激しくふるえて、粉を何度もこぼしていた。目を逸らした先に狭いベランダがあり、洗濯物がすこしだけ干してあった。
「ここは日当たりよさそうだね」
「あ? そうだな、洗濯物はよく乾くな」
「いいね、うちの庭は日が当たらないから。靴下が乾かなくて困る」
「そういうときはな」
と父は顔をこちらに向けた。そのとき動いた喉仏の形が、桐原のと似ていると思った。
「まずバスタオルを用意するんだ。それを広げてな、絞ったソックスをのせる。端からきっちりと巻いていく。そうすると大方の水分は取れる。それを干しとけば、乾くのが格段に早くなる」
「なるほどね、やってみる」
「やってみろ」
ちいさな冷蔵庫の脇に低い食品棚があり、そこにラーメンの袋があった。一食分を一度に食べ切ることはできないようで、半分に割った麺と調味袋が残っていた。
「あんときアメリカに行っとったらなあ」
百万遍もした話を、父はまたする。
母のお腹にわたしができたから、父は大学院をやめた。自分のやりたかったことを断念して、やりたくないことをやらなければならない日々がはじまった。
「おまえのせいで俺の人生めちゃくちゃだよ」
冗談めかして父は言う。聴きなれたセリフだから、もはやなんとも思わない。
以前アルコール病棟の喫煙所でも同じことを言われた。近くにいた断酒仲間は苦笑し、「娘さんがいなかったらたぶん、もっとめちゃくちゃでしたよ」と言った。
コーヒーを二杯のみおえると、父はわたしをバス停まで送ってくれた。自転車で。ペダルをキーコキーコ鳴らして。
「歩くより自転車の方が楽なんだよ」
「わたしがこぐから、お父さんうしろに乗ったら?」
「そんな恥ずかしいことができるか」
歩くと足のろれつが回らないんだね、と軽口を叩こうと思ったがやめた。父の眼が徐々に正気を取り戻し、鋭さを増しており、それはわたしにとって必ずしもよい兆候ではなかったから。
トタン屋根に雨粒の当たる音がしはじめる。黄昏の停留所にバスはやってこない。
「タバコ持ってくりゃよかった」
「もうここで大丈夫だよ。お父さん、帰っていいよ」
「シケモクはまずいんだよな」
「傘買ってこようか?」
「いらん。傘さして自転車なんかこげん、転んだら終わりだ」
父と並んで道路を眺めた。雨はどんどん強くなり、乗用車の撥(は)ねる水しぶきが白さを増す。
「おまえ」と言って父は一度、空咳をした。「つきあってる男がいるんだろ」
「だれから聞いたの」
「だれから聞かんでもわかる」
父は言った。バスはなかなか来ない。
「数学のできる男か」
「うん」
「そうか」
バスが来た。立ち上がろうとして父はよろめいた。慌てて手を取る。細くて長い、きれいな指だった。おーすまん、と言って父はさらりと手を離した。
ドアがひらく。ステップを踏んで、車内に乗り込んだ。
父が何か言ったのをかき消すように、背中でバスの扉が閉まった。呆然と突っ立っていると、整理券をお取りくださいとアナウンスされた。はっとして白い券をひっぱる。最後列まで、ふらふらと歩いた。父が見えた。細い身体で、雨に濡れながらこちらを向いて立っている。
まあ、おまえらがおったから、おもしろい人生やったかもしれん。
バスが動き出す。父はどんどんちいさくなっていく。

6
卒業式にはつめたい雨が降っていた。夕方にいったん上がったが、夜、西国分寺駅へ向かっているとき、再びぱらつきはじめた。降りだしはやわらかく絡みついてくるような霧雨だったのが、走っているうちに一気に勢いが増し、激しい春の嵐となった。
バシャバシャと水の音を立てながら、わたしはどしゃ降りの中を走り抜けた。傘も差さずに、髪も服もずぶぬれで、息を切らしてアスファルトの坂道を駆け下りた。楽しかった。桐原に会うために疾走しているときはいつも、命を生き切っているという実感があった。
桐原が見えた。大きな黒い傘を差して、不安げな顔で立っている。一直線に向かって行く。ソックスに泥水が跳ねる。鎖骨の上のチョーカーすら歓喜していた。ひざやスカートが上がるのといっしょに、ちいさな星はうれしそうにジャンプして肌に吸いついた。
細い道を斜めに突っ切ろうとしたとき、
「由井!」桐原が叫んだ。「あぶない! うしろバイク来てる!」
さっと八百屋の軒下に身体を寄せた。わたしの中で桐原の声が反響していた。あんなに大きな野太い声を聴いたのははじめてだ。立ち止まってバイクが通り過ぎるのを待っていると桐原がまた声を張った。
「そのままそこにいて!」
広い歩幅で飛ぶように走って、桐原はわたしを迎えにきた。
「用心して、たのむから」
めずらしくきつめの口調で言う桐原の顔は、青ざめていた。
傘を、桐原はほとんど倒すみたいにして差した。わたしは柄の部分をつかんで桐原の方に向けた。それを彼がふっと笑ってまた倒す。そんなことを繰り返しながら、ざんざん降りの雨の中を歩いた。濡れて身体にぴったり張り付く服も、ぐじゅぐじゅになったソックスもまったく気にならなかった。
ふいに桐原が足を止めた。わたしを見おろして、手を伸ばしてくる。
「風邪ひいちゃうな」
指が、わたしの髪にふれた。傘の下で、桐原の匂いが濃く立ちのぼる。
「うちで乾かそうか」
白い車がその日はなかった。桐原はポケットから鍵を出して差しこんだ。
家にはだれもいないようだった。広い玄関には、よく磨かれたハイヒールがあった。桐原の脱いだバスケットシューズが重そうでどきどきした。
「そこ洗面所、タオルとかドライヤーとか、好きに使っていいよ」
ありがとうと言って、脱いだソックスを手につま先立ちで向かう。髪の先から水が滴り落ちた。ドアが、迷子になりそうなほどたくさんあった。廊下はホコリひとつなくつるつるで、すべらないように注意しなければならなかった。無機質というか、しんと平らで、熱のようなものがまったく感じられない家だ。ほんとうに人が暮らしているのだろうか。
髪やスカートを乾かして戻ると、キッチンから音がした。行ってみるとそこには黒い角の尖ったテーブルがあり、カゴがのっていて、色とりどりのフルーツが盛られていた。雑誌に出てくる家みたいだ。ソファの正面には暖炉まであった。そんなものはどこか遠い外国にしか存在しないと思っていた。お盆を手に戻ってきた桐原は、階段の下にしゃがんでいたわたしを見おろして「なんでそんなところにいんの」と笑った。
「立派なおうちだなあと思って」
「そんなことないんじゃない」
「あるよ。金色の洗面台が二つ並んでて、びっくりした」
「二つ同時に使うことなんてないから意味ないんだよ」
「お父さんなんの仕事してるの」
桐原はすこし真顔になって「よく知らない」と言った。
階段を上りきった脇に、おしゃれな洗濯機があった。二階に洗濯機があるというのはどういう間取りなんだろうと思ったが、これはお金持ちのスタンダードかもしれないと思い直した。

八畳ほどの洋室だった。きちんと整えられたベッドに、勉強机とクローゼット。机の横にはCDデッキ。床に腰を下ろすと「なんでそんなところに」とまた笑われた。桐原が手渡してきたクッションを尻の下に敷く。わたしたちは向かいあって桐原が淹れた紅茶をのんだ。会話は弾まない。クッキーは妙にぼそぼそして喉をおりていかなかった。
ごめん、と桐原が言った。カチャリとカップを置く音が大きく響いた。
「俺いま、すごくやましい気持」
「どういう意味?」
「賭けをしないか」
顔を見上げてたじろいだ。これまでに見たことのない表情をしている。メガネの奥、目の縁が赤く染まり、つり上がって、怒っているみたいだ。桐原は立ち上がって窓辺まで歩くと、手招きした。わたしが来るのを待って、桐原は外を指差した。
「あそこ、遠いけどわかる? 線路が見えるでしょ。次来る電車は何色だと思う」
「そんなのわかんないよ」
「言ってみて。もし当たったら今日はまだ我慢するから」
「我慢て何を」
「さあ何をだろうね」
またした。今まで見せたことのない顔。桐原の黒髪の一本一本から放出されている、このぴりぴりしたものはいったいなんだろう。
「もう来ちゃうよ。このまま答えないうちに来たら俺の勝ちね」
言って桐原は、わたしのうしろに立った。「俺はオレンジ」わたしは腹をくくってシルバーと答えた。電車の音が聴こえてきた。
家と家のすきまから見える、西国分寺駅へ向かう線路。夜の膜を切り裂くように、やってきたのはオレンジ色の電車だった。頭の上で桐原が笑うのが息でわかった。
部屋の空気が動く。桐原がメガネを外す気配があった。それを勉強机にそっと置くと、桐原は背後からわたしの両脇に手を差し入れてきた。軽々と抱き上げるようにしてベッドの縁に座らされる。視線が合う。かわいらしい目だった。こんな目だったかな、と思う。メガネをかけるようになってからまた、骨格が変わったのかもしれない。桐原は床にひざをつくと、わたしの太ももに頭を載せてきた。腰に腕が回される。甘える子どもみたいだった。へそには桐原の後頭部が、太ももには頬がくっついて熱かった。わたしは自分の手の置き場に困って、迷った末に彼の髪にふれた。硬い髪をぎこちなく撫でた。胸がどくどくして声にならない。腰に置かれていた大きな掌が、背中に上がっていったかと思うと、急に強い力で引き寄せられた。
「スキー教室の夜もこんなふうにしたかった」
「じゃあ桐原は、反省文になんて書いたの」
「はっ、いまそんなこと思い出せんわ。たぶん、本当のことは何も書いてない」
「なんで自分が誘ったなんてうそをついたの」
桐原がわたしを見上げた。
「なんでだか、本気でわからないの?」
桐原を見おろすのははじめてだと気づく。ここからの角度だと顔立ちがずいぶん幼く見える。笑うわたしの口元に、桐原が手を伸ばしてきた。
「もし俺がいやなことをしたら言って」
「言ったら」
「言われてもやめないかもしれないけど、最善は尽くす」
「本当にするの? コンドームっていうのを、使わないとだめなんだよね?」
わたしが言うと桐原は「武士が丸腰で戦うはずがないだろう」と笑って立ち上がり、引き出しの奥に手を突っ込んだ。箱が出てきた。その使い方は合ってるみたいと言った口を口でふさがれる。桐原の身体にこんなにやわらかい部分があったことに驚いた。唇を合わせながら、息つぎするように桐原はシャツをぬいで、肌着をぬいだ。それから、大きな白い身体が覆いかぶさってくる。耳に桐原の息がかかった。首にも、肩にも、スタンプを押すように。それはとても熱くて、心地いい。
いざ挿入という段になって、わたしの性器は桐原の小指すら受け入れられなくなった。
「さっきは中指も入ったのにな」
「入れてみて、痛くても大丈夫だから」決心してわたしは目を閉じる。
やっとぜんぶ収まったと思ったのに、桐原はわたしの足首をつかんで広げ、さらに奥までぐっと押し込んできた。挿入後に男が動くということを知らなかったので、それが奇妙に感じられた。桐原の汗が、広がった黒髪からポタポタと落ちてきて、目にしみた。
終わってしばらくすると、桐原はていねいな手つきでシーツをはがして、部屋を出て行った。洗濯機を操作する音が聴こえてくる。
放心していると、桐原がもどってきた。手にはバスタオルを持っている。桐原はトランクス一枚だった。青いきれいなトランクス。制服を着ていた彼とは別人で、大人の男の人みたいに見える。裸の男の人というのは、物悲しいなと思った。
桐原が敷いてくれたバスタオルに座ると、夢みたいにふわふわしていた。向かい合うように座ってから「ねえ」と桐原は言った。「なんでそんなに早く服を着ちゃうの」
「はずかしいから」
「もっと見たい」
「やだよ。ほかの女子よりおっぱいちいさいし」
桐原はまじめな顔で首をふって、短く褒めた。それはわたしにとって賛美のように響いた。
大きな手が服の中に入ってくる。ごつごつした掌に、すっぽりつつまれた。桐原はあぐらをかいて、じっとわたしを見ている。顔があまりに熱いので目を伏せると、トランクスからにょきにょきと伸びてくる性器が見えた。理科の授業で、植物の成長の早回しビデオを見たときのことがよみがえる。その動きは、わたしに身震いするような感動をもたらした。わたしは桐原に求められている。目の前の愛しい男は今、わたしに受け入れてもらうことだけを渇望している。ずっと探していたものはこれだったんだ。わたしはその植物に手を伸ばす。撫でてみる。つばを飲み込む音が立った。わたしのものか、桐原のものかわからない。顔を上げると、桐原のうつくしい喉仏がコリ、コリ、と動いた。

7
電話が鳴って、わたしは現実に引き戻される。いそいで手をぬぐって、通話ボタンを押す。「ちょっと疲れたから電話してみた」と夫は言った。「今日の晩メシ何?」
「ちらしずし、はまぐりのお吸い物、茶碗蒸し」
「おっいいね、ひな祭りっぽいね」
「あとはイカ大根。大学芋も作るよ」
「うわー、今すぐ帰りたい。仕事が多すぎるよ。もう明日の僕に頑張ってもらおうかなあ」
「ねえ、イカのなかに魚が入ってたのよ」
「えっ、なんの魚?」
「知らない。もうすてちゃった」
「なんですてたの」
「毒があったら怖いじゃない」
「魚もさばいてみたらよかったのに。もう一匹入ってたかもよ」
手がかゆい。心がかゆい。桐原の声がよみがえる。
うしなった人間に対して一ミリの後悔もないということが、ありうるだろうか。
大人になった桐原は、どんなふうに携帯電話に触れるのだろう。タバコは喫うだろうか。あれから背はさらに伸びただろうか。今、どんな服を着て、誰といっしょにいるのだろう。
中学を卒業して、桐原は有名私立高に進んだ。わたしは定時制の高校に入ったが、高一の夏にとつぜん遠くへ越すことになった。
あの夜、オレンジ色の電車が来るのを知っていたことは言わずじまいだった。
桐原と出会ってはじめて、自分は生まれてよかったのだと思えた。彼を好きになるのと同時に、すこしだけ自分を好きになれた。桐原がわたしを大事にしてくれたから。
あの日々があったから、その後どんなに人に言えないような絶望があっても、わたしは生きてこられたのだと思う。
桐原が今笑っているといいと思いながら、二杯目のイカに手を伸ばす。
軟骨を引っこ抜いて、体内を覗き込んだ。いくら覗いても、そこにはもう何もない。
(カット 沿志)
*イラストはウェブでの立ち読み版限定で入っています。
株式会社新潮社のご案内
1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。
▼新潮社の平成ベストセラー100
https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/
関連ニュース
-
ピンクのモヒカンの父親と勉強嫌いの娘……こがけんの元相方・ピストジャムのドラマみたいな家庭教師体験 『こんなにバイトして芸人つづけなあかんか』試し読み
[試し読み](タレント本)
2022/12/31 -
世界史の教科書にも載っている偉人が、中国で「悪党」と嫌われた理由 『悪党たちの中華帝国』試し読み
[試し読み](世界史)
2022/09/16 -
「美少年」で読み解く、西洋美術の歴史 「芸術新潮1月号 永遠の美少年 深読みアート・ヒストリー」刊行記念
[イベント/関東](アート・建築・デザイン)
2016/12/30 -
作家・芦沢央と現代美術家・冨安由真が怪談の魅力を語る
[イベント/関東](ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2018/08/14 -
塩野七生からのメッセージ《資源のない日本は「人材」こそ「資源」とせよ!》[新書ベストセラー]
[ニュース](自己啓発)
2022/11/26