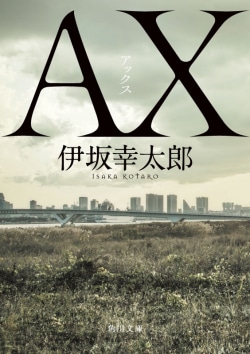伊坂幸太郎の最高峰エンターテインメント小説! 凄腕の殺し屋“兜”が――実は恐妻家!?『AX アックス』
レビュー
『AX アックス』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
伊坂幸太郎の最高峰エンターテインメント小説! 凄腕の殺し屋“兜”が――実は恐妻家!?『AX アックス』
[レビュアー] 杉江松恋(書評家)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:杉江 松恋 / 書評家)
伊坂幸太郎は死の不安を書く作家だ。
口にする機会は少ないが、皆がそれを抱えて生きている。いや、生きるということ自体が、死の気配から目を逸らし続ける行為と等しいと言ってもいい。
背後に迫る死の影に、誰も気がつかないふりをしている。だが、ときどき伊坂は振り向いて、それが自分の後ろにいることを確かめようとする。恐怖映画に悲鳴を上げる子供が、指の隙間から画面を観るのをやめられないように。怖がりは、確認したがりでもあるのだ。
死が怖いからこそ、伊坂はその死を主題にした小説を書くのだと私は考えている。
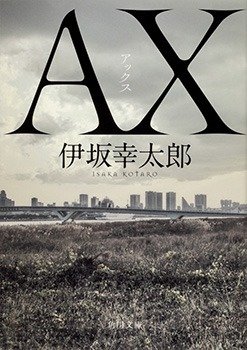
角川文庫『AX アックス』
『AX』の単行本版は二〇一七年七月二十八日に発売された。二〇〇四年の『グラスホッパー』、二〇一〇年の『マリアビートル』(いずれも現・角川文庫)に続く、殺し屋が主要人物として登場する小説の第三弾である。それまでは書き下ろしの長篇だったが、本作は初めて連作短篇集形式になった。前二作がバッタ(グラスホッパー)、テントウムシ(マリアビートル)と題名に昆虫の名前が使われていたのに対し、本作では「AX」、つまり斧という道具になっている。これは第一話のタイトルだ(初出:「小説 野性時代」二〇一二年一月号)。おや、と思って同話を読むとすぐに種明かしがある。主人公の兜が息子と交わす会話が「蟷螂(とうろう)の斧」という成語に関するものなのだ。
「でもそのことわざは、カマキリもその気になれば、一発かませるぞ、という意味合いではないんだろ」
「どちらかといえば、はかない抵抗という意味だ」
伊坂は一作ごとに異なる技巧を凝らす作家で、本作でもさまざまな手が試されている。今書いた蟷螂の斧のやりとりもその一つだ。読者は本のどこかでこの会話をもう一度思い出すことになるだろう。忘れたころに戻ってくるブーメラン、という伏線の技巧は伊坂が二〇〇七年の『ゴールデンスランバー』(現・新潮文庫)で極めたものだ。
『AX』では前二作に登場した殺し屋たちの消息が語られる。『グラスホッパー』の解説にも書いた通り、伊坂にはもともと、事故死に見せかけて人を消す殺し屋が多数出てくる小説という構想があったのだという。さまざまな殺し技を考えたが、物語として書くことを考えて、人を事故死させる押し屋、説得して相手に死を選ばせる自殺屋、ナイフ使いの三人だけが残った。これが『グラスホッパー』で、押し屋こと槿(あさがお)は『AX』にも顔を出す。

角川文庫『グラスホッパー』
続く『マリアビートル』にも檸檬と蜜柑なるコンビや、てんとう虫と呼ばれるツキのない殺し屋が登場する。頻繁に視点人物が入れ替わる三人称多視点の文体は伊坂作品ではおなじみだが、この連作では誰が章の主役なのかが印鑑で示される趣向が採用されている。「槿」「天道虫」といったハンコが章の頭に押されるのだ。注意深く読むと、この印鑑にはもう一つの仕掛けが隠されていることがわかる。前作『マリアビートル』では気づかなかった方も、ぜひ本書で確認してもらいたい。

角川文庫『マリアビートル』
さきほど主人公を兜と書いたが、本名ではなく通り名である。カブトムシからとられたもので、最初は伊坂がクワガタムシが好きなところから大鍬という名だったという。彼の本名は三宅であることが、第三話の「Crayon」(初出:「小説 野性時代」二〇一四年二月号)でわかる。殺し屋の本名が明かされるのは、これが初めてだ。
既に書いた通り『AX』は初の連作短篇集だが、もう一つ異なる点がある。前二作が殺し屋が暗躍する事態に巻き込まれた一般人の恐怖を描いたスリラーだったのに対し、本作ではその殺し屋自身が主役なのである。兜の表の顔は会社員だ。偽装ではなく、ちゃんと文房具メーカーの会社員として働いている。家に帰れば克巳という高校生の息子がいる普通の父親でもある。普通と違うのは彼が並外れた恐妻家だという点か。解説から目を通す習慣のある方は、とりあえずここで表題作の冒頭数ページだけでもお目通し願いたい。熟睡している妻を物音で起こすのが怖いから夜食は魚肉ソーセージに限る、と力説している人物。それが我らが主人公の兜なのだ。これでも腕利きの殺し屋である。
『AX』への影響関係は定かではないが、読むと連想せざるをえないのが伊坂自身も愛読者だと表明しているアメリカの作家、ローレンス・ブロックの〈殺し屋ケラー〉シリーズだ。依頼を受ければどこへでも出張していき、獲物を始末して帰ってくるという殺し屋を主人公にした連作で、ブロックが一九九四年から断続的に発表していた短篇が一九九八年に『殺し屋』という作品集としてまとまった。日本での翻訳も同年である(二見文庫ザ・ミステリ・コレクション)。このケラーの姿が、私には兜と重なって見えるのだ。
ケラーの連作では、淡々と日々を過ごす主人公が突如殺戮(さつりく)機械に変貌し、標的の命を奪う。その切り替えがあまりに素早く、日常と非日常の境目が見えないこと、一切の感情が描かれず、道徳律から無縁であるように描かれることから、ケラーにはとてつもなく非人間的な主人公という印象がある。彼の日常パートは穏やかなユーモアと共に語られるので、余計に落差は激しい。
本書でも、同種の演出によって非情さが強調されている。たとえば第一話では、息子の進路相談に駆けつけるために、兜がそそくさと標的を殺して高校に急行する。この境目のなさが肝で、殺人による死と家族の重大な行事という生に属する事柄が一続きで描かれる。ホームドラマが演じられている中に突然侵入してきた殺し屋、という違和感が忘れがたい印象を残すのである。
『グラスホッパー』は無機質な殺し屋が跋扈する世界を描いて不条理観の溢れるスリラーとなった。これは第二長篇『ラッシュライフ』(二〇〇二年。現・新潮文庫)から始まって、やがてディストピア小説『モダンタイムス』(二〇〇八年。現・講談社文庫)で結実する、現代人の抱える漠然とした不安を主題とする小説の系譜にも連なる作品である。次の『マリアビートル』は、話の舞台を東北新幹線という密閉空間の中に限定したアクション小説で、前作とはがらりと風合いが異なる。近い作風を求めるならば、アメリカの作家ドナルド・E・ウェストレイクの影響が感じられるスラップスティックな犯罪小説『陽気なギャングが地球を回す』(二〇〇三年。現・祥伝社文庫)か。また、作中には法で罰することが難しい極悪人が登場するが、これも伊坂の作品にはよく出てくるタイプの敵役で、『死神の浮力』(二〇一三年。現・文春文庫)などが連想される。
殺し屋の出てくる小説といっても、毎回風合いは異なるのである。家族小説と犯罪小説の合体が試みられたのが第三作である『AX』で、その結果として接合面にいる兜という主人公の個性が際立って見えることになった。父親であり夫である兜と殺し屋の兜という二つの顔は、本来一人で併せ持つことが難しく、かけ離れたものだ。話が進むにしたがって乖離(かいり)と相克が兜の中では大きなものになっていく。この葛藤が描かれるのも過去作にはない特徴である。
最初に書いたように伊坂は死の不安を描く作家だ。同時に伊坂には、家族という生のつながりを描く作家という一面もあり、この二つは根底でつながっていると私は考える。家族という要素が小説の前面に出てきた最初は二〇〇三年の『重力ピエロ』(現・新潮文庫)だ。同作では主人公と弟の関係を通じて、血のつながりだけが家族なのか、という問いかけが行われる。後に『オー!ファーザー』(二〇一〇年。現・新潮文庫)でも同じように伊坂は家族の多様性を題材にするが、自分という存在は個として完結したものではなく、他者との関係を通じて時間軸上に広がっている、という認識が伊坂作品には見えることが多い。その最も小さな単位が家族なのだ。
年代記の形式で書かれた『あるキング』(二〇〇九年。現・新潮文庫/徳間文庫)は、その単位自体を題材にした小説である。家族小説ではないが、まったく関係ない出来事の因果がまわりまわって意外な結果を呼ぶ『SOSの猿』(二〇〇九年。現・中公文庫)や『PK』(二〇一二年。現・講談社文庫)などにも背景に同種の思考を読み取れる。時間軸上に自分の延長が残っている間は、自分は終わらず、孤独ではないのだ。そう考えることが、死への不安に対抗するための根拠となる。
実は殺し屋の男を主人公とする『AX』にも、そうした要素が備わっているのである。引き裂かれた自己を持つ男が、家族を通じて本来の自分は何かを考える小説なのだ。
本書の執筆期間には、中断期間がある。「AX」、「BEE」(初出:宝島社刊『しあわせなミステリー』二〇一二年四月刊。二〇一四年三月に『ほっこりミステリー』と改題して宝島社文庫)、「Crayon」の三作が書かれた後、「EXIT」「FINE」の二話が書き下ろされて単行本が二〇一七年に出るまで、三年空いているのだ。これは、伊坂が当初の予定を変更したためである。収録作の頭文字を並べるとABCEFとなって不自然であることにお気づきだろう。本来は「Drive」という一篇が予定されていたのである。
「小説 野性時代」の二〇一五年十一月号に「Drive/イントロ」と題された作品が掲載されている。これは兜が家族と房総半島にドライブ旅行に出かける途中で殺し屋の仕事をこなさなければならなくなるという出だしで、最終的には妻や子供に気づかれないようにして任務を遂行する、という構想だったようだ。作品には斧田という害虫駆除業を営む人物が登場する。名前からすると重要な役割を担っていた可能性があるが、今となっては、作者の意図は知りようもない。
当時のインタビューによれば阿部和重との合作『キャプテンサンダーボルト』(二〇一四年。現・文春文庫)と『火星に住むつもりかい?』(二〇一五年。現・光文社文庫)を発表した後で燃え尽き症候群のようになってしまい、「Drive」を続けられなくなってしまったのだという。この話を最後に持ってきて単行本化するという目論見が崩れたが、代わりに「EXIT」「FINE」の二篇で物語をしめくくるという案が浮上した。そのきっかけになったのは新海誠監督の映画『君の名は。』だったというからおもしろい。構造を分解してみると、『君の名は。』には本書と重要な共通項がある。できれば「FINE」まで読んだ後、映画を観直してみていただきたい。
書き下ろされた二篇で印象的なのは「EXIT」に古山高麗男『プレオー8(ユイツト)の夜明け』(一九七〇年。現・講談社文芸文庫他)が引用されていることで、前述した兜の葛藤は、この地点から表面化し始める。「Drive」が幻の作品になってしまったのは残念だが、後半の書き下ろし二篇を加えたことで、本としての『AX』は伊坂幸太郎という作家の全容を体現した奥行のある作品になった。夜の百貨店内での闘争という痺れるような活劇場面を持つ「EXIT」は犯罪小説の短篇として単体としても抜群なのだが、連作全体の折り返し点としても十二分に機能している。ここで用いられる「大事なことほどさらっと言う」技巧や、次の「FINE」でも披露される伏線の見せ方はすべての伊坂作品を通じても上位に来る見事さである。あ、「モブの中に実は重要な役者が隠れている」も加えなければ。
書きたいことはまだまだあるが、そろそろお暇の頃合いである。二〇一七年の伊坂は、七月に本作を上梓したあと、九月に書き下ろしで『ホワイトラビット』(新潮社)を出した。作者とは『ラッシュライフ』以来の長い付き合いとなる、泥棒・黒澤を主人公にした企み溢れる長篇である。また、十月には初の絵本『クリスマスを探偵と』(河出書房新社)も発表している。成果に満ちた一年であったし、兜という読者の心に忘れられない記憶を残す主人公を書き切ったことで充実感もあったのではないか。
この解説を書くために『AX』をまた読み返した。誰の人生にも小さな幸せが訪れることはある。それを書いた小説でもあるんだな、と思いながら何度目かになる再読を終えた。
▶伊坂幸太郎『AX アックス』特設サイト(https://promo.kadokawa.co.jp/ax/)