赤川次郎の大人気シリーズ! 人気与力の本性を暴くため大泥棒〈鼠〉が江戸の夜を駆ける『鼠、嘘つきは役人の始まり』
レビュー
『鼠、嘘つきは役人の始まり』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
赤川次郎の大人気シリーズ! 人気与力の本性を暴くため大泥棒〈鼠〉が江戸の夜を駆ける『鼠、嘘つきは役人の始まり』
[レビュアー] 縄田一男(文芸評論家)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:縄田 一男 / 文芸評論家)
赤川次郎さんの〈鼠〉シリーズ第一集『鼠、江戸を疾る』が角川書店から刊行されたのが二〇〇四年十二月、そして巻を重ねて記念すべき第十集となる本書『鼠、噓つきは役人の始まり』の刊行が二〇一六年の十二月。十二年以上も続く長期シリーズを久方ぶりに読み返して、何でこんなことに気がつかなかったのだろう、という発見が二つ、私にはあった。
一つは、このシリーズが読者を幸福にするそれであるということ──そんなことは当たり前じゃないか、という読者諸氏もおられるに違いない。しかしながら、私は、あることを確かめたくて、思わず担当編集者に電話をし、「〈鼠〉シリーズの読者の年齢層は現代ものより高いですか?」と尋ねてみた。すると「特に高いということはなく、いつもの赤川さんの読者と同じです」という答えが返ってくるではないか。
もったいない、私は年輩の読者にこそ、このシリーズを読んでもらいたい、と思った。というのも、〈鼠〉シリーズにおける、物語の運び、登場人物の所作、台詞、間の取り方──これらは、一九四〇年代後半から六〇年代中頃の戦後日本映画黄金時代に、週替わりで封切られていた滅法イキのいい、時には現代調の明朗極まりない時代劇のテイストを含んでいると思ったからだ。
主演は東映なら中村錦之助(萬屋錦之介)、監督は沢島忠。大映なら主演は市川雷蔵、監督は田中徳三といったところか。それらを浴びるほど堪能されたのが、いま、年輩となっている方々なのだ。
例えば、第一話「鼠、横車を押す」の(ここからは作品の内容に立ち入るので、是非とも本文の方を先に読んで下さい)ラスト、鼠が、鼓の方が観劇をしている桟敷に槍を投げ、それをスリの名人「風の吾助」に弟子入り志願をした浪人・笠井松ノ介が、助けると見せかけて、あることをするシーンなど、もう東映時代劇の芝居小屋のセットが目に浮かんでくるではないか。
また、さとと小袖の駕籠が入れ替わる場面では、特に詳細な説明はないが、かつての映画ファンは、こうした二人の女優の競艶を観て、やんやの喝采をおくったものだった。加えて、「余は当藩剣術指南役より、『まれに見る剣客』と言われているのだぞ」とのたまう裸の王様然とした殿様の登場とくれば、私は第一話からすっかり嬉しくなってしまった。
続いて第二話「鼠、雨の夜の人助け」は、他人の空似と思われた武士二人、実は──というところで物語は逆転していくが、ここから、私のもう一つの発見が如実に示されていくのだが、そのことは後でまとめて記そうと思う。
さらに第三話「鼠、空っ風に向う」では、謎の「おさとさま」をめぐって、剣吞な討ち入り騒ぎが起こるが、侍社会を戯画化したような、「おさとさま」と家臣との関係が笑いを誘う。
そしてこの話にも名場面、名台詞がある。鼠の、
「屋根の上じゃ、俺の方が慣れてるぜ」
という台詞にはじまり、
「誰だ!」
「猫じゃねえ、〈鼠〉だよ」
匕首(あいくち)が空を切って、よけようとした武久(たけひさ)は瓦(かわら)に足が滑って、そのまま転落した。
と綴られるくだり。
こういう場面を大川橋蔵あたりにやってもらいたかったねえ。橋蔵は「大江戸の俠児」という作品で鼠小僧を演じており、名作といっていい出来栄えだったが、監督が加藤泰であったため、シリアスな内容だった。
粋でいなせな鼠小僧も演じてもらいたかったと、私の妄想はふくらむのであった。
そして表題作に登場するのは、いまや、江戸で〈鼠〉と人気を二分する奉行所の与力・〈鬼万〉こと神原万治郎。但し、この〈鬼万〉のやり方は、相当、荒っぽい。盗みの現場で盗賊を斬るのはまだしも、その家族までをも皆殺しにするのである。まるで兇刃である。
ところが、〈鬼万〉の座敷に呼ばれて気に入られた〈鼠〉の知り合いの芸者・鈴乃は、その眼力で、
「あの飲み方、酔い方は普通じゃないね。すぐにカッとなって刀に手をかけるあたり、何か胸の中に辛いものを抱えてるよ」
と見抜く。
その人間的苦悩が〈鬼万〉の別の顔をつくってしまったのだ。表題作はこの一巻の中でも最も陰翳に富んだものになっているが、〈鬼万〉に斬られた盗っ人喜多次の娘であるお豊が、女医師・千草の診療所で働くことになったのが、唯一の救いだろう。
そしてこの一篇も、私の二つ目の発見が色濃く出ている作品なのだ。
次なる第五話「鼠、刺客修業の裏表」は、〈鼠〉の妹・小袖の道場仲間(といっても小袖の方が師範代なのだが)米原広之進が刺客を差し向けられる、というのが発端である。しかもその理由が不義密通の遺恨というのだから驚きだ。もちろん、広之進の身におぼえがないのは当然だ。
しかも、おかしいのは刺客としてやって来た浪人は、強いのか弱いのかその力量はまったく不明。実は貧乏故に猿若町の芝居小屋で、「馬の足」をやっていて、これが絶品という人物。佐伯康ノ介といって病気の妻女を抱え、金欲しさに刺客となったものの、その出来はあまり芳しくはない。
それに、
「何ごとも、道を究めるのは同じことです。おかげさまで『足』の面白さも分って来ました」
といい出すのだから悪人であろうはずはない。
そしてこの物語では、ラストで敵役と思われていた人物の本心が明らかになり、読者もホッとされただろう。
そしてこの一巻も、第六話「鼠、天井裏に眠る」で幕になる。
発端は、国枝藩江戸屋敷の天井裏に忍び込んだ〈鼠〉が、白骨死体を見つけるという怪奇的なもの。しかし、この猟奇的な話が、本書最大の爆笑篇になろうとは、この時点で一体誰が想像し得ただろうか。
当然だが、この白骨には秘密があり、屋敷で寝ずの番をしていたが、重い〈眠り病〉を抱えていた田崎弘太郎は、本人は何も覚えていないのだが、ある理由から何度も殺されかける。何度も、というのは、この弘太郎、まるでロシアの怪僧ラスプーチン並のたくましい生命力があり、煮ても焼いても一向に死出の旅路に出ることもなく、ある時は天下無双の怪力の女中お照の努力もあり、〝田崎が生きている〟と皆を驚かす。
そして、掛軸一本を盗むために屋敷に忍び込み、この事件に巻き込まれた〈鼠〉は、白骨の一件の黒幕が、先代の殿様の奥方で、いまは出家した円月院であることを知る。
時代小説や時代劇を少しでもかじったことのある方なら、もうお分かりですね──。
〈眠〉
と、
〈円月〉
と来れば、故柴田錬三郎が創造した戦後最大のヒーローの一人、円月殺法の使い手、眠狂四郎ではありませんか。
そして、眠狂四郎がつかう円月殺法とは、剣を下段に構え、ゆっくり円を描く。相手は一瞬の眠りに誘い込まれ、狂四郎が円を描ききるまで持ちこたえた者はいないという。
狂四郎といえば市川雷蔵の当たり役。雷蔵も初期は、〈濡れ髪〉シリーズなど現代調のユーモア時代劇が光っていたが、狂四郎を自分のものにしてからは、その演技にますます磨きがかかった。
しかし、三十代半ばで病気に倒れ、帰らぬ人に。狂四郎シリーズの最終作となった「眠狂四郎 悪女狩り」では、雷蔵の出番を少なくするため、江原真二郎の贋狂四郎を登場させている。そしてラストの対決シーンの雷蔵の台詞に「俺はいままで狂四郎は何人いても良いと思っていたが、やはり狂四郎は一人でなければならぬ」というのがあり、何やら遺言めく。
さて、余談が過ぎたので、私の二つ目の発見について記しておくと、この一巻は、これだけ読者を楽しませ、幸福にさえしておきながら、一貫してシビアなテーマを打ち出している。
それは一言でいえば、侍は封建時代の奴隷である、というものだ。
本書の中で、ユーモラスなものも、ハードなものも、多くは封建制度の基盤となっている家や藩に縛られて事件を起こしているではないか。
例えば表題作に示された〈鬼万〉の悲痛な叫びを聞いてみよう。
「その呼び方だ。〈鬼万〉なぞと。俺は人間だ。鬼なんかではない」
「俺はな、神原家に婿養子に入ったのだ」
「女房も、初めから俺のことを見下していた。義母はもちろん、使用人でさえ、俺のことをさげすむような目で眺めていた」
そんな〈鬼万〉の救いは情け容赦なく手柄を立てることしかなかった。
「鼠、空っ風に向う」の馬鹿馬鹿しい討ち入り騒動や、「鼠、雨の夜の人助け」の米の買いつけをめぐる遺恨、「鼠、刺客修業の裏表」における抜け荷への誘惑等々──。
〈鼠〉はそんな武家社会のしがらみを軽々と超越して、読者に胸のすく思いを与えてくれる。一巻読み終わっても、すぐまた次が読みたくなる。それが〈鼠〉シリーズなのである。
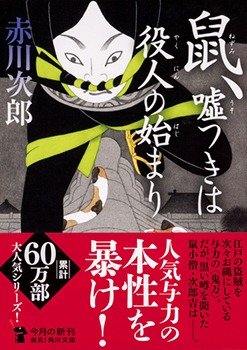
赤川次郎『鼠、嘘つきは役人の始まり』
▼赤川次郎『鼠、嘘つきは役人の始まり』の詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321902000557/


































