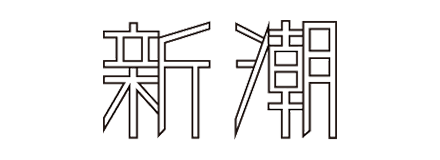(トランスジェンダー)女性が綴った葛藤「男でも女でもなく、社会問題化した“LGBTQ”でもなく、“わたし”として生きる自由を」
特集

鈴木みのりさん(撮影:森栄喜)
大学中退、正規雇用に就いた経験なし、思春期の頃から自身の性に違和感を持ち、トランスジェンダーとして、女性として、葛藤と模索を続けてきたライターの鈴木みのり(38)さん。現在はジェンダーやセクシュアリティの考察を続ける一方、舞台俳優としても活動する鈴木さんが、これまで抱いてきた感情の揺らぎを見つめ直しながら、当事者としての考えを論考という形で明かした。
学校や家庭、職場、創作の現場など、あらゆる場所で差別を感じてきたこと、「LGBTQ」という言葉に違和感を抱くようになったことなど、自身の経験や思いを率直且つ丁寧に綴る。(「新潮」3月号掲載「わたしの声の複数」を加筆修正したものです)
***
わたしは擬態する。スカートを穿く。下地を塗ったら、オレンジのコンシーラーで目の下の青い陰を補色して、その下にはイエローのコンシーラーで頬周りに透明感を出す。瞼にはアイシャドウを何色か重ねて、アイラインを引く。チークを入れる。ほとんど毎日、こうしないと気が済まない。スカートを穿くのは女性的な衣類とされているから。Tシャツ選びの際は、筋肉質で太くなる腕の部位が隠れるよう袖の微妙な長短を見極める。肩幅が目立つスタイリングをして出かけてしまったら、早く家に帰りたくなる。20代の初めごろから、裸の自分の寸胴を想像して、カバーできる服を探して必ず試着を重ね、視覚的に補正できるか確かめてきた。
メイクやファッションの華やかさにときめいて楽しんでいるし、好きという気持ちもしっかりある。まったく主体性がないわけじゃない。けれど、義務感も拭えない。自分のために美しくありたいというより、「女性」として整合性が取れているかどうかいつも不安だから。
毎月伊勢丹のコスメ売り場でメイクアップ用品を何かひとつは買う。わくわくしながら悩んで手にした新作のアイカラーが使い切るまもなく古く感じられて、また次の新作を買わないといけない気がするのは、違う顔を見せないと「女性」としての新鮮さが失われてしまうと感じられるからかもしれない。ハイファッションの衣類は、生地をていねいに惜しげもなく使われたパターンの妙で、隆起の乏しいわたしの胸や腰に女性的な立体感、ふくよかさを象ってくれる。写真に収めた平面では、同じように見えるデザインのファストファッションの服と比較して、着たときの違いがはっきりする(生地の質も良くて劣化しにくいから長く着られるし)。でも毎年、春夏と秋冬、何を買おうか新作に追われている感に疲れてもいる。
デートの日には新しい下着をおろしたり、168cmの身長をさらに高くしないようにフラットなソールの靴を選ぶこともある。ユニクロのコットンのワンピースだけ着ている楽な部屋着姿で、ときどき、この最大限の努力はなんのためなのかと考え、わからなくなる。装飾された自分と裸の自分のどちらに価値があるなんて単純に比較できない。表面と中身どっちも大事だし、両者はどこかで繋がっていると思う。そういうことじゃない、わたしが悩んでいるのは。
「性同一性障害」からトランスジェンダーへ
中学生になって、脛や腕に生えてくる毛がなぜだか嫌で、剃っていた。あるとき深爪が悪化して手術することになった。術前の剃毛の際、すでに剃られているわたしの足を前に、母が笑いながら看護師さんと何か話していた。照れというか、とにかく取り繕っているような感じ。剃毛は恥ずかしい行為なのだとわたしは受け取った。すね毛を生やしっぱなしにするのが当たり前という期待を向けられていると感じられて、居心地が悪かった。まだ自分のジェンダー(なんて言葉も知らず)がなんなのか、考えたこともなかったころの話。
トランスジェンダーという属性を知った2000年の春より1年近く前の初夏、縁があって知り合った若い精神科医がインターネットで調べてくれて、「性同一性障害」という言葉を知った。男性的に成長する身体に違和感を抱いていた17歳のわたしは、自分が何者なのかの落としどころがやっとわかった気がして、少し安堵した。そのさらに前の高校2年のあいだは、自分がこの世界に存在する場所がないと感じ、混乱していた。女性となるか、あるいは、男性として異性愛(ヘテロセクシュアル)かゲイと自覚するか、とにかくなんでもいいから自分で自分を受け入れられる状態を欲して毎夜祈り続ける、危機的な1年だった。その前の年の秋、学校である男性にときめきを感じた。そのことを普通に周りに話していたけれど、段々と「おかしい」という眼差しを向けられているのを察知し、世の中は、男女ふたつの性別にのみ分けられ、わたしは「男」に分類されているのだと気付いた。それまでも、すね毛の件や、立ちションが普通な男子トイレ(あの後ろ姿の無防備さと言ったら!)を嫌だと感じて避けたりしてきたけど、何かの理由で便宜的に「A/Bグループに分けられている」くらいにしか認識していなかったと思う。加えて、男女は互いに好意や性欲を抱くもの、つまりヘテロであるのが「当たり前」とされていることを知った。マンガ研究部の友人らと共有していたやおい(BLは当時はこう呼ばれていた)を通して、「ゲイ」という言葉は知っていたけれど、男性として男性に好意や性欲を抱く自分が想像できなかったし、テレビで見る「ニューハーフ」という存在も、美しさを徹底的に追求して女性化する様子がわたしからは遠かった。
「男性」と見なされること、制服はズボンを穿かなければいけないこと、体育の授業や修学旅行で「男子」と「女子」に分けられて前者に分類されること、「くん」付けで呼ばれること、ネイルやマスカラを塗って登校すると噂されること、「彼」という三人称で名指されることへの違和感や、ふくよかな胸のない身体や性器への嫌悪感が増していった。ギャルブームがあって、「egg」や「non-no」を読んで、ラルフ・ローレンやイーストボーイの紺色のカーディガンを羽織って、ルーズソックスを穿いていた、みんなをわたしは羨ましく思っていた。
その歪な状態を、伝えて良いのかもわからず言葉を探し続けながら、次は「性同一性障害」という呼称で説明すると向けられる、「病気だから仕方がない」という眼差しに抵抗を抱くようになった。2001年に『3年B組金八先生』で上戸彩が演じたキャラクターの影響で、一般に知られはじめた頃だった。社会的に不利という意味で「障害」は確かにあると、そう名乗る自分を納得させようとしたけれど、「病気」につきまとう例外化やネガティヴなイメージにわだかまりがあった。「心と身体の性別が違う」と説明されるのに、誰もその「心」の不確かさについて考えてなんてなくて、そこに男/女の性別があると信じているのが、わたしには信じられなかった。だって誰もが、周りや、テレビや雑誌の中のモデルや俳優から、女(男)らしい振る舞いや見た目みたいなものを感じ取って、それに倣ってパフォーマンスして生きているのだから。男/女らしさを本質的なものとしてしまう、「心の性別」説にわたしは与さない。
それよりも、大学1年の春に偶然手にとった本で知った「トランスジェンダー」という呼称は、あいまいだけど、自由な感じがした。この属性の呼称は、病理化などネガティヴなイメージを付す他者化ではなく、欧米を中心に当事者によって名乗られはじめたもの。それから10年近く経って、既存の性別に違和感を持たないことを「シスジェンダー」と呼ぶと知った。その言葉が、「普通」とされてきた人たちをジェンダーという尺度で捉え直すことで、トランスと同じ地平にいるのだと示すために生まれた。こうした自尊心の獲得の歴史に勇気づけられる。
鈴木みのり
1982年高知県生まれ。ライター。ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズムへの視点から書評、映画評などを執筆。「i-DJapan」「エトセトラ」「週刊金曜日」「週刊プレイボーイ」「すばる」「東洋経済オンライン」「ユリイカ」などに寄稿。2012年、タイでの性別適合手術(SRS)を収めたドキュメンタリー「THIS IS MY LIFE~心の声が聞こえますか?」に出演、番組が第50回ギャラクシー賞奨励賞を受賞する。利賀演劇人コンクール2016年奨励賞受賞作品に主演、衣装を担当する。
Twitter:@chang_minori
株式会社新潮社「新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shincho/
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
池上彰、三浦しをんも激賞 本屋大賞受賞作『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
[ニュース](思想・社会/社会学/科学/韓国・北朝鮮/生物・バイオテクノロジー/教育学)
2019/12/07 -
矢部太郎『大家さんと僕』ついに完結 涙の続編が初登場[ノンフィクションベストセラー]
[ニュース](コミック/本・図書館/タレント本/イラスト集・オフィシャルブック/エッセー・随筆)
2019/08/03 -
「自分の力で、世の中を変えていけ! 日本の未来に期待している」夭逝した瀧本哲史 「伝説の東大講義」が一冊に
[ニュース](哲学・思想/社会学/心理学)
2020/05/23 -
東野圭吾 超一流ホテルを舞台にしたミステリ「マスカレード」シリーズ待望の新作登場!
[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2017/09/23 -
第32回三島賞・山本賞の候補作が発表 岸政彦、金子薫、芦沢央など
[文学賞・賞](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2019/04/22