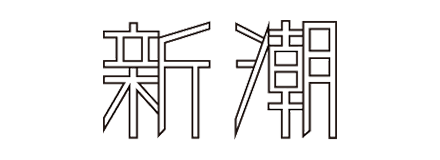(トランスジェンダー)女性が綴った葛藤「男でも女でもなく、社会問題化した“LGBTQ”でもなく、“わたし”として生きる自由を」
特集
恋愛における障壁
「仲の良い人といっしょに食事をしていたお店で、別の席の団体客から、新宿二丁目に習慣的に遊びに行くという大きな声が聞こえて、その声の主が帰り際にわたしを見て、やっぱりそうだよね? と誰かに耳打ちして小笑いしていたのが見えた」と綴った2年ほど前の日記を、先日見つけた。続いて書かれた「わたしといっしょにいるこの人も嘲笑の対象になるんじゃないかと懸念する」という気持ちは今でも拭えない。かつて飲み会で、「この人はこのあいだ手術を受けて」とわたしの性器に関して話題にされ、無思慮だと憤ったこともある。シス女性であるその人は、自分の生殖器の形状や身体の状態についていきなり話題にされても良いのだろうか。
こうしたささやかな日常の澱みが、世界への信頼を損ね、生存を脅かしかねない。
昨春、「仲の良い人」ともう会えなくなった。うまくいかなかった。長いあいだ話さえできればいいと、素直に触れ合いたいと求めることを避けてきた態度も影響したのだと思う(もちろんそれだけが理由ではないだろうけれど)。相手に(シス女性の)恋人ができた後に、わたしに対して性的な好奇心があったものの進展がなかったからそういう目で見られなくなった、というような話があった。はっきりと言葉にされたわけではないけれど、相手にとって、わたしの身体(特に性器)の状態を把握することも重要だったのだと理解した。
わたし自身も恋愛とセックスを結びつける価値観を内面化していて、好意を抱いた人と触れ合う心地良さを求めているにもかかわらず、欲望を封じ込めてきた。なんとなくのムードで察したりできる、シス・ヘテロ前提の恋愛の作法に則れたら楽なのに、と悔しくなる。ロマンティックさを保ったまま、どうやれば、どう言葉にすれば、わたしの身体への懸念を相手から拭い去れたのだろうかと考えても考えても、どうしてもわからない。
恋愛対象である男性から(トランス男性の可能性も含まれているけれどまだそういう感情を抱く対象と出会ったことはない)一時的に性欲を向けられることはあっても、継続的な信頼関係を築けた経験が、わたしにはほぼない。この乏しさが、自尊心の低さや、他人を欲望したり好意を抱く権利すらない存在だと自己規定する癖に繋がっている気がする。愛される資格がないのだと。わたしから、「興味がある」や「好き」を向けられても、迷惑がられるだろうと及び腰になる。
自分の身体について話すこと、開いていくことにとてもセンシティブになる。わたしにとって、「自分は女性である」と実感できるのは、異性愛の文脈で欲望されたり好かれたりすることを通して、なのに。もっと心を開いて、関係性を発展させたいのに。
「オネエ」「オカマ」一方的なイメージを押し付けられるニューハーフ女性たち
「生産性」という言葉から、「ニューハーフ」という立場を引き受けて生きているトランス女性たちを思い浮かべた。友達のインスタグラムやフェイスブックに登場する、主に水商売や風俗などセックスワーカーとして働くトランス女性たちの声、顔、振る舞い。
トランス女性だと告げただけで、「髪を伸ばした方がいいんじゃないか」とか「豊胸しないのか」とか助言されたり、女らしさという偏見と共にシス女性といかにちがうかという声をぶつけられる。「声の低さ」をあげつらわれるのはそのひとつで、その規範は、物理的にも発言すること自体へのハードルになる。例えばコンビニで、レジ袋はいらないとただそれだけを言うために発する声で、自分が異質なものだと見なされるのではないかという不安、怖さ。
シスに同化しないと一般的な社会に溶け込めない、「女性」と見なされないと知っているトランス女性たちは、肌の質感や顔の造形や身体のかたちを、ファッションやメイクアップや、人によっては美容整形を重ね、調整しようとする。容姿で性別を規定されたり、対応を変えられる。だから、一般的な仕事ではなく、「ニューハーフ」市場での接待業・セックスワークの道を消極的に選ばざるを得なかった、というトランス女性たちの声も聞いたことがある。忘れられない。
20代の半ばごろに非正規雇用で勤めていた会社で、同世代の経理の人から突然放たれた「どういう風に付き合ったら良いのかわからない!」という声がときどきリフレインする。まだトランスという言葉が一般的ではない時代に(今も周知だとは言えないと思うけど)、わたしが「男なのか女なのか」「同性愛なのか異性愛なのか」、あの一言にはたくさんの疑問が含まれていたと思う。面接のとき、採用にジェンダーを問わないという意味で「仕事ができればなんでもいいよ」と言われたこともある。トランスの人々が、その「仕事ができる」までにどういう障壁に阻まれて、どういう労力を費す必要があるのかが、伝わらない。知識で説明しようとすると「難しいこと考えているね」と切り捨てられる。
さらに、少なくないトランス女性が、ペニスの有無で「ニューハーフ」市場で値踏みされるからと、違和感があっても手術に踏み切れずに、男性的な部位と女性的な部位を引き受けて生きていることをわたしは知っている。
生身のひとりの人間として尊重されるのではなく、フィクショナルな女性性を押し付けられる不当な状況は、トランス女性自身が「ニューハーフ」というフィクショナルな像を引き受けるなかで補強されていく。社会的な処遇による悩みは、美の自己実現という要素など自分で背負うしかないものとして溶けていって、「当事者」個人の中に閉じられていく。そうしないと生活する仕事の場を失う懸念。
テレビやメディアが切り取る「オネエ」や「オカマ」像も、AVやエロ本のポルノ像も、トランス女性ひとりひとりの実像なんかじゃないと、一方的なイメージの期待を拒絶したくなる。
杉田氏の発した「生産性」やそれに続くトランス女性差別を前に、性別移行(トランス)ということと、生殖と労働の重なる身体や生活をめぐって、トランス女性たちの居場所に思いを馳せる言葉は一般的にはまだほとんど見当たらない。「LGBT」はレズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダーの頭文字を取り、シス・ヘテロが支配的な社会で、パイの少ないなか権利獲得の闘争のための連帯として打ち出された。しかし日本では「性的マイノリティ」の代名詞と化し、いっしょくたにされやすい。そこでは、マイノリティ内のマイノリティはさらに言葉を発する機会を失っていく。少なくないトランス女性たちが、経済的な不安定さから声をあげる気力すら湧かなかったり、そのための知識や知恵を獲る機会に乏しい可能性は想定されにくい。
インスタグラムで友人知人のトランス女性たちが見せる、お酒を飲んで楽しそうな顔や、同じような仲間たちとプールに行ったりする様子は、きらきらしている。ネガティブな側面に目がいってしまうわたしが考え過ぎなのではないかとも思えてくる。こうして言葉にするとこぼれ落ちていくものがあるはずだし、説明するために得た知識で強張った身体にはさらに徒労感が溜まる。
鈴木みのり
1982年高知県生まれ。ライター。ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズムへの視点から書評、映画評などを執筆。「i-DJapan」「エトセトラ」「週刊金曜日」「週刊プレイボーイ」「すばる」「東洋経済オンライン」「ユリイカ」などに寄稿。2012年、タイでの性別適合手術(SRS)を収めたドキュメンタリー「THIS IS MY LIFE~心の声が聞こえますか?」に出演、番組が第50回ギャラクシー賞奨励賞を受賞する。利賀演劇人コンクール2016年奨励賞受賞作品に主演、衣装を担当する。
Twitter:@chang_minori
株式会社新潮社「新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shincho/
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
「水着」「入浴シーン」もふんだん 戦前の駅スタンプでもセクシー系への人気は高かった?
[ニュース](収集・コレクション/鉄道)
2023/11/17 -
「各国のヤバすぎるコロナ対応」世界のニュースを解説した一冊に注目[新書ベストセラー]
[ニュース](インターネット・eビジネス/法律/心理学/ジャーナリズム/マスメディア)
2020/12/26 -
「おっさんずラブ」公式ブック ベストセラーランキング2位に躍進
[ニュース](自伝・伝記/テレビ/野球/エッセー・随筆)
2018/08/18 -
気が付くと女子大生の前には男性の死体が…サバイバルパニックホラー 都留泰作『ういちの島』試し読み
[試し読み](コミック)
2024/04/15 -
百田尚樹「アホちゃうか!」立憲・自民議員をともにぶった切るも「政治家がアホだということは……」[新書ベストセラー]
[ニュース](医学一般/情報学/思想・社会/エッセー・随筆)
2021/10/02