家族は有機体で、その形は状況に応じて変わっていく。時には家族を捨てなければならないときもある。 窪美澄氏インタビュー
インタビュー
『ははのれんあい』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
家族は有機体で、その形は状況に応じて変わっていく。時には家族を捨てなければならないときもある。 窪美澄氏インタビュー
[文] カドブン
窪美澄さんは、ままならない人生に翻弄されながらも乗り越えて生きていこうとする人たちの物語を紡ぐストーリーテラーです。読者はその作品を通して、“今、どれだけ行き詰まっているとしても、人生の扉は自分の手で開けることができる”ことに気付かされてきました。これまでは「性」と「生」の両方から物語を描くことが多かった窪さんですが、新作の長編小説『ははのれんあい』では、女性の自立と家族の再生を軸に、正面から“生”を描きます。
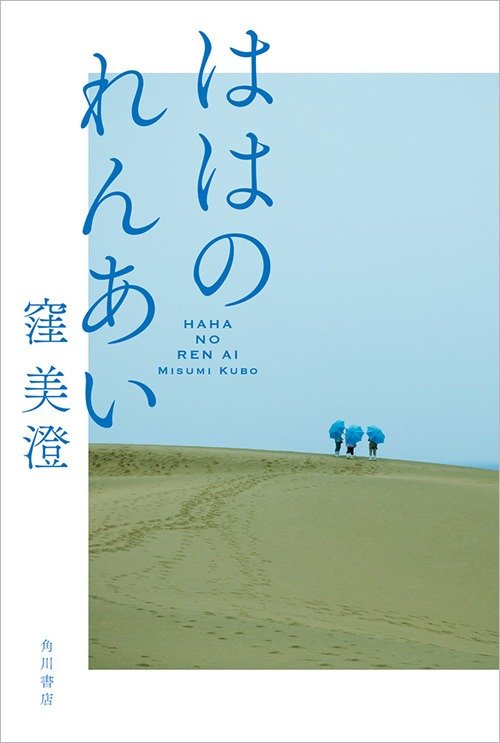
窪美澄『ははのれんあい』 ※画像タップでKADOKAWAオフィシャルペー…
――長編小説『ははのれんあい』が刊行されました。高校卒業後、デパートで働いていた由紀子は、誘われて行った飲み会で2歳年上の智久と出会って結婚します。智久は優しい人で、両親が経営する縫製工場で働いていました。由紀子は自ら進んで縫製工場の仕事を手伝い、やがて長男の智晴も生まれて幸せな日々を送っていたのですが、双子の次男・三男が生まれた辺りから、少しずつ歪みが生じていきます。縫製工場の閉鎖、義母の死、智久の婚外恋愛、そして離婚……。壊れかけた家族を救うのが、幼い頃から母の奮闘と苦労を横で見ていた智晴でした。智晴は母と弟たちを懸命に支えながら生きていきますが、そんな智晴にも人には言えない葛藤があり……。派手な見せ場はないのに物語の世界にぐいぐいと引き込まれていき、最後の1行を読み終えるまで何度も心を揺さぶられました。まずは、この豊饒な作品を執筆するに至った経緯から教えてください。
窪:『ははのれんあい』は、2018年7月から2019年9月の期間に「信濃毎日新聞」「高知新聞」「秋田魁新報」「神戸新聞」などに連載された小説を加筆修正し単行本化しました。新聞連載の依頼をいただいたときに、「家族をテーマに書いてほしい」と言われていましたので、家族の物語にすることは最初から決まっていたんです。
執筆する上で意識したのは、掲載が朝刊という点でした。基本的に朝刊は朝の早い時間に読むものですので、私が日頃書きがちなトゲトゲしたものではなく、少し穏やかな小説にしたいと考えました。朝に読まれるということを考慮し、性描写も自主規制しました。ダメだとは言われなかったのですが(笑)。また、新聞の場合、読者層も幅広く、本をよくお読みになる方もいれば、逆にお読みにならない方もいらっしゃいます。私としては全ての方に届けたいと考えていましたので、平易な言葉を使うことも意識しました。
――家族についてはこれまでも多々書いておられますが、今回は家族の一代記です。
窪:家族というテーマをいただいたとき、すぐに「一代記を書きたい」と思いました。というのも、最初から若い人も読んでくれる小説にしたいという思いがあったからです。
よく若い人から“両親が離婚していることをコンプレックスに思っている”ということを聞くんですね。これって「親がいて子ども2人がいて……」というのが一般的な家族だと思っているからだと思うんですけれど、私はそれはちょっと違うのではないかと思っています。
そもそも家族とは有機体で、一つの決まった形があるわけではありません。家族のメンバーが増えたり欠けたりすることは当たり前のことで、定型がないのが家族です。両親が揃っていようがいまいが、子どもがいようがいまいが、家族なんです。そういうことを伝えたいと思い、一代記にして家族の変遷を書くことにしました。
窪:今回の物語は北関東が舞台です。主人公の由紀子も、夫の智久も、義父母も皆、穏やかで根のいい人ばかりです。他人を蹴落とそうとか馬鹿にしたりすることもありません。長男の智晴もとてもいい息子ですし、次男の寛人、三男の結人もごく一般的な少年です。つまり、登場人物全員がどこにでもいそうな、身近な存在でした。そのことが物語にリアリティを与え、読み手の内側でイメージが膨らむのを後押ししてくれたように感じています。こういった人物像はどのようにして生まれたのでしょうか。
窪:新聞連載をするとき、物語の舞台をどこにするのか決めないといけないのですが、何も浮かばなくて困りまして、藁をもつかむ気持ちでKADOKAWAの担当編集者に相談しました。
彼は群馬県のご出身でした。実際に現地に行ってみると、冬枯れの寒い北関東のイメージがさあーっと広がっていったんです。作中で、田んぼがずっと続いていて、鬱屈がたまったら自転車で走りながら「わーっ」と言いたくなるようなところも、遊ぶところがモールしかないというところも、全部取材の通りです。ご実家の近くに団地や工場があるのも、そこに外国籍の子どもたちがたくさんいるのもそう。蓮の池のある公園も、取材させていただいたままです。
ちなみに担当者は智晴と同じ3人兄弟の長男で、弟さんたちは双子なんです(笑)。智晴のモデルではありませんが、双子を育てるときの大変さについてお母様に教えていただきました。それにお父様は縫製工場を経営されていて、その後タクシーのドライバーさんになられたそうです。こういった背景は智久を形作っていく上で拝借しました。言うまでもありませんが、お父様は不倫や浮気はされていません。そこは100%フィクションです(笑)。

窪美澄さん
――そういった綿密な取材をもとに、由紀子と智久の2人が誕生していったんですね。
窪:最初から女性の自立を主軸に置こうと決めていましたので、由紀子のイメージはありました。20年9月に『私は女になりたい』という長編小説を出しました。こちらの小説はカメラマンだった夫と別れ、シングルマザーとして一人息子を育て、高齢の母親の介護もしている47歳の美容皮膚科医が1人の女性として恋愛をするという物語でした。主人公の女性がいわゆる勝ち組なんですね。
一方、由紀子は、ただただ智久のことが好きで結婚したという女性です。子どもが生まれたことで母親としての意識が芽生え、徐々に目が開いていくというのは女性の話としては“あるある”かもしれません。違いがあるとすれば、智久の違う面が見えたり家族関係が自分の考えていたものとは違っていたと気づいたりしたときに考えることや取る言動、あるいは夫が外で恋愛していたことに気づき、自分1人で子どもたちを育てていくしかないと覚悟を決める――そういう点かもしれません。
智久にもモデルはいません。智久は不甲斐ない男ですが、私が男性を書くと、どうしても不甲斐ない男になりがちなんです(笑)。自分の父が不甲斐なく、男性の原型が父にあるからかもしれません。元夫も不甲斐ない男でした。私の人生は不甲斐ない男を抜きには語れないのかもしれませんね(笑)。勝ち組の女性も非の打ち所がない男も、「今回はそういう人を書くぞ」と意識しないと書けないと思います。
――由紀子は駅の売店でパートからスタートして、やがてキャリアウーマンになっていくわけですが、彼女のこういったキャリア形成も説得力がありました。
窪:駅の売店の話は、私の母の経験です。今年80歳になる母は、父と離婚したあと、駅の売店で定年まで働き、マンションも自分で購入しました。今回、母にも取材をし、駅の売店の中がどれくらい狭いか、お金はどういうふうに渡しているかなどを聞きました。見習いの由紀子が、家で暗算の練習をするシーンがありますが、これも母からそういうふうに頑張っている人がいたと聞いたことを参考にしています。
――子どもたちの設定はいかがですか。智晴にも葛藤や屈折はありますが、それでも素直で優しくて、いい子過ぎるくらいです(笑)。双子にしたのは、担当編集者の弟さんたちが双子だったからだけではないように思えます。
窪:はい、最初から双子にしようと考えていました。由紀子の離婚や自立に伴い、家族の形が変わっていくことを念頭に置いていましたので、智晴には母親のことを大変だ、自分が母親の代わりをしないとお母さんがどうにかなってしまうかもしれない、と思ってほしいと考えていました。そうすると、双子って強力な要素だなあと思って(笑)。弟1人くらいなら、智晴自身が子どもでも助けられそうな気がなんとなくした、ということもあります。
それから、子どもの設定を娘にしなかったのは、娘なら母が恋愛することに対して、もうちょっとどろっとした感情を持つのではないかと考えたからです。自分のお母さんが恋をしているかもしれないと思ったら、息子とは比較にならないくらい複雑な思いを抱くのではないでしょうか? それに、女の子のことを書くときはどうしても自分自身と重なります。ですが、自分を客観視するのは難しいんです(笑)。自分のこととなると、どうしても感情が少しねじ曲がってしまうと言いますか、複雑になる気がしました。それで男の3兄弟にしたんです。自分が実際に育てたのも息子でしたし、男の子は書いていて楽しいというのもあります。
――「ははのれんあい」というタイトルですが、母・由紀子はなかなか恋愛をしません。むしろ、父・智久の恋愛とその結果がもたらす家族の変化が物語を推進させていきます。
窪:意図はしていなかったのですが、私は雛鳥だった由紀子が羽ばたき、やがて自立する姿を書きたかったんです。恋愛が先にあるわけではありませんでしたから、母の”恋愛“にだけフィーチャーされないように、由紀子が恋愛に至るまでの過程を詳細に書こうと考えました。
それから、この物語では智晴が母親の役割をするということも描きたいと思っていました。ですので、智久が本気の恋愛をして由紀子たち家族を捨て、新しい家族を作るというのは必要な流れでした。智久のことをひどい夫でありひどい父親だと考える人もいるかもしれません。智久と恋愛をした、タイ人のカンヤラットが悪いと読む人もいるかもしれません。でも、智久は最初から浮気をしようと思っていたわけでもなければ、由紀子を裏切って傷つけようとしていたわけでもない。カンヤラットも由紀子から智久を無理やり奪おうと狙っていたわけでもない。由紀子が智久を邪険にしたり追い詰めたりしたわけでもありません。ひょんなことから出会った智久とカンヤラットが恋に落ちてしまい、由紀子と智久の関係が変わり、結果として家族の形態が変わってしまっただけです。家族の形は、そういった様々な状況が重なりあって変わっていき、それに伴い、家族の役割も変わっていきます。そういったこと全てを書きたくて一代記を書くことにしたんです。

家族は有機体で、その形は状況に応じて変わっていく。時には家族を捨てなければ…
――新型コロナウイルス感染症の蔓延で、パートやアルバイトなど非正規雇用の方々が失職し、学生の新規採用も激減しました。政府の公共広告でもやっていますが、虐待をはじめとする暴力も増えました。親が子に振るう暴力もあれば、子が親に振るう暴力も目立ちます。社会不安が一気に高まり、今、家族という存在が改めて問われている気がしています。
窪:世界の価値観が大きく変わり、みなさん同様、私もとてもしんどい1年を送りました。抑圧の続いた2020年でしたが、一体これはなんだったんだろうと思っています。
そういう状況下でストレスが蓄積されていくと、暴力でしか表現できないことも出てくるのかもしれません。ですが、暴力の背景を辿っていくと、やりたいことがやれていないなど何らかの原因があると思うのです。心を紐解き、自分を凝視してみたら、何か見えてくるかもしれません。
もし、親など他者から暴力を受けているのであれば、勇気を出してその関係を断ち切ることが必要です。この小説と入れ違いに週刊誌で連載していた小説は、トラウマを抱えている人がまさに親を捨てる物語です。私は、自分の身を守るためには親を切り捨てることも必要だと思っていて、そのことで自分を責める必要は全くないと言いたいですね。
何度も言いますが、家族は有機体で、命があります。その形は状況に応じてどんどん変わっていくもので、変わることは決して失点ではありません。
――先ほど、いろいろな家族の形があっていいとおっしゃっていましたが、窪さんにとっての家族は、今はどういう形をしていますか?
窪:今の家族、ですか……私は今、1人なんです。だから、今の家族と言ったら私だけですね(笑)。今回の小説も、自分がいったん1人になって、自分の人生を俯瞰してみることができたから書けたと思っています。
再婚して、その夫と母は暮らしていますし、私にも息子はいますが、息子には早く家から出て自立してほしいと思っていました。そうしないと、うちは私と息子の仲がいいので、うっかりすると私自身が彼のことを縛って食い潰してしまい、自立を阻んでしまうかもしれない。そんな危機感は常に持ち続けていました。
家族には始まりもあれば終わりもあります。両親が永遠に側にいるわけではありませんし、我が子がいつまでも自分の側にいるわけでもありません。子どもが増えることは怖いことでもあり、それで夫婦の関係が変わるということもよく起こることです。目の前の家族の状況はどんどん変わっていくもの。そして、それが恐怖でもあり、喜びでもあるんです。
――ラストでは窪さんが考える家族像と、それを全身で肯定して一歩踏み出すことを決意する智晴の姿が描かれます。温かみと情味のある、幸福なエンディングでした。
窪:ありがとうございます。世間から見たら歪なものであっても、どんな形をしていても、家族としてどれも間違っていないということが伝わるなら、書き手としてこれほど嬉しいことはありません。
▼窪美澄『ははのれんあい』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321612000240/



































