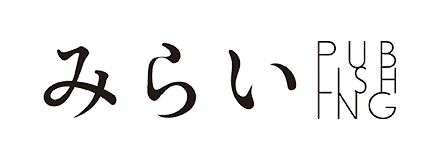写真家・青山裕企さん(撮影:Dhani Caro)
「何がしたいのか突き詰めていくと、写真をやめたほうがいい人がほとんどなんですよ」
そう話すのは、吉高由里子・指原莉乃・オリエンタルラジオなど時代を象徴する人物の撮影や「ソラリーマン」「スクールガール・コンプレックス」「少女礼讃」の作品シリーズで知られる写真家の青山裕企さん。
24歳で写真家になると決めてから20年。これまで一貫して“人”を撮り続けてきました。
「写真はだれでも簡単にはじめられて、すぐ上達する。そのぶん、やめるのも簡単です」と青山さん。
「でも僕は、写真以外の道がない。ある意味、他を全部捨てたんです」
一体、何が青山裕企に写真を選ばせているのか。
写真にできること、写真でしかできないことは何なのか。
独立して17年目になる写真家・青山裕企さんの創作の根源に迫ります。
■カメラを持つまで、人前で言葉が出なくなるほど人見知りでした
――青山さんのお仕事や作品はすべて“人”を撮っていますね。人を撮るようになったきっかけや理由などあれば教えてください。
人を撮るというのは、写真を撮りはじめた20歳のときから決めていました。僕にとって写真を撮る喜びは、=人を喜ばせる・楽しませる、なんですよね。
僕はもともと人見知りなのですが、人見知りって人が嫌いなわけではないんですよ。
人を見知るということは、相手が気になるからなんですよね。変に思われてないか、嫌われてないかって。むしろ人に興味がない人は見知らないんです。
僕は、カメラを持つまでは、人との向き合い方が分からなくて、人を前にすると言葉が出なくなってしまうような人間でした。
そして、それは人に興味があるから、人が好きだからなのだと、カメラを持ちはじめてから気づきました。
カメラを構えれば、喋らなくていいし没頭できるし、カメラ越しに相手を見ることもできる。
そして自分の写真で人に喜んでもらえる。こんな嬉しいことはないじゃん、ってどんどん写真にのめり込んでいきました。それがずっと今まで続いている感じです。
――写真を撮りはじめてから今まで、嫌になってもうやめたいと思うような瞬間はありましたか?
好きなことを仕事にすると嫌いになってしまう、とよく言いますよね。だから、将来を決めるときに、写真を仕事にしてしまっていいのかは、かなり悩みました。
でも、24歳のときに写真家になると決めてからは、嫌になってやめたいと思ったことは一切ないんですよね。本当はあったほうがネタになると思うのですが。
疲れたり、軽いスランプはありましたが、それ以上の負の感情に落ちることはないです。写真でやっていくしかないという覚悟が異常に据わっているのかもしれません。ある意味、他を全部捨てたということなんですけど。
写真以外の道がない。だからやめるという発想にならない。そういう感じですね。

働くサラリーマンが跳ぶ瞬間を捉えた「ソラリーマン」
■「いいね」の数は「どうでもいいね」の数かもしれない
――青山さんが特別審査員を務めるコンテスト(第5回写真出版賞)の審査で「今回は突き抜けた写真が少なかった」と仰っていましたが、青山さんにとって突き抜けた写真というのはどんな写真なのでしょう。
突き抜けた作品というのは、その人にしか撮れないもの、そこでしか撮れないものだと見る人に感じさせる作品のことです。
たとえばポートレートなら、その人の美しさや可愛さなど表面的なものだけでなく、もっと深くパーソナリティまで捉えようとすること。
その人を撮る必然性が感じられないと、ただの自己満足になってしまうんです。
可愛い子を撮れば、それだけで80点ぐらいの写真になります。夕焼けや空、海辺を撮れば、いい写真にはなるでしょう。でも、上を目指すのであれば、そこで100点を目指そうとしてほしいですね。
SNSでは、表現が浅くても、見映えのいい写真であれば、流行ったり「いいね」が沢山ついたりするんですよ。でも、あまり「いいね」の数に囚われすぎないほうがいいと思います。
僕は「いいね」の数は「どうでもいいね」の数かもしれないと思っているんです。もし「いいね」ボタンを押すのに、お金を支払うのであれば、きっとほとんどの人が押さなくなりますよね。ノーリスクだから押すんです。
人が本を所有しなくなった今の時代に、それでも写真集をつくりたいと思うならば、被写体だけではなく、背景や光も、プリントも、すべてにおいて美しさを追求してほしいですね。
■「撮りたい気持ち」と「撮られたい気持ち」が釣り合っているかは、すごく大事
――その人にしか撮れないもの、そこでしか撮れないもの。それは、青山さんの作品シリーズ「少女礼讃」でも強く感じました。これはこの2人の関係でしか撮れないものかなと。
ありがとうございます。この作品は、3年前にこの少女と出会ったことからはじまりました。
コロナ禍になる前までは毎週のように会って撮っていて、それらをまとめた写真集は512ページという狂気的なボリュームになりました。
でも、この作品は、僕の実力というよりも少女の人間的な魅力によるところが大きいんですよね。
カメラを向けると、普通はみんな構えるじゃないですか。いい角度で、とか、笑うと歯が出るからいやだ、とか。そういうフィルターがこの少女にはないんですよ。いつでもご自由にお撮りくださいという感じで、決め顔がない。

「少女礼讃」より
――コロコロと表情が変わるから、見ていて飽きないですよね。吸いつくような中毒性があって…。でも、彼女もきっと心を許していない人にはこんな表情を見せないと思うので、青山さんだから、というのも大きいのだと思います。
それはあるかもしれませんね。この少女も、僕が撮りたいと思うのと同じくらい、僕に撮られたいと思ってくれていると思うんですよ。
モデルさんとの相性を考えるときに、「撮りたい気持ちと撮られたい気持ちが釣り合っているか」はすごく大事なポイントかもしれません。「撮りたい」が相手の「撮られたい」より強すぎると、作品のなかに我が強く出てしまいます。
僕とこの少女は、「撮りたい」と「撮られたい」が高いところで拮抗している感じがあります。そして、そのバランスがずっと崩れていないから、こうして作品が成立しているのだと思います。
――人物というより空気を撮っているのかな、と思うほど、その場の雰囲気がそのまま写っていますよね。撮影の日は、時間を決めてどんどん撮るのですか? それともゆっくり少しずつ撮りますか?
撮影のときは、なるべく長い時間一緒にいるようにしています。だから、写真を撮っていない、「ただ一緒にいるだけの時間」もけっこうあります。
少女も、ここを撮ってとは絶対言いません。だから、感覚的にここだ、というところでシャッターを切っています。
――青山さんにとってのこの少女のような存在は、探せばだれにでもいるのでしょうか?
僕のように突然の出会いということもあれば、身近な人のなかにも相性のいい人がいるかもしれないですね。
何時間しゃべってもおしゃべりが途切れないとか、会話がなくても沈黙が心地いい人っているじゃないですか。写真も、そういうのと近いかもしれません。
だれにでもその人にしか撮れない人がいるので、そういう人を撮ってほしいと思います。
■写真を通して自分の趣向をむき出しにする。撮りたいものを撮るために。
――「少女礼讃」をはじめ「スクールガール・コンプレックス」などを見て思うのですが、青山さんは、写真を通して自分の趣向がむき出しになってしまうことに、恥ずかしさを感じたりしないのですか。
撮りはじめたころはありました。最初の写真展は、恥ずかしくて会場にいられませんでした。
でも、今は恥ずかしくありません。むしろ、意識的にむき出しにしているところがあります。逆に見る人のほうが恥ずかしくなるくらい。
自分の気持ちには嘘をつきたくないんです。素直に撮りたいものを撮りたい。
社会的、倫理的に問題があることをしているわけではないですし、さらけだしたところで自分に害はありません。恥ずかしい奴と思われてもいいんです。写真がすべてですから。
――ご自身のイメージはあまり気にしないのですね。なかなかそういう強い心を持つのは難しそうですが…。
「写真家」と「写真」どっちが大事? と聞かれたら、僕は「写真」と答えます。
多くの人は、自己愛があるので「写真家」が勝つと思うんです。でも僕は、写真が好きな自分を見せたいわけではなく、何も気にせず好きなように写真が撮りたいだけなんです。
そういう意味では「写真至上主義」と言えるかもしれません。自分がどうなろうが写真が良ければいい、という。

思春期の頃の満たされない思いを作品にした「スクールガール・コンプレックス」
■目標は、著書100冊。渇望感を忘れずもがき続けること。
――今年で写真家として独立して17年目になるそうですね。今後の目標があれば教えてください。
そうですね…。写真集の出版は、2009年の『ソラリーマン』から数えて、最近出た「スクールガール・コンプレックス」のベスト版で92冊目になりました。だから、分かりやすい目標は「著書100冊」ですね。完全に自己満足ですが。
あとは、ギャラリーを運営するという夢も頑張って叶えているし、他に分かりやすい目標というのはないんですよね。
――ここまで順調に叶えてきているんですね。
ただ、ある程度の慣れや実績があると、向上心や情熱がさーっと引いてしまうものだと思うんです。そうなったら、終わりですよね。
とくに自分の場合は写真にすべてを捧げてきたので、そこが空虚になったら辛いでしょうね。想像すると怖いです。
こういうことを考えずにいられたのは30代までですね。40を越えてから意識するようになりました。若い人を見ていると、悩んだりもがいたりできるのが羨ましいです。
もがき続けたいですね。写真を撮りたくてたまらない! という渇望感を忘れたくないと思います。それが日々の目標かもしれません。
■新章「ソラリーマン」。心の奥底から狂えるようなテーマを模索中。
――こんな作品をつくりたい! という創作の目標はありますか?
今、いちばん最初の作品「ソラリーマン」を進化させたいと思っています。
これはもともと、自分の父親の死をきっかけにサラリーマンという存在に興味を持ったことからはじまりました。
2015年に「むすめと! ソラリーマン」というシリーズをやって大きな反響があったので、そんな感じでまた、あっと驚くようなソラリーマンをお見せできたらと思っています。
――すでにイメージはあるのですか?
いえ、それが、まったくないんですよ。暗中模索という感じです。
でも、この段階がめちゃくちゃおもしろいんですよね。
このシリーズを撮りはじめたときは20代でしたが、今は自分もサラリーマンのおじさんたちと同世代になりました。
「お父さん世代を撮る」が「俺らの世代を撮る」という感覚に変わってきたんです。そういう心情の変化も次のシリーズに現れてくるかもしれません。
「むすめと! ソラリーマン」のときは、家族全員とか息子さんと一緒にとか色々試しているなかで娘さんと撮ってみたら「キター!」という感じだったんですよ。今回も、そういうテーマを見つけたいですね。
頭で納得するだけじゃ、心底ピンとこないとダメなんですよ。心の奥底、中心に打たれるくらいのものじゃないと、狂えないんです。
――たしかに、自分は騙しきれないですもんね。
そうですね。狂わないと、全国を飛び回って大勢のサラリーマンを跳ばせるなんてできませんからね。
テーマがいつ見つかるのかは、本当に分からないです。すぐ見つかるのか5年後なのか…こればかりは予測できないですね。
今回は、まずは自分が跳ぶところからはじめようと思っているんです。スーツを着て、まずは本気で跳んでみようかなと。

後日、本当に跳んでいました
■世界中の人を泣かせたいと思うなら、写真はやめたほうがいい
――ここ数年で、世界はまた大きな転換期を迎えましたね。今の時代に求められる写真は、どんな写真なのでしょう。
「ソラリーマン」は、わりと辛い時代に話題になることが多いんですよね。
コロナ禍でシリアスな時代が続いていますが、今みんなが見たいのは、きっと悲しい写真ではなく明るい写真なのではないでしょうか。
笑っちゃうもの、面白いもの、かわいいもの、美しいもの、気持ちがポジティブになるようなもの…。
写真は、悲しい時代を悲しく切り取ることもできますが、表現はもっと可能性があって自由だと思います。
自分の内側を見つめて好きなものを撮るのもいいですが、その時に、少しでも見る人のことを考えて、人を楽しませるというエンターテインメントの精神も持つことができたらいいですね。
「人を楽しませる=自分も楽しい」になれば、最高ですよね。基本的に、写真は楽しいものなので。
――最後の質問になりますが、青山さんが周りの写真家を志す人たちにいつも共通して伝えていることがあれば教えてください。
周りの若い人たちには、「どう考えても僕は抜けないよ」って冗談で言っています。
その理由は、単純に僕のほうが写真を撮っている時間が長いから。それだけです。
写真って、だれでも撮れてすぐ上手くなるんです。こんなにハードルが低い表現は他にないと思います。
でも、簡単にはじめられるということは、簡単にやめられるということ。芽が出る前にやめてしまう人は沢山います。
僕は、「辛くなったらやめたら?」とも言っています。世界中の人を泣かせたいと思うなら、写真をやめて映画をつくったほうがいいんですよ。写真は映像や小説のように感情を導けないので。
何がしたいか、それに写真は適しているのか、突き詰めていくと、写真をやめたほうがいい人がほとんどなんですよ、実は。そして、世の中には写真より魅力的な表現もたくさんあります。
それでもやめられない人だけが写真の世界に残っているんです。僕みたいに。
生き残るには、やめないこと。それだけですね。
――今日は一生もののお話が聞けました。本当にどうもありがとうございました。
■〈ミニコラム〉
「ただなんとなく撮る」を脱出して「テーマのある写真」を撮るには?
僕は“目のクセ”と呼んでいるのですが、だれにでも写真の癖というのがあるんですね。なんとなく無意識のうちに沢山撮っているもの。それが自分の好きなものなんです。
データフォルダの今まで撮った写真を見返してみると、自分の好きなものが分かります。空を撮りがちだな、とか、緑っぽい色が多いな、とか。そういう自分の傾向を意識して写真を撮ると、「ただ撮る」ことから脱出できるんですよ。
でも、この話を色々なところでしていますが、みんなあまり実践していない気がします。今まで撮ったものは財産なのに、みんなスルーしがち。それは、もったいないなと思います。
株式会社みらいパブリッシングのご案内
みらいパブリッシングは、本で未来を創る出版社です。ウェブマガジン「みらいチャンネル」では、作家やクリエイターへのインタビュー、詩や写真の連載を日々更新中。ぜひ覗いてみてください。
https://miraipub.jp/mirai-channel/
関連ニュース
-
『戦メリ』を超える曲はもう目指さない ガン闘病中の坂本龍一の心境
[ニュース/特集/特集・インタビュー](家庭医学・健康)
2022/06/08 -
「手で尻を拭く」「料理をシェアしない」同じアジアでも全然違う衛生観念
[特集/特集・インタビュー](歴史・地理・旅行記)
2020/11/27 -
南極の氷を掘ったら何がわかるのか? 国立極地研究所の現役研究者と元地球惑星科学専攻の小説家が語るサイエンスの世界
[特集/特集・インタビュー](日本の小説・詩集)
2020/12/24 -
「せんせえ、遅くなってしまったけど……」作家・吉川トリコが山本文緒さんに伝えられなかった言葉【山本文緒さん追悼】
[特集/エッセイ・コラム/特集・インタビュー](日本の小説・詩集/エッセー・随筆)
2022/11/20 -
現役警察官がオススメする「本当に面白い警察小説」とは
[特集/特集・インタビュー](歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2021/11/23