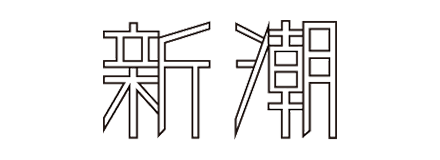黒人初の「ルイ・ヴィトン」ディレクター ヴァージル・アブロー 黒人社会からは批判された“セレブ”である彼が白人社会に仕込んだ「トロイの木馬」とは
特集・インタビュー
 Photo by Mike Vitelli/BFA/REX/Shutterstock (10020470a)Virgil Abloh Spg x Amex Miami Art Week Party, Miami, Florida, USA – 08 Dec 2018
Photo by Mike Vitelli/BFA/REX/Shutterstock (10020470a)Virgil Abloh Spg x Amex Miami Art Week Party, Miami, Florida, USA – 08 Dec 2018
2018年に黒人として初めて〈ルイ・ヴィトン〉メンズウェアのアーティスティック・ディレクターに就任したヴァージル・アブローが、2021年11月28日に心臓血管肉腫で急逝した。アーティストのカニエ・ウェストの盟友としても知られ、自身が立ち上げたファッションレーベル〈Off-White オフホワイト〉は日本でも展開しておりご存知方も多いだろう。41歳という若さでこの世を去ったアブローは、ファッションを専門的に学んだ経験はなく、一般的なルートで〈ルイ・ヴィトン〉のディレクターになったわけではない。ストリートの美学や黒人カルチャーをラグジュアリーブランドの世界に持ち込み、ファッション界に革命を起こしながらも黒人社会からは批判を受けやすく、またエスタブリッシュメントである白人たちからも異端視されてきた。
ここに紹介するのは昨年秋、パリを拠点にしたファッション批評誌『Vestoj』に掲載されたヴァージル最後のロングインタビューである。聞き手を務めたのは同誌の創刊者/編集長のアンニャ・アロノウスキー・クロンバーグ。彼女はこれまでにもシカゴ現代美術館で開催されたヴァージルの大規模個展「Figures of Speech」の公式インタビューをはじめ、何度もヴァージルと対話を重ねてきた人物である。そうしたふたりの信頼のうちに語られるのは、ヴァージルが人知れず感じてきた孤独と葛藤、アフリカ系クリエイティブ・コミュニティに残そうとしている遺産(レガシー)についてだった――。
自分流の”トロイの木馬”
ときどき”たった独りだ”と感じることがあります。はぐれ者か村にひとりでやってきた異邦人のような気分になるんです。パリの上流社会にいても、シカゴのサウスサイドにいても。ですが、疑うことは私の原動力にもなっています。これほどモチベーションを高めてくれるものはほかにありません。そう、だからいつも自分を疑っているわけです。私にやり切ることができるのか。確信は足りているだろうか。この壁を乗り越えられるか。はたして”トロイの木馬”作戦(訳註1)はうまくいくだろうか、と。しかし、他人(ひと)から疑われるとなれば話は別です。ちょっと待て、私のほうが一枚上手だぞ、と言わねばなりません。
学生時代には「お前のしゃべりかたって白人みたいだよな」だの「うぶなヴァージルちゃん(ヴァージル・ザ・ヴァージン)」だのとよく言われていました。でもそのたびに私は気の利いた返しをしていたんです。すると立場は逆転しました。彼らが笑われる側になったんです。周りの連中も笑うほどに。
今もやっていることは変わりません。誰かに”ストリートウェア”のデザイナーだと決めつけられれば、次のコレクションで仕立て(テーラリング)を取り入れた服をつくってみせます。彼らは肌の色でもって私の話しかたや振る舞いを決めつける。作品を理解したつもりになっているんですよ。そこで私は彼らの裏をかくわけです。
2020年の夏以前、人種差別に対する蜂起が盛り上がる前までは、白人が権力を握っている場で人種の話題を持ち出すのはタブー視されていました。私自身、自分の作品で人種を前面に押し出すことはしていませんでした。というのも、お山のてっぺんから人種問題を叫んでも、誰も聞く耳を持たないのは明らかだからです。だからこそ私は自分流の”トロイの木馬”を拵えようと思ったわけです。
ただ今は白人も「機は熟した、さあ人種について話そうか」「白人だけど、あなたの話を聞きますよ」というような状況です。そのおかげで、つかの間トロイの木馬から降りて地上で活動できるようになり、それが威嚇的だと捉えられることもなくなりました。私が不満を垂れていると考える人はもういません。彼らは私の訴えを理解しています。ファッション界の黒人クリエイティブはどこにいるのか。役員会のなかに黒人が少ないのはなぜか。黒人の経験(ブラック・エクスペリエンス)とはなにか。黒人にとっての正典(ブラック・カノン)はどんなものなのか。
私と協働している企業はどこも目下、自分たちのビジネスのなかで生じている人種問題を是正しようと動きだしています。私もブランドの顔として、あるいはコラボレーターとして企業と対等に意見交換できるようになりました。「今私たちがすべきことは何でしょうか?」と問いかけることだってできます。新しいシステムが生まれつつあるんです。ブランド側にとっても、私に先導してもらったほうが都合がいいわけですよ。
二年前に「今度のプロジェクトには黒人だけを雇いたい」と提案しても、よってたかって「まあ、落ち着けよ」と止められたでしょう。それが今ではプロモーション効果もあって、反対する人は一人もいません。
ブラック・カルチャーの輪郭
それでも黒人のアーティスト――呼び方はクリエイティブでもデザイナーでもいいですが――であることにまつわる疑念を払拭できたわけではありません。つまり西洋の価値基準(カノン)に対立する、ということです。人種はどこにいっても付いてまわります――見た目のために、名前のために、そしてこの時代のために。それこそが私が体現するものであり、私の実体です。黒人であることを抜きにして私自身も作品も存在しえません。
階層化された白い業界のなかで、私は白人の正典にその名を刻もうとしているんです。ファッションやアートやデザインの世界では、白い西洋の価値基準がもはや分別できないほど当然視されています。普遍的な正典かのように見なされているわけです。私はその発想をひっくり返したいんです。あるいは少なくとも、そうした分野で黒人がいかに存在し、いかにクリエイティブたりうるかという問いを投げかけたい。だから私は白人の同僚と意見交換をしますが、同時に対立してもいるわけです。
ここで疑念が生じます。二重の疑念です。ひとつは私の作品の妥当性に対する周囲からの疑い――「彼は本当のデザイナーじゃない」とかなんとか。もうひとつは、私の自分自身に対する疑いです。自分に役が務まるだろうか。その場にいるたったひとりの黒人でありながら、他の出席者たちに聞く耳をもってもらえるだろうか。制作に必要なリソースをちゃんと与えてもらえるだろうか。そう自問してしまうんです。
私は黒人の正典(ブラック・カノン)にゆっくりと近づいていきました。黒人の正典を頭のなかで定義し、作品で体現しながら慎重に。私たちお気に入りの比喩を使えば、頭のなかにある家具を並べ替えていったわけです。あなたと初めて会ったのはファッション界で少しずつ知られるようになった頃でしたが、私は黒人であることについて話したがろうとしなかったはずです。そうでしたよね。人種のことは避けていたんです。でも今黒人のデザイナーとして後進に残したいと思っているのは、人種について意見する姿勢です。今は日々、組織内の人種問題への取り組みを牽引しています。疑念はいったん脇に置いておくことにしたんです。
こうやってあけすけに話すことがリスキーなのはわかっています。ソーシャルメディアがまた荒れるかもしれませんし、上司や同僚が売上への影響を心配するかもしれない。あるいはブラック・ツイッター〔ツイッター上のアフリカ系アメリカ人コミュニティ〕が、私の発言のあら探しをするかもしれません。人種についてなにひとつ間違ったことを言わずに話すのは、ほんの三分でも不可能なんじゃないかと思うことがあります。白人を怒らせたら終わり、黒人を怒らせたら終わり――。もちろん私にもまだ答えはありません。ほかの人と同じく、答えを探している最中です。ただそれでもはっきりしているのは黒人の正典を定義する一助になりたいということです。ぐるりと線を描いて”これだ”と示したいんです。
黒人の規範(カノン)が普遍化されている白人の規範とどう重なり、どう異なっているかをより明確に理解しないかぎり、黒人のクリエイティブや知識人から”黒人の(ブラック)”という接頭辞は外れないでしょう。同じように黒人が新たな分野に進出したとしても、その活躍を讃える際に”ブラック”が付きつづけるのであれば、人種を乗り越えたことにはならないでしょう。これからも輝かしい黒人精神(ブラック・マインド)は〔白人の美意識とは〕別物として扱われるのでしょうか。もしそうだとすれば、私たちはいつまでも”仲間に入れてもらっている”状態なわけです。黒人の側に権限はないということです。白人の正典の寛大さに甘んじているということです。私たち黒人はブラック・カルチャーの輪郭をはっきりと示し、それを祝福しなければなりません。黒人コミュニティに意識を向け、なにが黒人の正典か見極めなければなりません。まずはそこからです。
ニュアンスこそが強み
そもそもの前提として理解すべきは、芸術の領域で黒人が注目を集めようと思ったら演じなければならないということです。「おい、座ってないで楽しませてみろ!」といった具合に演技を求められるんです。黒い肌が受け入れられるのは、バスケットボール選手や歌手、モデルやエンターテイナーといったカメラの前に立つ人だけです。そのことはよく理解していたので、私も利用しました。バスケットボール選手を演じ、歌手を演じ、エンターテイナーを演じてきました。いわば”顔”になってきたわけです。
でも今は作品のエンタメ要素はすこしずつ減らしています。自分は一歩引いて、作品そのものに語らせたいんです。露骨な表現ではなく、細かなニュアンスをたっぷり孕んだものとして――。私は考えるための余白をつくりたい。思想家になりたいんです。自分のロジックを明らかにし、曖昧さを歓迎したいんです。
ところが2020年の夏、まさにそのことによってソーシャルメディア上の騒動(訳註2)の渦中にあった私は叩かれることになりました。ブラック・コミュニティはこう言い立てました。「ニュアンスなんて要らない」「直接、行動しなよ」「あなたは闘うべきだ」。それでもニュアンスを諦めたくはありません。ニュアンスこそが私の強みなんです。
ブラック・コミュニティからすれば、私はそれほど”黒く”ないわけです。高校の頃からそう言われてきました。初めて偏見を向けられていると感じたのは白人からではありませんでした。「お前は饒舌すぎる。なんで白人みたいにしゃべるんだ」となじる黒人からでした。自分が何をしたかもわからず学食のテーブルで呆然としていたのを覚えています。
両親がアフリカ出身で、移民としてアメリカにやってきたことは前に話しましたよね。父は70年代にガーナからふたつの学位をもって海を渡りました。2020年の夏ブラック・ツイッターから総攻撃を受けたとき、父はそっと私に言いました。「今お前の身に起こっているのは、私がこの国に着いてまもない頃に体験したことだよ」。当時のアメリカの黒人たちは父にこう訊いたそうです。「なぜそんな言葉を使うんだ?」「そんな車に乗るのか?」「なぜ俺たちみたいに振る舞わないんだ?」と。
ブラック・カルチャーから期待されていると感じることもあります。でも彼らが望む物語から外れた途端にゴミ箱行きです。私は使い捨てなんです。皮肉も皮肉ですよね。駆け出しの頃は中傷ばかり言ってくる連中もいましたが、サポートしてくれる人も大勢いました。成功するよう応援してくれていたんです。でも今は……。強者が転げ落ちていく姿を見るのはある種の愉悦ですからね。人間らしいというか、まさに他人の不幸は蜜の味(シャーデンフロイデ)、ですよ。
今度はそれまでとは違う疑念が浮かんできました。駆け出しの頃はまだ危機感も希薄で、そこまで疑い深くありませんでした。危機管理をする必要がなかったんです。それが今では疑いぶかい政治家にならざるをえません。
48時間続いた去年〔2020年〕夏のインターネット上の竜巻は酷いありさまでした。私の結婚式の写真も勝手にアップロードされましたしね。セレブに騒ぎ立てる動物園のような沙汰でした。キャンセルカルチャー(訳註3)に巻き込まれてしまったわけです。
以前から周りの友人知人は、なぜ著名人はもっと積極的に――人種などについて――議論を誘うような発言をしないのかと不思議がっていました。でもキャンセルカルチャーが苛烈化した今ならわかります。誤りを言うのはあまりにも簡単です。そして今はひとたび間違った発言をすれば、公衆の面前で恥をさらされます。だからこそ、何も発言しないセレブたちのなかに埋もれて目立たないようにするのが得策になってしまうわけです。
もちろんこれは、さっきまで話していた疑念とは別のものです。でもこの一件で私は人間の本性を、自分の居場所を疑うようになりました。
聞き手=アンニャ・アロノウスキー・クロンバーグ(Anja AronowskyCronberg)
『Vestoj』創刊者・編集長。セントラル・セント・マーチンズでファインアートの学士号を、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでデザイン史の修士号を取得。2009年にファッション批評誌『Vestoj』を創刊した。
訳者=平岩壮悟(ひらいわ・そうご)
1990年生まれ。フリーランス編集者/ライター。日本翻訳大賞実行委員。2020年までi-D Japanに勤め、その後独立。主な担当書籍に、『角砂糖の日 新装版』(山尾悠子, LIBRAIRIE6)、『ヒロインズ』(ケイト・ザンブレノ、西山敦子訳、C.I.P. Books)、『エレンの日記』(エレン・フライス、林央子訳、アダチプレス)など。
株式会社新潮社「新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shincho/
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
第32回三島賞・山本賞の候補作が発表 岸政彦、金子薫、芦沢央など
[文学賞・賞](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2019/04/22 -
草間彌生の詩と絵画が文芸誌に掲載 タイトルは「愛と死の対決」
[リリース](日本の小説・詩集/絵画)
2017/12/09 -
又吉直樹『火花』に続く待望の第2作は“恋愛小説” 3月7日発売『新潮』4月号に掲載
[ニュース](日本の小説・詩集)
2017/02/13 -
真珠湾攻撃に参加し「日本人最初の捕虜」となった海軍軍人とは? GHQが手記を検閲した文書も初公開
[ニュース](歴史・地理・旅行記)
2023/03/24 -
矢作俊彦の新連載がスタート 二村永爾シリーズの新章
[リリース](日本の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2017/12/07