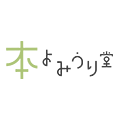『地の底の記憶』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
地の底の記憶 [著]畠山丑雄
[レビュアー] 小山太一(英文学者・翻訳家)
小説には〈あるある〉と〈それもありかも〉という二つの極が存在する。〈あるある〉の極を支配するのはリアリズム、〈それもありかも〉の極を支配するのはファンタジーだ。もっとも、〈あるある〉のリアリズムが成立するためにはフィクショナルな作り込みが必要だし、〈それもありかも〉のファンタジーが成功するためには、奇想に満ちた世界観がリアルな厚みと手触りを持って立ち現われなければならない。
いわば、小説のリアルとファンタスティックは持ちつ持たれつの関係にあって、その「持ちつ」と「持たれつ」を仲介するのが創作という手工業の技術なのだろう。作り物でない小説など存在しないのであって、あらゆる小説に通用する評価基準は、それがどれだけ巧みに作り込まれているかということだ。
畠山丑雄のデビュー作『地の底の記憶』は、明らかに〈それもありかも〉を志向する作品である。ここで披露されているのは、歴史の地層をフィクショナルに掘り起こし、あるはずのないものを取り出してみせるという大技だ。道具立てを列挙するなら、ロシア革命後に日本が行なったシベリア出兵、鉱山と電波塔、太平洋戦争中にボルネオで一兵士が組み立てた鉱石ラジオ、坑道の奥にある地底湖の水底に敷き詰められたラピス・ラズリ、そして心が鉱石でできている「やつら」。
二百数十ページによく詰め込んだと思えるほどの大仕掛けであり、語り口もそれにふさわしく重層的だが、ハッタリ臭さや怪しさはいささかも感じさせない。先に述べた「作り込み」のよき実例だ。その巧みさは大学生のデビュー作とは思えない。
一方で、本作の作り込みが成功しているのは、それが実はひとつのシンプルな譬(たと)え─―「心を奪われる」ということ─―をめぐる精一杯の試みだからこそ、という意地悪な見方もまた可能だろう。今後、この作者がより老獪な大嘘吐きに化けてゆくかどうか、動向に注目したい。