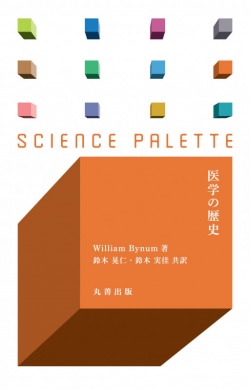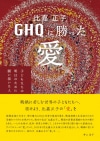『医学の歴史』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
斯界の泰斗が5つの視点から西洋医学の足跡を辿る
[レビュアー] 西田藍(アイドル/ライター)
医学史と言っても、医療技術そのものの発展だけでなく、呪術から科学に至る道、からだとこころの捉え方など人文社会系の要素もたくさん、あらゆる方向に広がっている。そこが面白いところなのだが、何から手をつければいいのかわからないのも事実。長い歴史を把握するのは難しい。そこで筆者は古代から19世紀までの西洋医学の歴史を、五つの類型に分けて整理し、歴史的に発展した順番に紹介。簡潔な記述が入門者に最適だ。
まずは〈臨床の医学〉。ここでは古代ギリシャの医者ヒポクラテスを中心に語る。彼自身の生涯は謎に包まれているが、影響は現代にも及ぶ。ヒポクラテス派は、病気そのものだけではなく患者全体を診る「全体観的(ホリスティック)」な診療を行なった。
「医師」や「薬」は「自然」を意味するギリシャ語に起源を持つ。自然主義的なギリシャの古代医学だが、それが近代に至る医学を形成したのだ。
続いて〈書物の医学〉。書物によって体系的に学ぶ場所である大学の誕生と、ルネサンスが与えた影響、解剖学の発展がメインだ。
そして〈病院の医学〉。18世紀末からパリで起こった「医学革命」が西洋全体に影響を与え、現代では一般的な病院での診療は、このときに定着した。聴診器もこの時代の発明だ。精神病院の発展も興味深い。
〈共同体の医学〉では、公衆衛生運動の誕生に迫る。貧困と病の関係、不潔と病の関係。そして医学の数値化。
〈実験室の医学〉では、やっと科学と医学が密接に結びつく。細菌、ウイルス、小さきものが発見されるのだ。
最後の章は〈現代世界の医学〉である。先述した五つの医学の類型が重なり、現代の重要課題を押さえている。
人類が自らの身体を知り、生命をコントロールしようとする過程はとても複雑でロマンチック。いま我々が持っている当り前の身体観は、自明のものではない。この本で、ぜひ医学史の素敵な世界に足を踏み入れて欲しい。