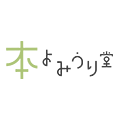『砂浜に坐り込んだ船』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
耳に残るは誰の歌声
[レビュアー] 山本貴光(文筆家・ゲーム作家)
ちょっと想像してみよう。もしこの先、自分の記憶が変わらないとしたらどうだろう。つまり、日々新しい出来事は何一つ起こらず、これまで経験したことだけが思い出される世界だ。なんならそれらの記憶は夢の中のように、見えたり聞こえたりすると考えてみてもいい。そういえば夢もまた、当人の記憶を材料に編まれる織物だ。
例えば、そこでは過去に味わったものだけを食べられる。過去に観た映画だけを観られる。そして、人は過去に交わした言葉を口にし、表情を見せる。同じ物事が繰り返す、いわば永劫回帰の世界である。
経験者は語る。「ここでは驚くということがないらしい。すべてはかつて知っていたこと・思い出すこと・そうだった・こんな風だったと納得することでしかない。新しいものとの出会いはない。自分の記憶にあるものがそれらしい格好で出てくるばかり。ぜんぶ自分の中から出てくるというこのやりきれなさ」
こんなふうに独りごちるのは『砂浜に坐り込んだ船』の一篇「上と下に腕を伸ばして鉛直に連なった猿たち」に登場する人物だ。実をいえば彼はこの世にいない。人が死んだらどうなるかはさておき、なるほど五感を通じて何も入ってこなくなったら、あとはひたすら自問をするわけか。なんだか耐え難いことのようにも思える。
だが、彼は存外楽しそうだ。彼岸へ渡る舟上では辺りを眺め観察し、辿り着いた場所でも状況を静かに考察してなすべきことを淡々と行う。かつて飲んだワインをそれと知りながら味わい、若くして先立っていた姪といつかのように仲睦まじく語りあい、昔見たオペラを見る。姪が笑うのを見て、このために来たということにしておこうかと前を向いている。
そこにはセンチメンタルな湿っぽさはなく、過度の諦念のようなものもない。これに似ている姿勢があるとしたら、古代ローマ、ストア派の賢人だ。自分に制御できることとできないことの違いに自覚的で、無暗に悩んだりすることもなく、さばさばとして清々しくさえある。思うにこれは池澤さんの小説に登場する主人公たちに共通して見られる性質であり、多くの読者を魅了してきた要素でもあるだろう。至るところに死が顔を見せる本書も例外ではない。
さて、以上は死者の場合だった。生きている者はどうだろう。本書には八つの短篇が収められており、そこかしこで生者と死者との対話が描かれている。ある者は既にこの世にいない友人とのおしゃべりに興じ、ある者は墓前で独り話しかけ、またある者は敬愛する作家(物故者)と語る。こういってよければこれは池澤版『死者の書』である。
死者との対話がどうなるかは、生者の脳裡にある記憶次第であろう。もうどこにもいないその人が、どれほど自分の中に入りこんでいるか。生前多くを知らなかった相手であれば対話の手がかりは少ないから一方的に語ることになる。親しい友であれば「あいつならこんなときこう言うよな」と、様々な話題を楽しめるはず。とはいえそれでも知らないことがいくらでもある。たとえ会ったことがなくとも、恋するように愛読した作家が相手ならどうか。その人が書いた言葉の数々に親しんでいるから、身近にいながらあまり言葉を交わしたことのない他の誰かよりも遥かに深く広く、その人を知っていると感じられるかもしれない。
そうか、つまるところ死とは記憶のことなんだ――短絡するようだが腑に落ちた。死者は誰かの記憶のなかで思い出されるたびに甦り、そこにいる。ただし、誰にも想起されなくなったとき、取り返しようもなく消えてしまう。
思えば私たちは、死者のあいだで生きている。太古のこの星に生命と呼べるものが生まれてから現在まで、どれだけの生物が生まれて死んでいったかは分からない。だが、ともかくそうした生物たちが生まれて死ぬまでに行ったこと、その一切合切の積み重ねの上に現在はある。とりわけ人間がつくってきた社会や法律、建造物や各種の道具、知識や創作物、そう、こうして使っている言葉もまた死者たちの産物だ。私たちは死者と共に、少なくともかれらが残したものの中で生きている。それでいながら、かつて地上にいたはずのかれらは、ほとんど記憶されることなく消えてきた。
私たちは、直接であれ間接であれ、なにがしかの縁を結んだ人びとの記憶をおのおのが自分のうちに蓄える。もし私の記憶の少なからぬ部分が、死者たちにまつわるものだとしたら、果たしてどこまでが私なのか。私たちはそれと気づかずに、本書の主人公たちのように、死者と混ざり合い対話をしながら暮らしているのではないか――と、話がいささか抽象に傾いた。『砂浜に坐り込んだ船』は、あくまで具体的な人物の具体的な行動を描く小説だ。だが、時に幻想のような出来事を交え、時に見てきたような嘘を真のように描きながら、小説にこそ可能な魔力を存分に及ぼして、こんなふうに読者を思わぬ場所へと運んでゆく。
この八篇の小説にはもう一つ共通点がある。いずれも移動する話なのだ。ある者は砂浜に坐礁した船を見に車を走らせ、ある者は原発事故で立ち入りを禁じられた故郷に戻る。舟で三途の川を渡る者があるかと思えば、ピザを焼くために島へ向かって舟をこぐ者たちがいる。夢と現のあわいを幾重にも往復する者がいる一方で、空間どころか時間さえも超えてイスファハーンへ向わんと望む者がいる。一人危険な雪道を進んで墓場を訪れる男がいれば、旅する二人の作家は手を携えて空へ飛び立つ。
なぜ移動するのか。巻末にスプリングボードのように置かれた「マウント・ボラダイルへの飛翔」にこうある。「生と移動は一致している。動かないわけにはいかない。それは呼吸しないで生きろというようなものだ」とは死者である作家の言葉。彼の本を愛読するもう一人、生者である作家はそれを受けて言う。「人間が歌って歩かなければ世界は消滅してしまう」と。そういえばホメロスの昔から、歌は人から人へと記憶を伝える助けとなってきた。
なんということか。要するにこれは小説の形をとって、死者の遇し方、記憶の働き、つまりは世界のつくり方を書いた本なのである。だからだろう、一読するごとにこういう思いが募る。さまざまなものが流れ去ってゆくなかで、さて、私はなにを覚えておこうかと。もはや言うまでもないかもしれないけれど、そんな気持ちをそそる小説には、滅多にお目にかかれるものではない。耳に残るは誰の歌声か。