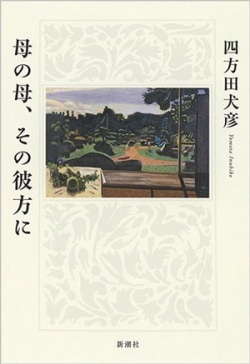『母の母、その彼方に』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
証言者の甘美な不安
[レビュアー] 平松洋子(エッセイスト)
最後まで読み終わったとき、名状しがたい感情が押し寄せ、容易に言葉が見つからなかった。ここに明かされた四方田家の「女たちの秘密」に触れたからだけではない。巻末に措かれた長いエピローグ、そこには著者自身の「秘密」もまた、おずおずと、しかし生々しく綴られていた。本書は「柳子」「美恵」「昌子」の三章から成るが、「犬彦」と名づけられるべき終章が用意されているとは想像もしなかったから、少なからず動揺したのである。ただし、著者はこんな心情を吐露している。
「三代にわたって続いた四方田家の女たちの物語をこうした卑小な挿話でもって締め括ることは、本書の執筆を思い立った時点のわたしには思いもよらぬことであった」
自身のとまどい、喪失感、不可解、解放、慰め……複雑な思いは、「女たちの秘密」の扉を開けてしまった所業への仕置きなのだろうか? 家にまつわる数々の事実は、封印されたままであるべきだったのだろうか? 問いかけても、過去は沈黙のうちにひっそりと沈んだままだ。一族の「秘密」に触れ、家の終焉を見届ける意味。一族の者として今を生きる意味。ふたつが交渉し合い、著者の現在を浮かび上がらせる。
十五年前、イタリア滞在中に送られてきた一通のメールがすべての始まりだった。ある女性史の研究者からの問い合わせ、“「四方田柳子」について知らないだろうか”。未知の名前だったが、人物の住所と自身が幼少時を過ごした土地が一致していたことから興味を抱き、帰国後、母に訊く。すると、驚いたことに、柳子は祖父が最初に結婚した相手だった。長らく隠蔽されてきた柳子の存在に、著者は泉鏡花『婦系図』の世界に迷い込んだような感覚を覚え、そして四方田家の秘密をめぐる旅が始まる。
まず語られる「柳子」。彼女の物語に読者が惹きつけられるのは、その進取の気性に富む生き方の新しさによってである。明治十八年、岡山県津山生まれ。家族の猛反対を押し切って十三歳で東京へ飛び出し、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)の附属高等女学校に入学。さらに学問を志し、日本女子大学校に進学。八年間に亘って平塚らいてうと机を並べ、婦人解放運動との関わりをもつ。ふとした偶然に導かれて京都帝国大学の学生、四方田保と知り合い、強い意志をもって在学中に結婚。ほどなく保は弁護士として頭角を現し、手掛けたシーメンス事件を契機に関西法曹界の重鎮となってゆく……文献資料を渉猟し、ゆかりの土地を訪ね、めぼしい人物から話を聞き出しながら、能う限り綿密に柳子の実像を描きだそうとする著者の視線は、身内の記録にとどまらず、歴史の証言者のそれであろうとする。柳子は五人の子を産み、育て、考案した婦人コートを発表し、婦人解放問題や幼稚園運動などの社会的事業に取り組んだ。児童教育家として、自然のなかで子どもを育てる教育施設「箕面家なき幼稚園」の初代園長を務めるが、乳がんを患い、病の床につく。過労の末、あえなく閉じた四十四年の生涯。その間に二児を失っている。
かくして公にされた四方田家の過去は、いっぽう、日本の女性たちと時代との関わりに光を当てるものだ。つねに背水の陣を背負って生き抜いた柳子の一徹さに、私は、この国の女たちの来し方を思わずにはおられない。立場や環境は大きく違っていても、同じく歴史に埋もれた無数の女たちの存在が、柳子を通じて見えてくる。
そして、第二章「美恵」。柳子が身罷った半年ののち、二十八歳のとき、後妻として二十歳上の保と結婚。わずか一代で財産と社会的地位を築き上げ、新興ブルジョワジーとして栄華を誇る四方田家の女あるじの役割をみごとに引き受け、女中たちを差配しながら箕面の広大な屋敷をマネジメントすることに情熱を注いだ。ところが、美恵自身もまた、いくつもの秘密を持っていた。十九歳のとき結婚した野球選手と離婚、生後まもない長女と死別。柳子の存在は生涯にわたって隠し通した。孫として三十年以上親身に交わったからこそ、著者は、祖母という存在の背景にくすんだ感情の蠢きを察知している。
「現在のわたしにとって彼女とは、〈女たちは秘密をもつ〉という真理を証し立てるさいに、真先に想起すべき原型的存在である」
丹念に繙かれる四方田家の女たちの物語に触れながら、思う。「女たちは秘密をもつ」ことが真理であるならば、それは「家」による要請ではないか、と。外に漏らせぬ大小の秘密を保持するからこそ「家」は成立し、存続することを女たちは知り抜いているのだ。その意味において、「四方田家をめぐるいかなる秘密をも継承したくない」と明言する著者は、「家」にまつわる秘密を公にする資格を有していたことになろう。
三番目に語られる「昌子」の存在には、どこかほっとさせられる。美恵の娘、つまり著者の母はブルジョワジーの子女として使用人に囲まれて育ちながら、労働とは無縁のまま生涯を送る。その恵まれた生活環境のなかで生まれたエピソードの数々には、秘密めいた匂いがもたらされておらず、つまり「家」から解放されて朗らかだ。
日本の「家」にまつわる文学作品は、とかく複雑な様相を呈して語られる。親子、夫婦、きょうだい、舅姑、嫁、婿、さまざまな単位が錯綜することで独特のほの暗さが醸成されることしばしばだが、いっぽう、本書にはその息苦しさがない。それは、あくまでも個として三人の女たちと向き合い、いましも終焉を迎えようとする四方田家を俯瞰する眼の知性のなせるわざだろう。だからこそ、長いエピローグに漂う寄る辺なさが、いっそう読者の胸に響くのである。著者がかつて暮らした深い森のような屋敷に抱く喪失感。無意識のうちに祖母から受け継いだ味覚と嗜好。土地や棲み処への執着のなさ。と同時に、じつは自分が決定的な世界観を継承しているのではないかという恐れ。それらが綯い交ぜになりながら、説明のつかない甘美な不安を著者にもたらしている。あげく、みずから恥の記憶と呼ぶ、くだんの「卑小な挿話」によって一族の歴史が回収されるときのカタルシスに、私は息を飲んだ。
「母の母、その彼方に」、果たして何があるのか。過去は、意味を与えられて生き長らえる。封じられていた秘密に指を触れ、自己との邂逅を果たそうとする著者の姿に感動を禁じ得ない。