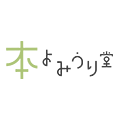『サラバンド・サラバンダ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
不安に満ちた時代のとらえがたい生
[レビュアー] 田中和生
敗戦後の日本で批判されてきた自然主義から私小説へといたる文学史以前に、日本語による近代文学とはどんなものかという共通了解さえとうに失われてしまったかに見える現在、私小説的な書き方であるということに過剰な意味づけをするのは、そろそろ差し控えた方がいいように思える。実際、作者は二〇〇九年から二〇一六年にかけて書いた十の短篇を収めたこの作品集で、しばしば作者自身を連想させる「男」や語り手の「私」を描いているが、その印象は批判されるべき私小説的な書き方をしているという挑戦的なものでも、またもはや存在しているかどうかわからない、私小説の伝統に連なっているという確信に満ちたものでもない。むしろ仕方なくそうしているとでも言った、頼りなげな不安定なものであり、そこにこの作品集の新しさがある。
たとえば私小説的という意味では、二篇目の「草屈(くさかまり)」は作家と思しい中年男性の「私」が、また七篇目の「未遂」は新潟に帰省している自由業らしい「私」が語り手で、読者に新潟出身である作者自身を連想させずにおかない。そうして「草屈」では、山梨の山中にある別荘に生い茂る草をガソリン式の草刈り機で刈っていくことが「私」の女性に対する鬱屈した思いを断ち切るのに重なり、一方「未遂」では新潟で妻子を残したまま失踪した親友の荷物整理をその妻から頼まれた「私」が、親友の妻に性的な魅力を感じながら彼女の死体を遺棄することを妄想する。そんな作者自身と重なる「私」という存在を定位し、過不足なく表現することが目的なら、それらの語り手「私」が前面に出ている作品ばかりでもよかったはずである。
しかし「未遂」ですでに、語り手の「私」より失踪した「若杉」やその妻の存在が強い印象を残すように、おそらく作者が書きつけようとしているのは作者自身と重なる私小説的な「私」などではない。だから五篇目の「燼(もえぐい)」や八篇目の「あなめ」、また九篇目の「禊」といった作品では、作者自身が語り手であるように感じられるが「私」という一人称は極端に抑制され、やむを得ず言及しなければならないときには「自分」という呼称が用いられる。こうして「燼」では、酒を飲んでいる語り手が酒場にあるアルコールランプから京都の青蓮院門跡で見た不動明王の炎を連想し、さらにそれを見た日に京都の酒場でやはり酒を飲みながら女将から聞いた話を回想する。また、作家である語り手が葬儀のあと、その葬儀を手伝った女性と同衾しているらしい「あなめ」では、女性の口を通して葬儀の主役である謡の先生をしていた八〇代の兄と妹の様子が語られ、そして語り手が新潟で入院している友人を見舞う「禊」は、その死につつある友人「洲崎」が導きとなる記憶や感覚が作品の主役である。いわばそれらの作品では、語り手は奇妙で不可思議な話を引き出すための触媒であり、その話の現実とも幻想ともつかない、生と死の境界にあるような感触が深い余韻を残す。
では私小説的な枠組みを消し去り、それらの奇妙で不可思議な話だけが作品で語られてもよいかと言えば、そうでもない。なぜならそんな話題や出来事に遭遇しそうな「私」や語り手がいて、初めてそれらは単なる荒唐無稽な話ではなくなるからである。その意味では私小説的な雰囲気を残しながら、三人称で「男」と記述される中年男性を描いた一篇目の「明滅」や三篇目の「分身」のような作品が注目に値する。たとえば「明滅」では出た覚えのない葬式の出席への香典返しが届くという出来事が起き、また「分身」では高校時代の寄せ書きを見て書いた覚えのない言葉を自分のものとして突きつけられる。それらは新潟出身で作家をしているらしい「男」の特殊な経験であるはずだが、しかし「男」と記述されることによって、それは誰にでも起きうると言って言い過ぎなら、動かしがたい事実であると感じられる、ある種の普遍性を獲得している。その感触は「私」という存在を表現する近代文学のものではなく、近代以前の叙事詩に近い。
作者が二十一世紀に入って書きつけている言葉が、近代以前の日本語と強く結びつこうとしていることは五篇目の「燼」で『徒然草』が引用されたり、六篇目の「錵(にえ)」で語り手が図書館で『葉隠』を読んでいたりすることでも示されている。しかしとくに冒頭に置かれた「明滅」で「男」が白鳥のいる冬の鳥屋野潟を思い出し、末尾にある十篇目の「或る小景、黄昏のパース」で作者自身を思わせる「私」が、主人公が冬の鳥屋野潟を思い出すその「明滅」と思しい短篇小説を書いたと語りながら、作中で新幹線の窓から白鳥を見ていることから連想するなら、この作品集で描かれている「男=私」が立っているのは、おそらく次のような古典の登場人物がいる場面と地つづきの場所である。
《倭建命(やまとたけるのみこと)を迎え、美夜受比売(みやずひめ)が、ご馳走を差し上げた時に、美夜受比売がお杯を捧げて献上した。ところが美夜受比売の着物の羽織の裾に月経の血が着いていた。倭建命はその月経を見て、お歌いになっておっしゃる、
(ひさかたの)天の香具山の空を
鋭く尖った新月の鎌のような姿で 渡る白鳥
その長くのびた首のように弱くか細い たおやかな腕を
かき抱きたいと 我はするけれど
共寝をしたいと 我は思うけれど
あなたが着ておいでの 羽織の裾に
月が出てしまっているとは》
(中村啓信による『古事記』現代語訳より)
表題は「あとがき」にもあるように、クラシック音楽にある舞曲の形式名をフランス語とイタリア語で重ねたものだが、その三拍子である舞曲の雰囲気が作品全体に通じ、またフランス語の「サラバンド」ともイタリア語の「サラバンダ」とも決められない、よろめくような音の響きが作品集の印象をうまく伝えている。不安に満ちた時代の、とらえがたいわれわれの生を注意深く言葉に換え、熟成された酒を味わうような時間をあたえてくれる、贅沢な作品集だ。