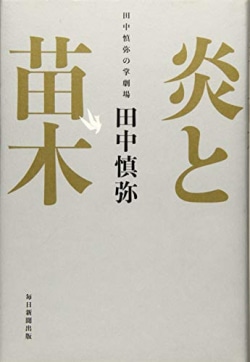『炎と苗木』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
なぜ作家は殺し続けるのか?
[レビュアー] 倉本さおり(書評家、ライター)
「書く」という営為の業。
どんなに慎重な手つきであっても、言葉を選んだとたん、鋳型からはみ出したイメージは無惨にこぼれ落ちてしまう――田中慎弥という作家は、その罪深さに恐ろしく敏感な作家だ。
ここに収められた四十四篇の掌篇の中には、社会的な空気の変化を反映したものも数多く含まれている。たとえば、「国益の作家」と題された作品の中で描かれるのは、国益に反する表現を規制する「出版文化保護法」なるものが可決される顛末だ。他にも「自由の首輪」では、犬の首輪をつけて「忠誠」をアピールすることにより「取材がしやすくなった」と喜ぶ記者の姿が、「正常な春」では、国防軍の戦闘映像を見ることで性欲を増進させる国民の様子がいかにもシニカルかつコミカルに描かれる。
意表を突かれたのは「右傾化」という一篇。そのきな臭いタイトルが示しているのは、やっぱりこの国の〈首相〉のことなのだが、読者の想像する姿とはすこし様相が異なる。というのも、それは単に〈首相の上半身がいつも、向って右に傾いている〉(!)という、なんとも字義通りすぎて脱力させられる事態なのだ。マスコミに「右傾」姿勢を連日あげつらわれ、ついに国会審議の中で野党からの追及を受けることになった首相は、こんな答弁をドヤ顔で繰り広げる。〈皆さんから見て右ということは、私にとっては左に傾いてることになるじゃありませんか!〉――思わず鼻フックをかましてやりたいほどばかげた問答にもかかわらず、その実、本作の核心にあるものをしれっと穿っているから恐ろしい。
くだんの「国益の作家」の中で、こちらの首相は〈我が国が世界のド真ん中で赫奕(かくやく)たる存在となるために〉という言い回しで表現規制を正当化する。それに対し、語り手である〈私〉は、三島由紀夫も用いた「赫奕」という言葉を取り出し、〈かのノーベル賞作家はこの大げさな言葉を、赤々と、という意味しか持たないのに、だとか批判していた筈だ〉と鼻白む。つまりは、「右」寄りに見える首相が「赤い」イメージに頼る――こうした反転や倒錯は、本作のいたるところで指摘できる要素だ。最もわかりやすい例が「赤い女」と題された一篇。この作中の首相は、自らの立場にとって怨敵であるはずの〈赤い女〉に、あろうことか欲情して果ててしまう。また、「別れるまで」に登場するのは、自らの一方的な思い込みの象徴としての〈赤い服〉だ。
私たちが思っている「それ」は、目の前の「それ」と、ほんとうに同じものなのか――すなわち「現実」、あるいは「私」自身の中にある、言葉に対する疑義こそが、この作品の本質だといえるだろう。そして、その間に横たわる計り知れないずれは、むろん「書く」という業――作家という生業にとって、致命的な事態を引き起こす。
「醜い女」の語り手である作家の〈私〉は、新幹線で移動中、前の座席に座る女の美しい後姿に着想を得て短篇を書く。目の前のこの女はきっと美人に違いない、だからこそ小説の中の女は、どこまでもいきいきと醜くあらねば――。ところが、実際の女の顔は、〈私〉が描いたそれよりもずっとずっと醜かったのだ。ショックを受けた〈私〉は懸命に手を入れるが、現実の女の醜さを超えることができず、けっきょくは〈最も安易な方法〉を取る。
〈主人公を、美しい女に変えたのだ。すると苦労しなかった。美しさは醜さよりも罪がなく、単純だった。こうして、いままで描いたことのないほど美しい、ばかのような女が出来上がった〉
象るべき現実の対岸にある幻想の、甘やかで明快でたやすい美しさ。作家の業とは、その誘惑を退けつつも、常に敗北を味わうことを意味するのかもしれない。
〈書き続けるという行為は、死体をいかに真新しいままに維持し続けるかという工夫の過程に他ならなかった〉
「終りと始まり」と題された作品の中にある一文が差し出しているのは、「書く」ことがけっきょく「殺す」ことでしかないという、ぞっとするほどつめたい真実だ。
では、なぜそれでも作家は殺し続けるのか?――おそらくその答えは、「首相の墓」という一篇に集約されている。
かつて国民から慕われた名宰相。にもかかわらず、今ではすっかり忘れ去られ、その豪壮な墓を訪ねる者も皆無に近い。ただ一人だけ、毎年欠かさず墓参りに来る男がいるのだが、まさしくその男こそが墓の主を屠った人物にして、現在の首相なのだ。
〈殺したからこそ誰よりも記憶する。(中略)国民は、前首相を愛していたから、忘れることが出来た。男は愛しても憎んでもいなかった。ただ手応えと血しぶきと叫びだけがあった。だから忘れないのだ〉
感傷や幻想は欺瞞と自己完結を招く。それがどんなに優しく緩慢であっても、忘却とは畢竟、ままならない現実の改変を意味している。その先に待ち受けるものが、本作で描かれるいくつかのディストピアであることはいうまでもない。
だからこそ、田中慎弥は返り血を浴びながらも粛々と殺し続ける。けっして「それ」を忘れ去ることがないように。
実際、作中ではあらゆるものが消え、殺される。たとえば熊。つきあっていた女。つきあってもいなかった女。龍。そして、神。なにかとても恐ろしいこと。あるいはとても大切なこと。なかでも頻繁に殺されるのが、ほかでもない、「私」自身だ。
ある時は相手を殺したつもりが逆に刺されている。ある時は存在を締め出され、ある時はシンプルに訃報を受け取り、また、ある時は自ら命を断とうと試みる。さまざまな形で殺される「私」が身代わりに連れてくる情景。そこには「愛」などという、鮮やかで激しくて易しい感情は介在しない。あるのは、ぬかるみのように不穏で茫漠とした手応えだけ。その失望の昏さが、読者の立っている場所を懸命に震わせる。
表題作は、強烈な光が世界を焼き尽くす情景を描く。それを〈他人事のように〉眺めていた〈私〉に対し、〈母〉は最後までひたむきに助けを求める。〈ごめん、船はないんだ〉/〈ないのなら、造りなさい〉/〈材料になる木もないんだ〉/〈だったら苗木を植えなさい〉――ここで言う「苗木」こそが、本作で繰り返し問い返されてきたことなのだろう。
一瞬で燃え広がる炎に対し、苗木とはいかにも頼りない。植えつけた場所できちんと根を張るかどうかさえあやふやだろう。けれど、言葉を媒介させる営みとは本来、そういうものでしかありえないのだ――殺め続ける作家の掌が「文学」の感触を教えてくれる。