小川洋子『不時着する流星たち』〈刊行記念インタビュー〉世界の隅っこでそっと息づく人々の記憶、手触り、痕跡を結晶化した全10篇。
インタビュー
『不時着する流星たち』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
小川洋子『不時着する流星たち』〈刊行記念インタビュー〉
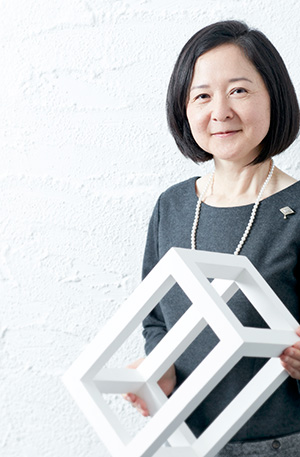
小川洋子さんの新刊『不時着する流星たち』は、
実に興味深い仕掛けのある一冊になっている。
それぞれの短篇の終わりに、その物語を着想する
きっかけになったのが何かが端的に明かされている。
読者は、まず物語を存分に味わい、さらにはこの作家の
創作の秘密を垣間見ることができるというわけだ。
これまでにない作品集が誕生するまでを聞いた。
小説にしかとらえられない
現実がある
――『不時着する流星たち』は一篇一篇に小川さんならではの魅力が詰まっていると思うのですが、まずタイトルがいいですね。
小川 ありがとうございます。この前に出した短篇集が『夜明けの縁をさ迷う人々』だったので、それと呼応するようなタイトルにしてみました。夜明けの縁をさ迷っていた人々が到着してみたら、それは不時着だったと。
――単なる「着陸」とも違う、何か危機的状況があったことを感じさせます。『科学の扉をノックする』で、国立天文台の渡部潤一先生と対談されていたことを思い起こしたりもしました。
小川 ゴリラの研究の第一人者である山極寿一先生や鳥のさえずりを研究されている岡ノ谷一夫先生もそうですが、科学者に惹かれてしまうのは、私が現実的なものにこだわりが強いからだと思います。今回の作品集も、実在する人物や実際に起こった事件から出発しているんですけど、私は自分が生きている世界がどうなっているかというのをすごく知りたい。そういう気持ちが、小説を描かせている。それを凝縮したのが今回の作品集だなという気がしています。

――小川さんがこれまでに描いた物語、たとえば『猫を抱いて象と泳ぐ』にしても、空想から生まれたのではなく、現実にあったことから着想されたというのは、意外に思う読者もいるのではないでしょうか。
小川 そうでしたね。あれも、実際に盤上の詩人と呼ばれたチェスの天才がいた。ですから私にすれば、今回も特に目新しいことをやったわけではなく、すべての物語をいつもこうやって描いてきたんですよね。自分が現実だと思っている、日常のあくせくした小さな世界を脱出しても、その外側にもっと広大な現実がある。現実の範囲は本当に計り知れず、ある範囲を超えると小説でしかとらえられないのではないか、というふうに思いますね。
――それにしても着想のきっかけを物語の終わりに記載するという構成は、まるで種明かしのようで画期的な試みじゃないかと。
小川 最後まで迷いました。『人質の朗読会』でそれぞれの短篇の最後に、その人の職業と年齢だけを書いたんですが、それが非常に重要な一行だということに、気がついたんですね。その人物がどういう人だったのかをあれだけ長々と描写してきても、最後に「お菓子職人 68歳」と書くことの方がものすごくイメージが膨らんだりする。そういう現実的な言葉、いわゆる情報しか含んでないような言葉には、実は深い情緒が潜んでいるということをあの時に体験して、同じような形式でやってみたくなったんです。直接のきっかけは『ニーチェの馬』という映画を観たことでした。哲学者のニーチェは、広場で馬が鞭打たれているところに遭遇したせいで精神を病んでしまったという逸話があるんですが、映画にはニーチェは一切出て来ないんですよ。その馬を飼っている老人の話なんです。
――えっ、それは意表を衝かれるというか。
小川 びっくりしますよね(笑)。でもその映画を観た時に、ニーチェのような実在の人物に光を当てながら、その陰にいる名もない、歴史にも記録にも残らない人の物語を描いてみたいと思ったんです。
子どもが語り手だからこそ
見えるもの

――読む時のお楽しみのために、すべてを明かすわけにはいきませんが、たとえば冒頭の一篇『誘拐の女王』は、ヘンリー・ダーガーから着想されています。
小川 ヘンリー・ダーガーのことは『琥珀のまたたき』を描くにあたって、アール・ブリュットについて調べた時に知ったのですが、ちょっと別格というか。どこをすくい取って小説にするかは毎回悩んだんですが、ここまで行っちゃえば、もう、如何様にも描けるという感じの人ですよね。
――かなり特異なアーティストの、どんなところが小説の糸口になったのでしょう。
小川 『誘拐の女王』の場合は「子どもたちの守護者」というダーガーの墓碑銘からでしたね。もっといろんな案もあったんですよ。たとえばダーガーには、ひとりだけ友人がいて、二人で遊園地に行った写真が一枚だけ残っているんです。その日のことも、小説に描けると思って。遊園地の回転木馬の柱の裏に、ダーガーが二人で乗った思い出に絵を残していて、それを誰かが見つけるとかね。もう、いくらでも描けるわけです。
――そちらの話も読んでみたくなります。
『誘拐の女王』は少女のもとに、義父の連れ子にあたる年の離れた姉がやってくる話で、この姉が何やら秘密めいた裁縫箱を抱えているところなんて、小川ワールドそのものだなと。何からインスパイアされた話なのかという痕跡が、そのまま残っているわけではないんですよね。
小川 この一篇は子どもの視点から描いていて、子どもだったがゆえに教えてもらえなかったことがたくさんある、そういう空白の暗闇を描いてみたいと思った。ダーガーという異常に子どもに執着した人を取り上げた時に、子ども時代にしか持っていないいびつな世界観が立ち現れてきた。やっぱりダーガーが描かせたんでしょうね。
――少女が姉と何かに追われるように街を彷徨うところも実に印象的で、小川さんにも、そうした体験があったのでしょうか。
小川 昭和のあの時代って、近所に何をしているかわからないおじさんがいましたよね。言葉を交わしたこともなかったのに、私は、そのおじさんと歩く夢をよく見ました。玄関先に長椅子を出して、浴衣か何か着て座ってるんだけど、たぶん口がきけない人だったんだと思います。いつもひとりぼっちで、気の毒に思っていたのかもしれませんね。今でもよくその人のことを思いだして、涙ぐんでしまうことがあります。ダーガーも、近所の人からそう見られていたという気がしますよね。
――少女が彷徨う時には、そうした道行の同伴者が要るのかもしれませんね。
小川 そうですね。謎めいた年上のお姉さんが現れたことで、この主人公が持っている子ども時代の暗闇が一層濃密さを増したということなんでしょうね。子どもの視点というのは、この作品集の重要なキーワードで、子どもが語り手だからこそ見えるものがある。子どもって、自分が実は捨て子だったという妄想にとりつかれたりしますよね。見えてないものを想像力で補うので、物語がすごく広がるんです。死者に近しい存在でもあるし、物語の語り手として本当にふさわしい。それでつい子どもに甘えちゃうというのがあって、それはむしろ気をつけなきゃいけないなと思います。

生きていく哀しみに
寄り添うこと
――『カタツムリの結婚式』は、もとになったパトリシア・ハイスミスの逸話にも驚かされました。
小川 当時、彼女の小説が原作になった『キャロル』という映画がヒットしていて、私も観に行ったんです。
――レスビアンであることをカミングアウトできなかった時代に、彼女が別名義で描いた小説ですよね。
小川 写真を送ってもらったら、パトリシア・ハイスミスって、ものすごくきれいなんですよ、若い頃。調べてみたら、カタツムリが大好きで、庭で何百匹も飼っていたらしいんです。それでフランスに引っ越す時に、生きたカタツムリを持ち込むことが禁止されていたので、自分の乳房の下に何匹も隠して往復したって。何これ、どういうことってなりますよね(笑)。
――そんな美人が、まさかカタツムリをそんなところに(笑)。
小川 でも確かにカタツムリって魅力的な生き物で、雌雄同体なんです。ユーチューブで交尾しているところが観られるんですけど、ひとつに溶け合っているみたいな。あの短篇に登場するのは、だからパトリシア・ハイスミスのカタツムリの末裔です。
――それぞれの短篇に、そうしたグロテスクなくらい、なまなましい生に触れる瞬間があって、そこがまたすごく魅力的でした。
小川 『臨時実験補助員』の母乳を搾る場面とかね。母乳こそ、ものすごくなまなましい命の塊ですよね。『肉詰めピーマンとマットレス』のテーブルを埋め尽くす肉詰めピーマンであるとか、『測量』のおじいさんの声とか、生きていることの禍々しさにどこか繋がっているものが、発想の原点になっているんでしょうね。
――グレン・グールドやエリザベス・テイラーといった実在の人物以外に、ギネスブックの公認記録や過去のオリンピックからインスパイアされた短篇もあります。

小川 昔からギネスブックを読むのが好きで、いつも机上に置いてあるんです。日本でもよく世界一長い巻きずしをつくるとかやってるじゃないですか。バカバカしいことに、みんなで挑戦してるというのがいいなと。オリンピックの資料も結構丁寧にとってあって、意外な事実の宝庫なんですよ。たとえば札幌オリンピックの時に、フィギュア・スケーターのジャネット・リンが大人気になるんですけど、彼女が転んだ氷が売りに出されたことがあるんです。ジャネット・リンが尻もちをついた氷で水割りを飲もうって(笑)。
――それ、実話なんですよね(笑)。
小川 ですから乱暴に言ってしまえば、人間って変な生き物なんですよ。そういうバカなことをやるし、間違いを犯すし、滑稽なことをしでかす。そういう人間のことを「もう、なんてヤツだ!」と思いながら、でもそういう人間を愛おしいという気持ちが、根底にあるんですけどね。
――なるほど、まさにそういうところから、小川さんの描く物語が生まれてきた。
小川 小説を描く時の資料のノートの、そのもう一段階前のノートがあって、そこには新聞の切り抜きがいろいろと貼ってあります。いつもそこからのスタートですね。
ですから、何もないところから、空想で「こんな人がいたら面白いな」と思って、自分がつくりあげた霞みたいなものを強固にするために取材するというんじゃないんですよね。いつも現実から始まっている。現実の中にいる人を、まるで私が空想でつくりあげたかのようにするという順番です。
――それって、つまり小説のネタ帳みたいなものなんでしょうか。

小川 ネタを集めてると言うと、機械的に書けるものだと思われるかもしれないですけど、そのネタの状態から小説に行くまでの間に、ものすごく紆余曲折というか複雑な回路が必要で、描いてしまった後はどれがネタだったのか、自分でもわからないぐらいになっていますね。
――小川ワールドの原液みたいな。
小川 そうですね。ダーガーの絵巻物にしても、何か無慈悲に切り捨てられないものがあって、人間が生きていることの根本にある逃れようもない哀切さと言いますかね。生きるって、なんて哀しいことなんだというのを、ある種の天才たちは、ものすごく高度な作品のかたちで残してしまう。私たちは、生きるってあまりにも哀しいことだから、それを見て見ぬふりをしてしまうんだけれど、そうできない人々がいるわけです。なかったことにできない人たちが。そういう人間のどうやっても紛らわしきれない悲しみに、小説を通してひと時寄り添うというのは、必要なことだと思うんですね。小説にしかとらえきれない現実があるというのは、そういうことかもしれません。
小川洋子(おがわ・ようこ)
1962年岡山市生まれ。88年『揚羽蝶が壊れる時』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。91年『妊娠カレンダー』で芥川賞、2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞と本屋大賞、同年『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞、06年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞、13年『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。



































