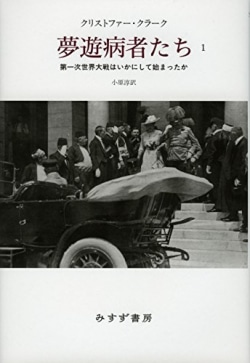『夢遊病者たち 1』
- 著者
- クリストファー・クラーク [著]/小原淳 [訳]
- 出版社
- みすず書房
- ジャンル
- 歴史・地理/外国歴史
- ISBN
- 9784622085430
- 発売日
- 2017/01/26
- 価格
- 5,060円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『夢遊病者たち 2』
- 著者
- クリストファー・クラーク [著]/小原淳 [訳]
- 出版社
- みすず書房
- ジャンル
- 歴史・地理/外国歴史
- ISBN
- 9784622085447
- 発売日
- 2017/01/26
- 価格
- 5,720円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
プロセスを丁寧に分析 近現代史に関心を持つ者、国際関係に関心を持つ者の必読文献
[レビュアー] 網谷龍介(津田塾大学教授・政治学・ヨーロッパ政治史)
第一次世界大戦開戦100周年を前に各国で多くの本が出版されたが、ケンブリッジのドイツ史家が開戦に至る過程を追跡した本書は、最も話題を呼んだものの一つである。
第一次世界大戦が「なぜ」起こったのか、は常に激しい議論の対象であった。開戦の責任の所在と密接に関連するからであり、多くの研究が罪責の所在を検討してきた。責任の所在という実体問題のみならず、この主題からは、伝統的な外政優位論に対抗する、「内政の優位」という新たな視座もうみだされた。国際政治学においても、第一次大戦はさまざまな理論や実証の素材となってきた。大戦は多国間勢力均衡の根源的不安定の証拠か、二陣営への同盟の固定化が戦争をもたらしたのか、構造要因と個別的事件の関係は、等々の論点がある。
このような大テーマにおける本書の貢献は、「なぜ」という問い(とそれに付随する責任論)をいったん脇に置き、「いかにして始まったか」(本書副題)というプロセスを、丁寧に叙述しているところにある。しかも本書は単に情報量の多い本という域にとどまらない。さまざまな原因論を踏まえ、それがプロセスの中でどのように作用したのか/しなかったのかを意識し、分析的に描いているのが本書の最大の特色である。読者は本書の中で、個別の事件をこえた国際関係の一般的問題を思考することを繰り返し促されることであろう。
より具体的には、開戦責任論に付随しがちな、「国」を擬人化した主語とする思考方法を廃し、国内の多様な主体・状況の組み合わせが、「結果として」特定の対外政策の選択につながるプロセスを描く点が特徴である。しかもその視角が、関係する全ての国について採用されている点が見事である。ドイツでも、あるいはイギリスでも、政治家や外交官、君主は国内政治過程の一プレイヤーに過ぎないのであり、特定の決断者が全体を掌握していたわけではない。それを明らかにすることで、戦争の原因を、特定国の文化や制度の特質に帰すことも回避されている。その結果、いわば等身大の政治的主体が、それなりに理解可能な判断に基づいて行動し、結果として凄惨な結果が生じた、ということが浮き彫りになる。
ただし著者は、登場する主体の行動が正しかったとして免責しているわけではない。合理的な判断が行われなかった要因を、同盟の構造、軍事力の認識、さらには文化的要因なども含め、手際よく叙述に織り込んでいる。特に、ほぼ同一の問題構造の中で危機が処理されていく中で、前の選択が認識の変化を通じて後の選択を拘束し、徐々に選択肢が失われていく様相の分析は、過程に重点をおく本書ならではの説得性がある。また、国内の多様な主体の絡み合いが、外に対しては異なる対外的メッセージ相互の矛盾・ブレとしてあらわれ、結果として関係の不安定化や、特定方向への偏った認識をもたらすことを示しているのは印象的である。
本書が反響を呼んだ一因は、上記のようなアプローチが、相対的にドイツの責任を軽減し、セルビア要因を重視しているかに読める点にある。だが評者には、そのような読み方は本書の美点を活かすものとは思えない。むしろ、天使も悪魔もいない世界において、それぞれの主体に何が可能であったのか、どの時点まで戦争は回避しえたのかを問う方が生産的であり、本書の趣旨に沿う議論ではないか。
最後に、翻訳はとても読みやすく明晰である。また原著のミスリーディングな記述や事実の誤りなどについて注記があるほか、ドイツ語版と英語版の記述の相違も指摘され、丁寧な作業に頭が下がる。翻訳の質の高さも含め、本書は近現代史に関心を持つ者、国際関係に関心を持つ者の必読文献と言ってもよいだろう。