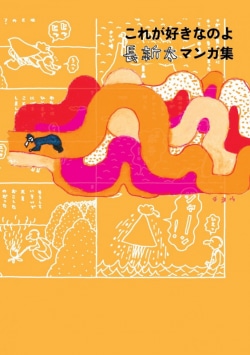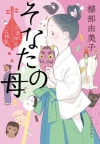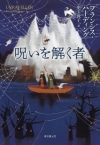『これが好きなのよ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
椹木野衣は 『これが好きなのよ 長新太マンガ集』を読んで 今の世の中に息苦しさを感じるすべての大人に勧める
長新太といえば、世の中的には絵本作家ということになっているけれども、あれは大人が読んでも、すこぶる刺激的である。というか、大人が読んでも十二分に刺激的な読み物を、あれこれ工夫して子供でも十分読めるようにしたのが、長=チョーさんの絵本の正体だったのではあるまいか。
そういう意味では、「大人も子供も一緒に楽しめる」みたいな、わりとよくある代物とはまったく似て非なる。僕も例に漏れず子供のころ図書室(図書館ではない)などで、なんだかおかしな表紙やタイトルが気になって、ふと手にしたのが長=超=チョー・ワールドへの入口だったわけだが、たいていはいつもキツネにつままれたような気分になった(いや、チョーさんの作画からしたらタヌキに化かされた、か)。
というか、もう少し精密に言うと怖くなった。でも怪談ではないのだから、なにが怖いのかがわからない。なにが怖いと言って、世の中に、理由がわからず怖いことほど恐ろしいことはない。チョー・ワールドはいつもそんなトラウマ的な余韻を残して読書の時間からシュッと去って行き、でもその後味は50歳を過ぎた今になっても、心の底のほうでずっと残っている。たぶん一生残るのだろう。
ところでそのチョーさんが、雑誌『話の特集』などで前後のエッセイなどに挟まれてマンガを描いていたのは知っていた。これは大人の読み物だから、チョーさんも読者としては大人を想定して描いている。だからなのかもしれない。絵本のとき以上に容赦がないのである。
前に読んだ話では、チョーさんは絵本作りでは最初、人には見せられないほど極限的にまでヤバい世界に突き抜けておいて、そのあとちょっとずつ世の中の許容範囲まで降りてくる、というようなことを書いていた。でもそれは絵本だからそうなのであって、大人の読み物ではそこまでの必要はなくなる。ゆえにここに収められたマンガでは、チョーさんの脳内世界の猛嵐に前触れなくいきなり吸い込まれて、前後不覚にされたような印象さえ受ける。絵が一見ほのぼのとしているから、そのぶん暴力的でさえある。
でも、どれも掲載時には前後を別の書き手が文字で挟んでくれていたから、過激さはそこそこ薄められていたはずだ。ところが本書では、そこからマンガだけを抽出して、丸ごと一冊にしてしまっている。帯には「“マンガ家”長新太の全貌を明らかにする」とまで言葉が踊っている。こんな危険なことをしてしまっていいのだろうか。
でも同時に、救われたような気分にもなるのだ。今の世の中、あれもダメ、これもダメで息が詰まりそうな思いをしている人が多いだろう。実は以前は大人にはある程度、許される領分というのがあったが、今ではまるで子ども扱いだ。そんな思いをしているすべての人に、この本を強くお勧めしたい。これこそ大人ならではの味わい! に適度に甘く、でも底なしに深い笑いが、よくできた鯛焼きのように餡状になって、頭から尻尾までギッシリ詰まっている。