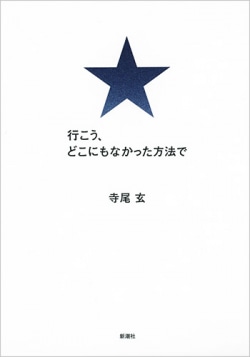『行こう、どこにもなかった方法で』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「苦しみつつ、なお働け」。「バルミューダ」創業者がロックスターの夢を捨て、ものづくりの世界へと飛び込んだ理由
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
自著で「自分語り」をする著者は少なくありません。もちろん、それ自体が悪いわけではないのですが、気になることがあるのというのも事実。というのも、そうした本の多くが自己満足的であり、「なぜそこに行き着いたのか」というファクト(事実)が明確に示されていない場合が少なくないからです。
しかし、『行こう、どこにもなかった方法で』(寺尾 玄著、新潮社)の場合は話が別。なぜならここに描かれている彼の人生は、(最終的に成功へと行き着くとはいえ)苦悩と失敗の連続だから。その道のりが、きちんと丁寧に描かれているのです。
これまでの私の人生は多彩だった。変化に富み、いつもいつも、山あり谷ありだった。驚きと失敗の数だけは、人に負ける気がしない。平坦な道が極端に少ない、決して退屈しない人生だった。
その人生は、はたから見ると危なっかしく見えるかもしれない。いつもドキドキしながら生きていける反面、安定とは程遠い道だ。
それでも色彩豊かな人生を、うらやむ人もいるかもしれない。若い人たちが影響を受けて、自分もワイルドサイドを行きたいと思ってくれるかもしれない。
あまりお勧めはしないが、興奮と驚き続きの人生は、どうしたら生きることができるのか。その答えは、とても簡単だ。
私は、特技を持っているのだ。なぜ特技と言えるかというと、他の人たちがそれをできない時でも、私はいつもそれをできたからだ。私の特技、それは可能性の存在を完全に信じられることだ。(「序章 可能性」より)
まさにこの記述のとおりで、驚くほど純粋で愚直、不器用。ある意味で、スタイリッシュなライフスタイルとは対極の位置にあるといっても過言ではありません。しかし、だからこそ心に強く訴えかけてくるのです。ちなみにご存知の方も多いと思いますが、著者は従来の価値観に縛られることのないスタンスを持つ家電メーカー、バルミューダの代表取締役です。
高校を中退し、単独でスペインを放浪
どんな人も可能性を持っている。それはおそらく、人が持っているものの中で最も貴重なものなのだが、可能性であるがゆえに、確実ではない。例えば、今晩、私は夕食を食べるつもりだし、明日は会社に行くつもりだ。のちのち行こうとしている場所もあるし、やろうとしていることもある。
しかし、これらの素敵な未来は、本当にやってくるのだろうか。そういう意味では、今晩の夕食も確実ではないかもしれない。自転車をとばしすぎて、帰り道に骨折して入院をして、夕食を食べ損ねるかもしれない。
私たちの未来に起こることで、唯一確実なものは、私たちが死ぬということだけである。この一点だけが私たちに約束されたものであり、それ以外は全て可能性なのだ。(67ページより)
著者がこうした考え方を学ぶきっかけとなったのは、中学生時代の訪れた母親の死でした。そしてその数年後、十代後半で自分の将来を決めなくてはならないということに疑問を感じて17歳で高校を中退。約1年をかけ、スペインを中心とした周辺の国をひとりでまわるという、「粗い計画」を実行します。当然のことながらその道程は波乱万丈ですが、結果的にはそこで得たものが著者ののちの人生に大きな影響を与えることになります。
結局のところ、あの旅で私が手に入れたのは自信なのだと思う。それは、成功する自信とか、何かをうまくいかせる自信ではなく、それ以前の基本的な感覚、自分は生きていけるという感覚だ。行きたい場所を選び、自分の身を心配し、守り、そこまで移動する。たくさんのものを見て、おいしいものも食べている。仕事をしているわけではないが、生きていけるかどうかと言えば、紛れもなく、生きている(108ページより)
17歳にして単身で海外を放浪した経験は、それだけでも大きなトピックになりうるでしょう。しかし読み進めていくと、著者にとってそれは単なる「プロセス」でしかないことがわかります。その証拠に、18歳になると新たな目標を定めることになります。それは、「ロックスター」になるということ。
きっかけは、アメリカを代表するロックン・ローラー、ブルース・スプリングスティーンの歌詞に感動したこと、それ以前から詩を書いていたため、将来は詩人か作家になるものだと思っていたものの、スプリングスティーンとの出会いによって考え方が変わったというのです。
「天才」だと信じてロックスターを本気で目指す
詩を表現する方法として、ロックもありなのだ。音楽にすると文字だけではない、サウンドもメロディーもあるし、声もある。その全部を使って詩の世界を表現できる。それに、作家になるよりもロックスターになった方が派手だ。
十八歳の私は単純だった。ロックスターになることにした。ギターを買い、最初に覚えた四つのコードを並べ替え、自分の曲を作り始めた。歌詞には困らない。きれいなコードを並べてギターを弾いているうちにメロディーは自然に浮かんできた。(117ページより)
大人がこんなことを聞いたとしたら、「なにを甘っちょろいことを」と感じるに違いありません。事実、かなりツメの甘い話です。ところが、彼は事務所との契約を勝ち取り、メジャーデビュー寸前まで進んでしまうのです。おそらく、そこまで彼を進ませた理由はふたつ。ひとつは、周囲がなんといおうと「本気」だったということ。やはりこの局面においても、自分の可能性を信じて疑わなかったのです。そしてもうひとつは、自分は「天才」だと本気で考えていたということ。
しかし、夢に近づいたり、夢から遠ざかったりを繰り返しながらも最終的には挫折…というひとことでは語りつくせない物語がその背後にはあるわけですが、いずれにしてもここで音楽の道に見切りをつけざるを得なかった著者は、さまざまな思いを巡らせるなかで新たな目標を見出します。
創造的な発信をしたいという想い
私は物心ついた時から、いつも何かを作っていた。作文、工作、絵から始まり、詩、バイクの改造、小説、そしてここ数年は、楽曲を作ってきた。毎日、毎日、それを続けてきた。
そして創造には結果が求められる。趣味だったらその品質を問われることもないのかもしれないが、趣味ではないのだ。いつも大真面目だった。自分が作るものが世界を変えることを望んでいたし、それが元で何かが起こるようなものを作ろうとしていた。
これは難しい。難しいので私はいつも、作っているものについて悩み、考えてきた。このようなことをなぜ続けるのかといえば、それが一番やりたいことだからだ。なにか素晴らしいものを作ろうとすることは、私の人生の喜びであり、これなしでは生きていけない。
ヒーローになりたい、ロックスターになりたいとは言いつつも、何かを作ることがいつも自分の隣にあった。むしろこちらが私の人生の核心なのではないだろうか。(139ページより)
つまりこうした思いが、バルミューダの創業につながっていくわけです。が、ここには重要なポイントがあります。
何か創造的な発信をして世の中に影響を与えようというのが音楽家や詩人、作家の活動なのだが、考えてみれば、そういうことは事業の世界でもいろいろな会社がやっているのではないだろうか。
世界を相手にして活躍する企業はたくさんあるが、その中の幾つかの企業のやり方が、私にはバンドのやり方そのものだと感じられた。特に気になったのが、アップル、ヴァージン、パタゴニアの三社だ。(153ページより)
高校を中退して海外を放浪〜ロックスターを目指してバンド活動〜ものづくりの道へ…という流れは、他者からすれば場当たり的なようにも思えます。しかし本書を読み進めていくと、それぞれの行動の根底には「(なにをやるにしても)創造的でありたい」という想いがあることがわかります。いわば、すべての決断や行動には、きちんとした裏づけがあるわけです。
しかも驚くべきは、基礎的な知識も持たないまま、すべてを自分でやろうと考えて行動に移してしまっていることです。起業して「ものづくり」をしたいけれども、自分には知識も技術もないという場合、プロフェッショナルを招き入れ、自身は経営に特化するなどの手段を選ぶのが一般的だと思います。
ところが著者はなんの疑問を持つこともなく、町の工場に飛び込んで頼み込み、設計、製造を独学で習得してしまうのです。もちろん、経営者としての業務もこなしつつ。「常識的には」考えられないことですが、そもそも常識という概念が著者のなかにはないのです。つまりそれこそが、バルミューダの可能性なのでしょう。
とはいえ本書は、最終章まで進んでも、なかなかハッピーエンドにたどり着きません。というより、「いつ倒産してしまうのか?」という状態が最後の最後まで描写されます。外からは華やかに見えるかもしれないけれども、実際に映し出されるのは、ギリギリまで戦い続ける著者の姿。つまり、現在もまだ著者とバルミューダは途上にあるということ。おそらく、本書が伝えようとしているのは、そんな事実が持つ「可能性の価値」です。
安住や安定、とても魅力的な響きだが、きっとそれはこの世にはない。苦しみつつ、なお働け、なのだ。(249ページより)
「現代の若者は醒めていて、食らいつくような向上心が感じられない」というような意見を、しばしば耳にします。果たして本当にそうなのか、その点については疑問も残るところですが、ひとつだけオススメしたいことがあります。
性格が熱かろうが醒めていようが、夢があろうがなかろうが、なんらかの形で「どう生きるべきか」を模索しているのであれば、本書を読んでみるべきだということです。
必ずしも、著者の行き方だけが正解だというわけではなく、他にもいろいろな手段があるでしょう。しかしそれでも、ここに記されたひとつの生き方は、なんらかのヒントになってくれるはずだからです。