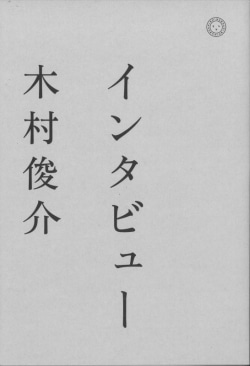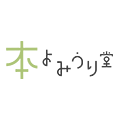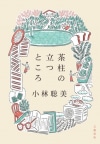『インタビュー』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ネット時代に取材でデータを作る時代
[レビュアー] 佐久間文子(文芸ジャーナリスト)
学生時代にインタビューを始め、成果を本にし、その後も二十年以上インタビューを職業にしてきた人が、「インタビューとは何か」を考え抜いて本にした。
仕事の中でインタビューをする機会がある人に面白く読めるのはもちろんのこと、これまでそういう機会のなかった人にも、いまがどういう時代で、どんな風に成り立っているのか、リアリティーを持って掴むことができる本でもある。
たくさんの著作のある著者の仕事のスタイルは、一人の人に時間をかけてじっくり話を聞き、地の文は極力使わず、その人の声でインタビューを構成するものだ。これまで話を聞いたのは料理人や漫画編集者、スポーツ選手や芸術家など多岐にわたり、著名人もいれば市井の人もいる。
ハウツー本ではない。第一章「道具としてのインタビュー」では自身の仕事のやりかたが惜しみなく開示され、じゅうぶん実用的なものではあるが、効率的な仕事のやりかたはここでは奨励されていない。この仕事は「ヒマな者勝ち」だとできる限り丁寧な準備をすることを勧め、「インタビューそのものを趣味のように味わってもいいのでは」と宣言する。取材相手と向き合う時間を大切にして、読者と同じように相手の言葉を「読む」。
第二章「体験としてのインタビュー」では、さらなる深みに降りていく。「ネット時代における、発言や取材のドーピング」「よく見せるための『作りごと』をどうあつかうのか」といった項目は、取材と広告の境目があいまいになったいまの時代に、取材をする人間として非常に切実な興味を持って読んだ。
組織に属さず、一人で仕事する著者は、弱い立場を大切に考え、「男手」ではなく「女手」の聞き手たらんと考える。一方で、自身の仕事に非常に自覚的なインタビュアーでもある。「なにもかもがやりつくされているみたいに思える、人が部品のようにあつかわれている時代において、なにかをあらたにやろうとすること」を自身のテーマとして訊くことで、たとえ誰かに依頼された仕事であっても、自前の質問を発してきた。
発信元もその真偽も不明な言説がネット上にあふれる時代に、インタビューは「自前のデータを作る作業」だとも言う。相手との関係で結果的に表に出なかったインタビューすらも、そういうふうに考えれば自前のデータの一部にはなる。
彼がこれまでに集めてきた千人以上の膨大な声は、いずれひとつのテーマにもとづいて編み直され、新しい著作になることもあるだろう。それは、スタッズ・ターケルが『仕事!』を発表したときのように、これまで誰も試みたことのない新しい切り口のノンフィクションになるのではないか。