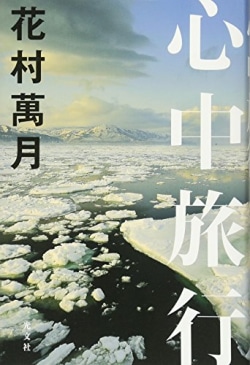『心中旅行』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『心中旅行』刊行記念インタビュー 花村萬月

――薬を飲んだ澤野が「純白の眠り、自我喪失の人工楽園にじわりと墜(お)ちこんでいく」という描写がありましたが、真っ白に閉ざされた北海道の景色とも、イメージが重なってくる印象を持ちました。そういう意味では、全体に「死」がずっとありました。
花村 まあ、他人事(ひとごと)じゃないよと。あんたも毎晩死んでいるんです、と(笑)。というか、生きることだけじゃ、もたないんじゃないか。夜毎の死があるから、生きていられるのかもしれない、ということだね。
――詳しくは書けませんが、澤野はいろいろトラブルが重なって、どん底のどうしようもない状態で、もう死のうと言って家族で旅に出る。死ぬための旅なわけですが、そこから物語がすごく明るいトーンになったのが印象的でした。
花村 俺自身は、ガキの頃からすごく楽天的な人間で、悩まない、悔やまない、という感じなんだけど、その根っこにあるのは何かなとさぐっていったら、「どうせ死んじゃうんだ」ということに行きついてね。多少恥ずかしいことがあっても「どうせ、死んじゃうんじゃん」というのが、投げ遣りなものじゃなくて、ずっとある。思春期の頃から、「じゃあ、諸々悩む理由がないじゃん。終わりが来るのに、何を悩むの?」と考えていた。だから俺、自殺を考えたこともない。
――澤野家の人々は、あそこで旅に出るとなったときに、死ぬことに決めてふっきれた、ということなのでしょうか?
花村 大袈裟な物言いになっちゃうけど、俺と同じ境地になったんだよね。「どうせ死ぬんだし」と。だから、いま生きているときのことも、あれこれ思い悩む必要はないんじゃないかと。もちろん死自体は苦しいものだろうけど、でも、逃れられる人はいないし、「どうせ死ぬなら」という考え方は、絶対みんなあると思うよね。
――心中旅行、みんなの人生がそうとも言えるわけですね。
花村 死に向かって旅行をしているようなものでね。延々とね。その旅行の目的地にいつ着くのか、わからないんだよね。あしたかもしれないし。
――澤野本人は家庭がまずいことになっていることに途中まで全然気づきません。
花村 たぶん、俺の楽天性の延長にあるのだろうけど、思い悩まないから、他人の、たとえば、一緒に暮らしている妻が追い詰められていることもわからないんだよね。どこかで俺は相手にも楽天性をかぶせちゃうから。
――ああ、なるほど。
花村 本音を言うと、「死にたい」と言っている人の気持ちがわからないわけ。そういう俺の中の齟齬(そご)が問題だと思う。
――確かに、澤野は、自分の仕事のこと、自分と豊嶋のことはすごく考えていますが、途中まで妻や子供のことは、ほとんど考えている気配がないですね。
花村 まさに俺だよ(笑)。
――作品の終盤、吹雪の北海道を走っている場面は、ファンタジーではないですが、どこまでが虚でどこからが実なのかわからないような印象もありました。
花村 昔、地吹雪の東北道をひたすら車で北上していたときに、空に向かって飛んで行くんじゃないかと怖くなったんだ。錯覚で。危ないんだよ、本当に。吹雪に煽られているうちに、ちょっと幻想的になっちゃうんだよ。天地が逆になったようなね。
――そういう意味では、確かに終盤は、読んでいて催眠術にかかるというか、ちょっと幻覚を見せられているような感じもありますね。
花村 もう死に片足突っ込んでいる、という意図もあったんだけどね。「もう死にかけているんだよ、この人たちは」みたいな。黄泉の国に向かいつつあるよと。
――いま話を伺いながら思いましたが、実は心中旅行に出ることを決めた時点で、あの家族はもう死んだのと一緒だったのかもしれませんね。
花村 「どうせ人間、死んじゃうんだし」と認識した時点で、人は結構強くなれちゃうんじゃないかな。
――書くのに苦労した点があれば、教えてください。
花村 紀行文的部分の細かさだね。もう少し端折ったほうがよかったとも思うけれども、書かずにいられなかった。厳としてある世界と、死にゆく人の対比を意図したんだけれど。
――本作の読みどころはどういうところでしょうか?
花村 やっぱり、人間と人間の齟齬というのかね。妻のことも、あるいは豊嶋のことも、わかっていないというね。もちろん子供のこともわかっていないし、会社の人間関係も推して知るべしでしょう。
編集者の仕事の面白さも読んでもらえたらというのは、どこかにあるね。俺も小説家より編集者になりたい。書いていてすごく思うよ(笑)。誰かをプロデュースするみたいな仕事をしてみたいな。……まあ、ないものねだりをしても仕方がないね。