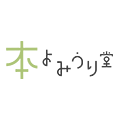『マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム――エビデンスに基づく支援環境開発アプローチ~精神保健福祉への適用例から~』
[レビュアー] 岩田正美(日本女子大学名誉教授)
はじめに
まず表題のマクロ実践ソーシャルワークという、やや聞き慣れない言葉に戸惑いを覚える人も少なくないかも知れない。ソーシャルワークという言葉自体、社会福祉領域以外で十分理解されているとは思わないが、ソーシャルワークにミクロ、メゾ、マクロという区別を付けて議論する習慣は、ソーシャルワーク論の専門的世界に限られているように感じる。本書は、その専門的議論を、日々の現場での実践に役立てられるよう、具体的なアプローチ法=エビデンスに基づく支援環境開発アプローチとして、豊富な実践例と共に示したものである。日本のソーシャルワーク論(日本だけではないかも知れないが)は、北米で開発され、変化しているソーシャルワーク論に依拠することが多いためか、その用語自体の理解が難しい面がある。このミクロ、メゾ、マクロの区別も例外ではない。本書でも指摘されているように、古典的なソーシャルワーク論は、ケースワークやグループワークと言われたミクロレベルを中軸としながらも、コミュティへの働きかけ(コミュニティ・オーガニゼーション)、社会制度への働きかけ(ソーシャル・アクション)をその使命としていると言われてきた。それはケースワークなどが、問題の根本解決に必要な制度や環境の問題を覆い隠す役割を果たしてきたという批判への反論、ソーシャルワークの「良心」の吐露であったかもしれない。だが、「良心」の吐露ではなく、メゾ・マクロの実践効果を客観的に示し、これをソーシャルワークの重要分野として具体的に提示したところに、本書の「新機軸」たる所以がある。
1 本書の構成
本書は、第Ⅰ部 総論(第1章 マクロ実践ソーシャルワークの新機軸、第2章 エビデンスに基づく支援環境開発アプローチの枠組み、第3章 支援環境開発のニーズと支援ゴール、第4章 ソーシャルワーカーの姿勢・知識・技術)をまず理論的前提とし、第Ⅱ部 精神保健福祉における適用例・実践例(第5章 脱施設化と地域生活支援システムの構築、第6章 包括的ケアマネジメントACTの実践・普及、第7章 援助付き住宅の効果モデル形成、第8章 退院促進・地域定着支援の効果モデル形成、第9章 ニーズに応じた体系的な家族支援のあり方、第10章 「ひきこもり」状態への支援と効果モデル開発、第11章 「働きたい思い」を実現する就労支援モデル、第12章 ピアによるサポート活動の効果モデル形成)で実践例を検討し、最後に第Ⅲ部 マクロ実践SWとエビデンスに基づく支援環境開発アプローチの可能性(第13章 EBPプログラムと支援環境開発アプローチ、第14章 エビデンスに基づく支援環境開発アプローチの意義と可能性)で締めくくるという構成となっている。実践例は第Ⅱ部の精神保健福祉分野の7つの具体的な課題にそったエビデンスのある効果プログラムの実例である。
2 理論前提と定義
キーワードは「エビデンスに基づく支援環境開発アプローチ」であるが、別のさまざまな概念、たとえば「ニーズ志向型支援環境開発アプローチ」「当事者協働型支援環境開発アプローチ」「アドボカシー型支援環境開発アプローチ」などが付随しており、かなり複雑な構成である。第2章の「エビデンスに基づく支援環境開発アプローチの枠組み」でその関係が説明されている。つまり「エビデンスに基づく支援環境開発アプローチ」は3つの支援目標に沿って整理すると、①地域における自立生活の維持という目標に対しては、ニーズの解決という明確な支援ゴールを設定した「ニーズ志向型支援環境開発」、②当事者の「ストレングス」を最大限に伸ばし、エンパワーメントを促進して、そのリカバリー、ウェルビーイングの実現支援という第2の目標に対しては、ボトムアップ型の「当事者協働型支援環境開発アプローチ」、③福祉ニーズを持つ人びとやその施策への理解を促し、公私の支援環境を開発することを目標として「アドボカシー型支援環境開発アプローチ」があるという。「ニーズ志向型支援環境開発」はニーズの領域ごとに解決すべきゴールの設定がなされ、これを②のボトムアップ型で進め、それらを包含したところに③のアドボカシー型が展開される、という理解が示されている。だが、本書の眼目はこの3者を枠組みとしたアプローチにあるというよりは、ニーズ志向アプローチの中で、ニーズ領域ごとに、「支援環境要素」を確定し、有効な支援パッケージ(効果的プログラムモデル)構築の検討を行うことにあるように思われた。その成果が社会的合意を得た支援環境の開発に繫がる、というわけである。とりわけ科学的にその効果が立証されたプログラムとしてのEBP(エビデンスベーストプログラム)や、EBPまでいかないが実践的裏付けがあるベストプラクティスプログラムをもっと日本でも活用していく必要こそが、著者の訴えたいことのようである。
第Ⅱ部の各章で取り上げられたのも、すでに(世界的には)EBPとして確立している「包括型ケアマネジメントACT」「家族心理教育プログラム」「IPS援助付き雇用プログラム」であり、あるいはベストプラクティスなどの根拠のあるプログラムであった。「まずは住居をプログラム」もEBPまではいかないが著者のおすすめである。このEBPという考え方は第Ⅲ部に詳しく展開されるが、医学や保健分野での定着に比べると、社会福祉領域では必ずしもそうではなく、ソーシャルワーカーが中心になって、その導入、構築、評価を行うべきだというのが著者の問題意識と言える。
3 議論
評者はEBPにも、ソーシャルワークにも詳しいわけではないが、効果あるプログラムを実践家と当事者が協働で構築すること、あるいは評価していくこと、それ自体には異論はない。すでに世界標準であるプログラムがあるのに、日本への適切な「技術移転」ができていないことへの、著者のもどかしさもよくわかる。実践例の各章では、いくつかの世界標準プログラムとその日本への「技術移転」の可能性が詳しく述べられており、「日本的しつらえ」という魅力的な言葉で、背景の異なるプログラムであっても移転可能なことが示唆されている。これらは、著者のフィールドが精神保健分野であるだけに、より明瞭に説明されているが、ホームレスや若者の失業問題、児童虐待など共通の社会問題に対して、効果あるプログラムの導入のもつ意味は大きいと言えよう。その上で、日本ではなぜ効果的プログラムの導入がすすまないかという問題が浮上し、ソーシャルワーカー教育によって、これを打破したいという本書の方向が見えてくる(第4章)。本書自体、そのような効果的プログラム開発や評価ができる専門職を作るための教科書という位置づけがある。
しかし、マクロ・ソーシャルワークが、より上級な支援スキルというだけでなく、制度要求まで展望すると考えると、いくつかの疑問もある。第1に、ニーズや課題の特定や分類がややステレオタイプであり、またもし関係者間でそのゴールにズレがあっても、ワークショップなどによって共通ゴールが導き出されるとするなど、少々楽観的な印象がある。
住民参加型ワークショップで名高く、成功例として著名な改良住宅の再生事業がある。評者自身、この事業に関わったことがあるが、ワークショップで共通ゴールが導かれたわけではない。このプロジェクトを率いた神戸大学・平山洋介氏は、ワークショップとは住民・行政・専門家がそれぞれの主張する「声」を複数浮かび上がらせる空間であり、むしろ合意の不可能性を顕わにする、と述べている。目標像はワークショップによって多元化するのであって、簡単に収斂しない。その中で何らかの決定に向かわざるを得ない葛藤が生まれる。また、ワークショップに参加していない住民の「声」は聴き取れないという問題もある。ある世帯から、その父親の意見とみられる特異な間取りプランが出された。行政も専門家も意見の一致ができないし、母親の「声」は聴かれない。だが、原案での決定となったという。苦悩の決定である。
第2に、これは、より本質的な問題であるが、効果的なプログラム導入の前提として、財源や政治的判断が必要とされるのが普通である。これらは、「効果がある」というエビデンスだけで獲得できるとは限らない。一定の政治環境が与えられると、エビデンスより政策判断が先行することは少なくない。社会保障財源の削減などが至上命令となると、効果は財源削減に対して持つ効果に転換する。退院援助、在宅介護などの選択は、ニーズに沿うだけでなく、政策によって目標値が決められてしまう。ホームレス支援のゴールは、ホームレスの人びとの住居の安定や社会参入であるばかりでなく、むしろ町の「浄化」にあるというのが現実であろう。
この第2の点から、本書の言うマクロ・ソーシャルワークの支援環境整備が「プログラム開発」であって、「ポリシーの改革」ではないことに気が付かされる。つまり、プログラムは、一定のポリシーを逸脱しない範囲で、より効果的なスキルとして提示されている。すると、ソーシャルワークのマクロアプローチとソーシャルポリシーには、基本的な断絶があり、マクロ・ソーシャルワークが制度変革を展望するのは困難だということになってしまう。
第3に、エビデンス自体の「科学性」も絶対的とは言えない。特に重い課題を複数抱えた社会福祉の対象への働きかけの効果は、時間をかけないと分からないこともある。今述べたポリシーのレベルでは、政策判断が先で、あとから適当な数字を探し出してくる、というようなことは普通に行われている。政策論研究を主戦場としている評者にとっても、科学的エビデンスで乗り越えたい場面は沢山あるが、むしろ多くはそうはならないのである。なぜそうならないのか、はエビデンスというよりも、社会構造と権力関係への着目が不可欠なのではなかろうか。
第4に、そうだとすると、国民への説明や社会的合意はそう簡単ではないだろう。ただし、一つの可能性として、マクロ・ソーシャルワークに通じた専門職能団体が、政治プロセスの中で力を持った勢力として成長し、そこから変革の途が拓かれるかもしれない。そのためにも、まずは多様なEBPの活用と専門職能の成長が必要だという点には同感である。