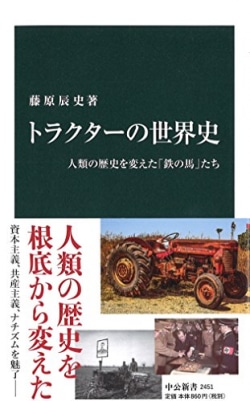『トラクターの世界史』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
近代文明のシンボル その功と罪
[レビュアー] 稲垣真澄(評論家)
二〇世紀は「モータリゼイションの時代」といわれるが、モータリゼイションはいわゆる自動車以外の分野でも顕著に進んだ。トラクターの登場は、人力・畜力に依存する農業風景を一変させた。二〇世紀以降の人口爆発も、結局はそれを支える食糧増産があったからで、幾分かはトラクターに負うはずだ。もちろん負の側面も少なくない。本書はトラクターから見たもう一つのモータリゼイション史であり、文明批評でもある。
トラクターとはもともと「引くもの」「牽引車」の意味で、土壌を耕起する犂(すき)や、種子の植付け、刈取り、脱穀、選別用の各種作業機、あるいはそれらを同時にこなすコンバインなどを引く農業用動力車のこと。内燃機関を用いた最初のトラクターは一八九二年、ジョン・フローリッチというアメリカ人発明家によって開発されたといわれる。
じつは小麦の生産では、六十%のエネルギーが耕起・耕耘(こううん)に費やされるという。刈取り、脱穀、選別などの作業は併せて四十%にすぎない。しかもそれらの分野では、三十八頭の馬が牽引するコンバインまで知られるくらいで、ある程度合理化も進んでいた。その点、機械が大地を耕す自動耕耘こそ農民たちの見果てぬ夢で、フローリッチの内燃トラクターは機動性、操作性からその夢の実現をリアルに予感させた。以来、アメリカは世界のトラクター先進国となってゆく。
しかしトラクターの導入は無条件に善かといえば、そうでもない。牧草を食べないトラクターも、石油は不可欠。病気はしないが、故障はする。排便はしない(堆肥が作れない)。つまり購入費・修繕費に肥料代・石油代までかさんで、銀行の農家支配と、化学肥料による農地劣化は一層すすむ。農民たちのトラクターへの激しい怒りは、スタインベック『怒りのぶどう』の描く通りである。
面白いのは、そんなトラクターに着目したのが、共産主義のソ連とナチズムのドイツ。ともに全体主義の国々だ。おそらくは大規模農地で効果を発揮するというトラクターの集約性が、全体主義の精神にマッチすると思われたからだろう。ソ連では修理場をMTS(機械トラクターステーション)と称し、人民管理の組織へと換骨奪胎したが失敗した。
戦前、トラクター後進国だった日本は、戦後、歩行型トラクター(耕耘機)から出直し、今では農地面積あたりの乗用型トラクター台数も、二位オーストリアを抜き圧倒的に世界一だそうだ(総台数は三位)。それにしても気になるのは、第一次大戦時、トラクターから戦車が作られたように、軍需品との近さである。トラクターに限らず、化学肥料と火薬、農薬と毒ガスなど同根のものが少なくない。その点に関しては、同時期に刊行された『戦争と農業』が参考になる。