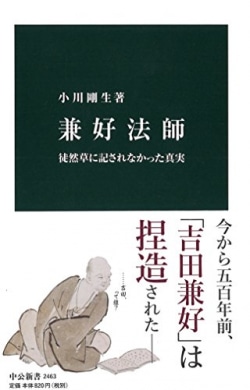『兼好法師』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
何百年と伝えられてきた人物像への疑問
[レビュアー] 平山周吉(雑文家)
たった一人の人間の足跡を掴まえるために、中世の歴史と文学に関する著者の膨大な知見が総動員されている。その結果、何百年とまことしやかに伝えられてきた人物像に疑問符が突きつけられる。徐々に、忽然と、その風貌が歴史の向こうからあぶり出される。その推理の全体は、壮観と言っていいほどである。
小川剛生の『兼好法師』は、学問の底力を新書本一冊に詰め込んだ驚きの本だった。誰もが教科書で習ったことのある「徒然草」の著者が、面目一新されて提示されるのだ。そもそもの発端は、系図を偽造した吉田兼倶(かねとも)なる人物の奸計にあった。吉田流神道の当主である兼倶は「徒然草」で有名になった兼好法師を我が家の家系図に書き込むのだ。「吉田兼好」なる人物の登場である。兼倶は文書偽造の常習犯だった。兼好の父と兄もでっち上げられた。藤原定家も鴨長明も日蓮も吉田流の門弟だったと主張したというから、かなりの強心臓である。
「世に語り伝ふること、まことはあいなきにや、多くは皆虚言(そらごと)なり」とは「徒然草」七十三段冒頭の一文である。小川剛生訳では、「世間に語り伝えられていることには、事実ばかりでは面白みが欠けるせいか、多くはみな作り話である」となる(角川ソフィア文庫版『徒然草』)。この一文を兼倶は知っていたかどうか。とんだ皮肉である。
本書を読むと、「虚言」を源流とする出自や経歴よりも、史実を基にした、同時代を呼吸する兼好伝の方がはるかにスリリングであり、精彩に富んでいることがわかる。通説では、兼好は六位蔵人として朝廷に仕え、後二条天皇の急逝により、将来を断念して遁世した隠者である。著者の小川がまず疑問にするのは、天皇身辺に奉仕しているなら当時の公家日記に頻繁に登場するはずなのに、まったく出てこないことであった。それどころか、その時期、京を離れ、鎌倉に長期滞在していた。あり得ない行動である。
兼好と鎌倉との関係は従来から言われていたが、著者は「金沢文庫古文書」の中に、兼好の若き日の足跡を発見する。金沢文庫古文書とは「中世人の肉声をよく伝えている点でも唯一無二といえる史料群」で、幸運な偶然で残った書簡類に、あろうことか、兼好と兼好の父母や姉の情報や筆跡が含まれていたのだ。ありえない奇跡が手がかりを与えてくれた。紙背文書といわれる、いわば反古(ほご)紙の記述を解読していく過程そのものが興味深いのだが、それは本書を読むしかない。
点と点を慎重に繋ぎながら、著者は若き日の兼好とその環境を復元する。兼好は伊勢国出身で金沢流北条氏に仕え、京都から下ってきた一族であった。「想像を逞しくすれば、幼いうち父を失い、母に連れられて京都に上り、そこで成長したが、ゆかりの関東に下向し、姉の庇護の下、無為の生活を送っていた若者の姿が思い浮かぶ。もちろん十分な経済的余裕が前提である」。
金沢文庫古文書が与える情報はまだいくつもある。兼好の主人であった金沢貞顕(六波羅探題)は書状で兼好を呼び捨てにし、官位も尸(かばね)も付していない。「当時貞顕の官位は越後守正五位下である。やはり兼好はそれより下、すなわち六位かそれ以下の侍品(さむらいほん)であったとするほかない。通説では当時の兼好は蔵人の任期を終え、五位の左兵衛佐であったとされる。それは決して貞顕が呼び捨てにできる相手ではない」。他の史料も援用すると、兼好は「出家まで正式な官途に就かなかった可能性が高い」。
鎌倉から京都に戻った兼好は三十歳近くで出家する。「市中の隠」ではあるが、「後世の人間が憧れた隠者」とは異なり、「侍入道(さむらいにゅうどう)」とでもいうべき存在だった。「公家・武家・寺院にわたり幅広い知己を有して活動するもので、経済的な基盤にも支えられ、清貧とはほど遠い生活」を送った。不動産を複数所有していたことは契約書が残っていることで間違いない。不動産取引はプロ並みだった。
鎌倉幕府の滅亡から南北朝時代へと、兼好の生きた時代は乱世だった。その乱世を逞しく生きた「隠者」が兼好だった。同時代には「徒然草」は知られず、兼好は歌人としてその名を知られていた。著者の本来の専門は中世和歌のようなので、歌人兼好の側面から考察された新事実も多い。「徒然草では醒めた、時にシニカルな批評さえよくする兼好であるが、歌道ではそのような素振りはなく」、師には恭順をきわめた。勅撰集に連続入集することは歌人の名誉であったが、兼好は存命中に四代連続入集を果たせなかった。「和歌の浦に三代(みよ)の跡ある浜千鳥なほ数そへぬ音こそなかるれ」という歌を晩年に詠んでいる。「あれほど「死」についても立派な省察をしていた人が、最後につまらない妄執にとらわれたものだと失望すべきか、それともこれが人生の真実として沈思すべきか」と著者は問うている。
「徒然草」で思い出すのは、小林秀雄である。小林は『無常といふ事』で、兼好を「文章の達人」「空前の批評家の魂」と評した。私は学生時代、一回だけ小林の講演を聞く僥倖に恵まれた。その時、小林は「徒然草」百五十五段の「死は前よりしも来らず。かねて後(うしろ)に迫れり。(略)沖の干潟遥かなれども、磯より潮の満つるが如し」を挙げた。老境の小林のぶっきらぼうで、融通無碍な語り口を久しぶりに思い出した。「省察」も「妄執」もともに兼好法師その人であろう。
未知の人物がたくさん登場する本なのだが、巻末の索引がよく出来ていて、理解を助けてくれる。このことも特筆しておきたい。