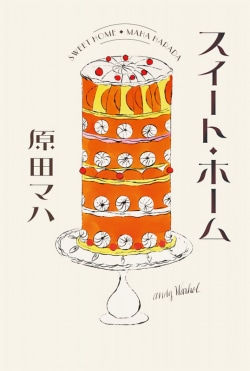『スイート・ホーム』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
愛のある場所/原田マハ『スイート・ホーム』書評:瀧晴巳(フリーライター)
[レビュアー] 瀧晴巳(フリーライター)
家族というのは不思議なものだ。
いつの間にか、思いがけないところが似ていたりする。
表題作「スイート・ホーム」の主人公・香田陽皆(こうだひな)の場合、それはお見送りのスタイルだった。五百円のキャンドルホルダーを買ってくれたお客さんに対しても、わざわざ店頭まで出ていき、見えなくなるまでお見送りをする。ていねいすぎるほどのそれはマドレーヌをひとつ買ってくれた常連さんを、わざわざ厨房から出てきて、店の前でお見送りをするパティシエの父親のスタイルそのままだった。
おそらく真似しようとか見習おうとか頭で考えて、そうしているわけではない。家族が当たり前にしていることを見るともなしに見ているうちに、呼吸するみたいに身についていたちょっとした仕草やたたずまいがある。
個性と呼ぶにはあまりにささやかで、自然とやっていることだから、本人はとりたてて意識もせず、気づかずにいること。でも迷った時、答えが見つからない時、その人を底から支えてくれるのは、もしかしたらそういう日々のなにげない習慣のようなものではないか。
28歳の陽皆は、進学にしても、就職にしても、無難な選択ばかりしてきた気がしている。OL生活になじめず、4年で退職したものの、次に何をしたらいいのか考えてもなかなか結論が出せなかった。妹の晴日(はるひ)にまで「お姉ちゃんは優柔不断やねん。自分ってもんがないし。そやからモテへんのよ」と言われる始末だ。
自分がない――。
飛び抜けた個性やこれと言った特技がないことが目下の悩みであり、それこそ口にしたら「なあんだ。そんなこと」と鼻で笑われてしまいそうだ。悩みに悩んだ彼女が梅田の地下街にある雑貨店の契約社員になったのは、ていねいに接客する両親の背中を見てきたからだった。そして彼女に恋の扉を開いてくれるのも、急ごしらえの個性なんかではなく、歳月に育まれてきたささやかな習慣なのである。
父親は、宝塚のホテルでパティシエとして長らく働いた後、自宅を改築してケーキ店「スイート・ホーム」を開いた。自称「スイート・ホームの看板娘」の母親は、そんな父親を手伝って店を切り盛りしている。家族のシンボルツリーは金木犀。毎年秋になると、咲きこぼれる花の下で家族写真を撮る。繰り返す歳月の記憶は、絵に描いたような幸せの風景そのものだ。
緑ゆたかな郊外型のニュータウンを舞台にしたこの連作短編集は、原田マハの近年のアート小説を読んできた読者にとっては、いささかテイストの異なる作品であるに違いない。そもそも宝塚という街自体が、どこか懐かしい桃源郷のような雰囲気を持っている。宝塚歌劇のファンなら劇場へと続く花の道を思い浮かべるかもしれないし、食いしん坊なら宝塚ホテルのクラシックなケーキを連想するかもしれない。岡山で育ち、兵庫県西宮市にある大学に進学した著者にとっても、宝塚は憧れの街であったらしい。学生時代を阪神間で送った著者には、これまで神戸を舞台にした恋愛小説『おいしい水』や阪神・淡路大震災を描いた『翔ぶ少女』などの著書がある。そして『スイート・ホーム』では、愚直なまでの誠実さが親から子に受け継がれ、報われる瞬間が、てらいなく、真っ直ぐに描かれている。家族の幸福をシンプルに思い描くことが困難な時代に、著者がひとつの願いごととして描いたような本作は、ケーキさながら、どこまでも甘くやさしい。
「あしたのレシピ」で母親と同じ料理研究家の道を選んだ未来(みき)も、レシピで悩んだ時は、母に倣って「初心に戻る」ことにしている。
あしたのレシピに行き詰まったら、今は亡きお父さんのことを思い出そう。お父さんやったら、何が食べたいかな――そう考えること。ままならない片思いに泣きたい日も、それが前を向く術になる。
料理研究家として知名度のある母親のレシピには、決して華々しいメニューはないし、忙しい主婦のための「手抜き料理」なるものも教えない。ていねいに下ごしらえをし、だしを取り、ひたすらやさしい味に仕上げる。
香田家のケーキと同じ。マーケティングとも流行とも無縁の美味しさは、いつの頃からか絶滅危惧種の贅沢品になってしまった。現実は甘くない、こんなにうまくいくはずがない。ついそう言いたくなるけれど、長年連れ添った伴侶を亡くしたいっこおばちゃんが香田家にやってくる「希望のギフト」を読みながら「待てよ」と思う。
子どもの頃、当たり前にあった家族の風景は、今はもうない。時が経ち、失われたあれは一体何だったんだろう。そうなって初めて気づく。〈家族〉という共同体自体が、いつかは消えてしまう夢そのものなのだと。そして、人はまた新しい家族をつくる。それが簡単じゃないことも、大人になれば、よくわかってくる。繰り返す営みの、なんてはかなく、美しいことか。
誰かとめぐりあい、歳月を重ねていこうと決めること、それは誰にでも起こりえる「奇跡」なのだ。だから人は「もしかしたら」と願わずにいられない。
赤い屋根、クリーム色の壁、ただよってくる甘い香り。私が欲しい幸福はここまで完璧じゃなくていいけれど、人は誰も帰りたい場所を探しながら歩いていくから。どこまでも甘くやさしい『スイート・ホーム』という小説は、誰かと家族になろうと夢見る瞬間とたぶん地続きなのだ。