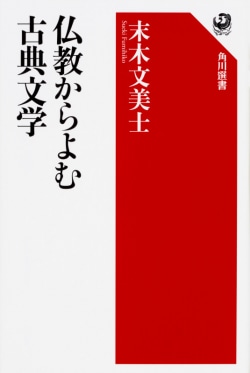『仏教からよむ古典文学』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
悟りを求める心、愛を求める心――【書評】『仏教からよむ古典文学』酒井順子
[レビュアー] 酒井順子(エッセイスト)
『源氏物語』に登場する女君達はそれぞれ、今を生きる私達をして「わかるわかる、こういう人っているよね」と思わせるキャラクターです。しかし一つよくわからないのは、彼女達にとっての出家とはどのような行為だったのか、ということ。
彼女達は皆、何かつらい事態に遭うと「出家したい」と願い、実際にしたりしなかったりします。たとえば女三宮は、源氏からはさほど愛されず、思わぬ不貞事件を起こしてしまうものの、素早く出家することによって、一定の区切りをつけました。対して紫の上は、生涯にわたり源氏からの寵愛を受けつつも、それゆえに悩みも深い。何度も出家を望むのだけれど、源氏は許してくれません。
六条御息所が嫉妬のあまり生霊と化すのも、朧月夜がついつい源氏と関係を持ち続ける気持ちも、私達はリアルな感覚として「わかる」のです。しかしこと出家に関しては、残念なことに私は瀬戸内寂聴さんではないので、「果たしてあの時代に生きていたら、私は出家をしたくなったのか。そして決行できたのか」と考えても、わからない。仏教が身近にあった時代との断絶が、そこにはあります。
『仏教からよむ古典文学』を読んで、私は『源氏物語』を読む時に欠けていた「仏教」というピースが、ぱちりとはまり、新たな絵が見えたような感覚を覚えました。日本における仏教受容の歴史をたどれば、「現世利益的な密教儀礼だけでなく、仏教は個人の人生観に関わる進行の問題として受け入れられるようになっていた」のが、源氏物語が書かれた時代。心身の不調の時も、人生がうまくいかない時も、頼りにされたのは、仏教。出家という手段に手を伸ばす女君達の感覚が、少し身近なものに感じられます。
出家の問題のみならず、『源氏物語』のあちこちには、仏教的色合いが顔を出しています。男女間の色恋問題をときほぐすことのみが、この物語を読む醍醐味ではない。この時代、色恋の世界のすぐ隣には、仏法が支配する死の世界が存在していたのであり、その闇の暗さに目を慣らすことによって、「光」はいっそう眩しく感じられるのです。
死の色合いがさらに濃くなる『平家物語』の世界へ進むと、仏教の存在感はますます強くなります。この時代になると、仏教のあり方はまた変化しているのであり、平家滅亡までの「諸行無常」を感じさせる出来事の数々は、うっとり感と共に読者に読まれるもの。
しかし諸行無常をそのまま受け入れて生きていくという感覚は、本来の仏教とは異なる「きわめて日本的に変容した仏教の発想」なのだそう。そしてそれが、「中世文学の大きな特徴となっていく」……。
時代につれて変化する仏教を、日本人はどう文学の中に受け入れてきたのか。物語以外にも、本書では能や随筆など、幅広い作品が取り上げられます。女性による作品も多く見られ、仏教は『源氏物語』の時代以来、男性だけのものではなかったことがわかるのでした。
「源氏物語と仏教」から始まる本書の最後の章は、「愛と修道 漱石のジェンダー戦略」。漱石は、「自分の分にある丈の方針と心掛で道を修める」という決意を、ある手紙に記しているのだそう。そして漱石にとっての修道とは、小説を書くことそのものではなかったか、と本書には記されます。
明治の家父長的家族観の下、『行人』から『道草』にかけては、男から女へ向けて「所有」の関係性が提示され、対して『明暗』で女が男へ突きつけたものは「愛」。一連の小説を記すことによって、漱石は女という他者について、考え続けたのでしょう。
「はじめに」において著者は、「『源氏物語』と漱石の小説群は、お手本通りの悟り臭さを拒否して、男女の愛の問題に深入りするところで響き合っている」と記します。色恋の背景に存在する仏教を見つめてみれば、“悟り臭さ”とは案外、エロティックなものなのかもしれないと思えてくるのでした。
◇角川選書