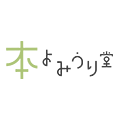かけがえのないふつうの話
[レビュアー] 星野博美(作家・写真家)
「イスラーム」という言葉が新聞やネットの国際面に頻繁に登場することは、国際情勢に特別な関心がない人にも同意していただけるだろう。いまや、イスラームに対する理解なくして世界は理解できない、と言っても過言ではないほどだ。
若い世代は、シャルリ・エブド事件やパリの同時多発テロ、あるいはIS(イスラーム国)による残虐な処刑映像などで関心を抱いた人が多いのではないだろうか。私を含む、それより上の世代になると、やはり二〇〇一年にアメリカを襲った同時多発テロ、いわゆる9・11で関心を持ち始めた人が多いのではないかと想像する。
きっかけはテロでも、何でもかまわない。関心を抱くことは、異文化を理解するための最初の一歩になる。しかしそれが偏見や極端な先入観に基づいた情報に依拠したままだと、理解につながるどころか、著しい妨げとなる。
私たちはどれくらい、イスラームと、その宗教を実践する人々のことを知っているだろう? ISにアルカーイダ、テロリスト、ジハード、ラマダン、エルサレム問題、豚肉を食べない、酒を飲まない、一夫多妻制、ヒジャブ、厳しい戒律、砂漠……。全世界に一六億人以上のムスリムがいて、国も地域も民族も多種多様であるにもかかわらず、相変わらずステレオタイプのイスラーム、そしてムスリム像からなかなか抜け出すことができない。イスラームは中東の砂漠だけで信仰されているわけではないし、ジャングルに囲まれた高温多湿な地域にも信徒はたくさんいる。ましてや、ムスリム=アラブ人ではない。たとえばそれがキリスト教なら、様々な地域に異なる宗派があり、厳格な信徒もゆるい信徒もいることがなんとなく想像できるのに(その想像が必ずしも合っているとは言わないが)、ことイスラームに対しては、その想像力がはたらかなくなってしまう。
なぜか。物理的に遠いからではない。地理としてはむしろ、キリスト教のほうが遠いとも言えるだろう。崇拝対象としての欧米志向から、いまだに抜けきれていないからだと、私は考えている。先入観に基づいたあふれるほどの情報が、想像力を阻害する。
個人的なことを思い返せば、私が初めてムスリムの人々と接したのは、大学生だった一九八七年(もう三〇年以上も前だ!)に中国の新疆(しんきょう)ウイグル自治区を旅行した時だった。特にイスラームに興味があったわけではない。ただただ、シルクロードの風景を見たかった。列車が西へ西へと向かうたび、人々が私たちとよく似た漢族の顔から、肌が白くバタ臭い顔に変わっていき、市場に並ぶ食べ物は、漢族の大好きな豚肉から、スパイスの効いた羊肉へと変わっていった。ウイグル族だけではない。漢族と見分けがつかない回族(かいぞく)(ムスリム民族集団)もたくさんおり、路地の風景に清真寺(モスク)が溶けこんでいた。いまほど国際色豊かではなかった時代の日本から来た私には、グラデーションを描いて民族や宗教が変わっていくことが、衝撃的かつ、とてつもなく好ましいものに思えた。
いま思えば、隣国・中国にこれほど多様な民族と宗教が存在すると若いうちに知ったことは、「イスラームは一枚岩ではない」という、その後の自分の核になったように思う。そのウイグルのムスリムが、いまでは苛酷な弾圧を受けていることが大変辛い。
前置きが大変長くなった。本書が依拠する統計によると、日本に暮らすムスリム人口は一〇万人以上にのぼるという。出身国別に見ると、最多がインドネシアで、パキスタン、バングラデシュ、マレーシア、イラン、トルコと続く。
本書は、谷根千(谷中・根津・千駄木)の地域雑誌を通じて、そこに暮らす人の言葉から町の歴史を記録し続けてきた森まゆみさんが、「お隣り」に暮らすムスリムに会いに行った本である。この「お隣り」が重要なキーワードだ。彼らはニュースの国際面を賑わすテロリストでもなければ、高名な法学者でもない。まさにお隣りに暮らし、私たちの社会をほんの少し多様にしている、一〇万人のうちの一三人のムスリムである。
出会いのきっかけが素敵だ。二〇〇一年、パキスタンにいるアフガニスタン難民のために衣類を集めたことをきっかけに、森さんは豊島区の大塚モスクと縁ができた。そして二〇一一年の東日本大震災の際、彼らが仙台、南三陸、気仙沼、いわきへと迅速に動いて支援物資を届けたことを知り、この「自由で融通無碍(むげ)な考え方」はどこから来るのだろう、と関心を抱く。そこから、日本で暮らすムスリムを訪ねる旅が始まるまでに、そう時間はかからなかった。
森さんのスタンスは、谷根千の時と同じく、地域のお年寄りと話をするように、「ふつうに話を聞く」である。大上段にかまえない。知ったかぶりをしない。難しい話は本人の言葉で説明してもらう。自分が抱いていた先入観に誤りがあれば、素直にそれを認め、ただちに修正する。簡単そうでいて、そうたやすくはない。
「あなたはどこから来て、なぜ、ここにいるの?」
すべてはそこから始まる。
私たちが近所の人と話をする時、挨拶に続いていきなり宗教観や国際情勢、テロの話をしたりしないように、故郷の話や食べ物、日本に来て驚いたことなど、「ふつう」に話は進んでいく。
イスラーム地域研究者や戦場ジャーナリストなら、また違った話が聞けるだろう。そういう向きは、そういった報告を読めばいい。しかし森さんは、彼らにはけっして聞けないであろう話を聞く。対等な市井の人間同士の会話から、いつしか、等身大の姿が立ち上がる。
「お金持ちになるのはかまわない。ただ、それだけ責任は重くなりますね」
「ラマダンというのは生き方のトレーニングなのです。我慢することを覚える。(中略)1个月実践すれば影響が残ります。1年して影響が薄くなったころ、またラマダンがめぐってきます」
「みんなに関係させる、ということが大切だね」
「イスラーム教徒だからといって特別なことはないですよ。キリスト教でも仏教でも宗教のいうことはだいたい同じじゃないですか。悪いことはするな、嘘をつくな、人を助けろ」
読み進めるうち、お茶の間に座っておじいちゃんやおばあちゃんの話を聞いていた、遠い昔を思い出す。知らない世界からやって来た彼らは、自分たちには思いもよらない知恵を持っている。かけがえのない宝物のような物語が、不意に飛び出す。
「代々伝わる絨毯を広げると、この上で亡くなった祖父や、父が笑い、語り、食事をしていた、家族の風景が浮かびます。そしてぼくがいまその上にいるんだけど、ぼくが死んだら息子たちが絨毯を使い、またぼくのことを思い出してくれるでしょう。絨毯とはそういうものなのです」
空気の淀んだ東京の片隅でこの物語を読む私に、突き抜けるような青空が広がるイランの村で、カタカタと機織(はたお)り機を動かす女性たちのおしゃべりが聞こえてくるような気がした。
日常のなかでも旅はできる。まずは、できるところから始めたい。そんな、小さな勇気を分け与えてくれる本である。