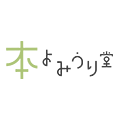“菊のハードル”を下げた証言の数々
[レビュアー] 平山周吉(雑文家)
近代皇室最大の功労者は誰か。その有力候補として名を挙げるとしたら、この方の名は逸せないのではなかろうか。大正天皇のお后として、お腹を痛めて四人の皇子を産んだ貞明皇后である。昭和天皇、秩父宮、高松宮、三笠宮、四人はみな順調に育っていった。
本書は、その「国母」貞明皇后の評伝である。皇室の伝記というと、どうしても尊敬の念が溢れかえってしまって、素顔が見えにくいという難点がつきものである。尊敬の念が自然であったとしても、不自然に過剰であればなおさら。そのいずれでもない本書は、稀有な皇室本である。ヘンな表現になるのを承知で言えば、書籍の中とはいえ、「基本的人権」のある「人間」として描かれているのだ。まるで選挙権を持ち、婚姻の自由もあったかの如くに。
その点は著者の川瀬弘至は自覚的であろう。貞明皇后は五摂家の名門九条家に生れたお姫様だが、すぐに東京郊外の高円寺の農家に里子に出され、元気に育った。色白でなければ美女とされない当時にあって、「九条の黒姫さま」と同級生からあだ名された少女だった。著者は書いている。
「華族女学校時代の節子(さだこ)姫について、戦前の文献は「御謙譲の徳に富ませたまひて、露ほども婦人の態度を失ひ玉はず、学友と御物語のときなども、温然として人々の話に御耳を傾むけさせられ……」などと紹介するが、戦後の文献からはむしろ、茶目っ気たっぷりの、はつらつとした様子がうかがえる」
その「戦後の文献」にしても一定の制約があり、皇室物の「定番」の範囲内にあった。著者が選んだ方法は、宮内庁の内部に眠っていた未公刊の資料をひも解くことだった。「膨大な量の閲覧請求申請」を提出して、「貞明皇后実録」、同「稿本」、同「編纂資料・関係者談話聴取」を入手し、ふんだんに引用するのである。「談話聴取」とは貞明皇后の同級生、お付の女官たち、おっかない教育係、宮中の要人たちなどさまざまな人々の思い出話を取材したもので、彼ら彼女らの「オーラル」から伝わってくる人間「貞明さま」が鮮やかなのだ。
本書はもともと産経新聞に連載されたものである。著者は社会部編集委員であり、産経の編集局が全面的にバックアップしたからこその成果であろう。著者が「あとがき」で、「“オール産経”で書き上げた連載」と述べた通りである。しかし、安易な小説仕立てにはせず、典拠史料を「註」として明記して、アカデミズムの検証にも耐えうるようになっている。『明治天皇紀』『大正天皇実録』『昭和天皇実録』といった宮内庁編纂の歴史書の欠点克服も目指されているのだ。それでいて読みやすいのが不思議である。
貞明皇后が亡くなったのは昭和二十六年(一九五一)の五月だった。「貞明皇后実録」の編纂は、その年から昭和三十四年(一九五九)にかけて行われた。天皇制の行方がどうなるか不明だった占領期をやっとおえ、独立を回復する頃から始まっている。昭和三十四年とは民間から正田美智子嬢が皇室入りをした年である。つまり「オーラル」の話を集めた時期は、皇室についてもっとも自由に、伸びやかに語る空気があった時代だったということになる。
貞明さまのお人柄もまた、その時代に語るにふさわしい伸びやかさを持っていたのだろう。「オーラル」取材に応じた関係者たちが、貞明さまならこんなエピソードをお話ししてもお許しになるでしょう、と“菊のハードル”を下げて胸襟を開いたのではないだろうか。親友の証言によれば、近視のために目つきがあまりよくなくて、意地悪だと誤解されたという。新婚早々、夫婦でテニスをするのが嬉しくて、御殿から外に出る時、階段を二、三段飛び降り、老女官に「ほう、叶ひませんな」と呆れられる。窮屈な宮中の暮しには泣き言も漏らしている。「結婚の翌日から泣いて暮した」、「九条家の娘として臣下に嫁いでゐたら私はもつと幸福だつたかも知れない」。
夫の大正天皇は大正七年に発病する。
気晴らしにと、側近たちによる園遊会や仮装行列を企画する。軍服に長い軍刀を引きずった仮装姿の侍従が怒った仕草をした。「まあ、あれは山県(有朋)のつもりよ。本人が見たらどんな顔をするかしら」と妻が笑って言うと、夫も声を立てて笑った。大正天皇は口やかましい「一介の武弁」の元老山県が苦手だった。
夫の晩年には献身的な介護で尽した。病室に付き添って、痰や咳の世話までする。ベッドの上り下りも手をとって助けた。侍従の万里小路(までのこうじ)元秀の証言によれば、「お小水の事までも皇后がお世話をなさいました」。看病も空しく崩御すると、貞明さまは一室に亡き夫の肖像画を飾り、「生ける人に仕へるが如く御奉仕」した。その部屋では、晩年に到るまで「寒中といへども敷物を御用ひなさいませんでした」。
ことさら「ちょっといい話」だけが集められているわけではない。「母子対立」という一章も設けられている。なぜか長男の昭和天皇とは意見を異にすることが多かったからだ。戦争の行く末については、支那事変の時から、勝てるとは考えていなかった、という証言が紹介されている。証言者は関屋貞三郎元宮内次官の夫人・関屋衣子である。湯浅倉平内大臣や宮様方にそう話していたというのだ。
貞明さまの人物については、戦後に侍従長となった大金益次郎の人物評が全編を要約している。「卑近な言葉で甚だ相済まないが、一箇の親切な伯母さん」。