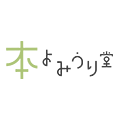【座談会】阿川佐和子×内藤啓子×矢代朝子――文士の子ども被害者の会 Season2〈後篇〉

まだ「小物」か!?

矢代静一氏(左)と阪田寛夫氏
矢代 昔はお正月に師匠筋とか親しい先輩のお宅へお年始に行ったじゃないですか。阿川先生は志賀直哉先生、阪田先生は庄野潤三先生、うちは文学座でしたから岩田豊雄(獅子文六)先生の系統ですよね。毎年のお年始に岩田先生のお家へ、わが家みんなで正装して行っていました。一月二日に乃木坂のお宅に伺って岩田先生の風貌を見ると、子ども心に「あ、これが文豪なのか」って思いましたね。子どもに「ああ、こんにちは」とかお愛想めいたことは一切おっしゃらないし、でも怖いというより立派って感じなの。あんな存在感がある大人ってもういないですよね。
阿川 啓ちゃんも庄野潤三先生のところにお年始に行った?
内藤 オジサンだけ行っていました。庄野家では毎年正月、百人一首のカルタ大会をやるんです。で、暮れの忙しい時、その練習に付き合わされた。
阿川 でも、お年始に行くのは自分だけなのね?
内藤 そうなのよ。なんで私たちが、父の庄野家での活躍のために犠牲にならなきゃいけないのって思っていました(会場笑)。
阿川 うちは家族全員で志賀家に伺ってまして、志賀先生は大きな居間の一番奥に仙人みたいな感じで鎮座されていました。怒られるとか怖いとかじゃないんだけど、とてもガキが近くに駆け寄って、「おじいちゃん!」みたいなこと言える雰囲気じゃなかった。
矢代 そうなんですよね、文豪の威厳ってすごかった。
阿川 高校か大学の頃だと思うんですけど、父に連れられて志賀家へお邪魔したんです。私が隅でちまーっと大人しく座っていると、退屈していると思ってくださったのか、志賀夫人が「ちょっと佐和子ちゃん、こちらにおいでなさいな」なんて、学習院言葉っていうのかな、山の手の上品な言葉遣いで仰って。正確には再現できないんですけど、「ウグイスを飼い始めたことよ」って、別のお部屋へ案内してくださって、「ごめんあそばせ」って入っていくと、もう三十代、四十代の実のお嬢様たちですよ、彼女たちがまた「あら、どうなさったの、お母ちゃま」って仰るの。
「佐和子ちゃんにウグイスを見せて差し上げようと思って」「あら、そう」って、お嬢様方が籠のウグイスに「チュルチュルチュル、鳴きなさい」って声をかけるんだけど、ウグイスはちっとも鳴かなかったの。そしたら志賀夫人が「ピーピーピー」っておっしゃったら、たちまち、ウグイスが「ピピピピピッ」て鳴いたんです。するとお嬢様方が「やっぱり、お母ちゃまの声はけがれてないことよ」と仰った。これが実の親子の会話かと、わが家とのあまりの違いに私は仰天して失神しそうになりました(会場笑)。
矢代 もはや文学ですね、それ。
阿川 まあ、うちとはお家柄が違い過ぎるんだけどね。だけど、もう驚いちゃって、家に帰ってから、心を入れ替えようと思って、「おい、酒」って言う父に、「そんなに召し上がるとお体に障ることよ」「うるせえ、バカやろう!」(会場笑)。「では、どんどんお飲みになることよ」「俺を殺す気か!」「そんなことないことよ」「いい加減にしろ! うちは山口のどん百姓の出だ!」って(会場笑)。
矢代 だから、私すごい生意気なんですけど、子どもの時に岩田先生とか、一時代前の文豪を生で見ちゃったから、大人になってから遠藤先生とか北先生とか中村真一郎先生とかとお会いしても、不遜にも「まだ小物だな」みたいに思っちゃって(会場笑)。
阿川 まだまだ文豪じゃないなって。
矢代 だって志賀先生を見てきたらさ、そう感じない?
阿川 それはそう、志賀先生は別格ですよ。私も家では「志賀おじいちゃん」と呼んでいたけれども、直接話しかけることはとてもできなかった。でもね、父が若い頃、志賀家にお邪魔して、お暇する時に、居間で「先生、失礼します」って言って、玄関まで奥様がお見送り下さった。父が靴も履いて、いざお宅を出ようという時、奥様が「阿川さん、うちの娘も年頃なんで、一つご縁があったらどなたかよろしくご紹介くださいね」みたいなことを仰ったらしいの。父が「はあ」って返事をしたら、志賀先生が急に奥から出ていらして、「あのね、君みたいじゃないのがいいんだ」(会場笑)。だから、けっこう遊び心はおありになったと思うの。
矢代 文豪の一言ひと言は素晴らしいし、面白いですよ。岩田先生もそうでした。会話も生活も文学になってますよね、文豪は。
父親たちのタカラヅカ
阿川 最初に訊くべきことだったけど、朝子さんは啓ちゃんとはちっちゃい頃から、軽井沢とかで会ってたの?
内藤 今日、初対面なの。うち、軽井沢に別荘ないし(会場笑)。
矢代 ただ、大浦みずきさん――なつめさんのことは、私の妹といとこも宝塚だったこともあって存じ上げています。
阿川 朝子さんの妹さんは毬谷友子さんですね。
矢代 大浦みずきさんの同期生の遥くららさんって娘役さん、父が名前をつけたものですから、二人の初舞台の『虞美人』を宝塚劇場へ見に行った時、大変な騒ぎだったんですよ。遠藤先生が「阪田の娘の初舞台や! 矢代が名付け親になった子も初舞台や!」って言って、遠藤先生が音頭を取ってくれて、父、阪田さん、三浦朱門さん、総勢五、六人のおじさんがコネを使いまくって、前から四列目くらいのVIP席にずらーっと並んだんです。
阿川 基本的に宝塚の客席は女性だらけ、その中に――。
矢代 ものすごく目立ってましたね。でも、まだなつめさんも遥くららさんも初舞台だから……。
内藤 その他大勢でね。
矢代 『虞美人』は項羽と劉邦の物語なので、若い子たちはみんな兵隊の役なんです。戦いの場面で、あっちへワーッと行ったり、こっちへワーッて来たりするたびに阪田先生は「うちの娘は右から四番目です!」とか言うわけですよ。そうすると、遠藤さんが父に伝言したり、あるいは父が「遥くららは今、左から二番目!」。相当うるさかったらしくて、後で主役の鳳蘭さんに「先生たち、目立ち過ぎやわ」って言われた(会場笑)。父は前の席で見て、舞台の上の生徒さんたちに「あ、矢代先生がいる」ってわかってもらうのが好きだったんですよ。目が合ったりするのがうれしい。でも阪田先生は、後ろの方でこっそり見るタイプでしたね。
内藤 そう、恥ずかしいのね。妹に言わせると、矢代先生みたいに堂々と見て下さった方がいいらしいです。父みたいに照れて下向いて見ていると、照れがうつるからイヤなんですって。
阿川 矢代さんは銀座生まれで、小さい頃から宝塚がお好きだったから、お嬢様の一人が宝塚に入ったのは嬉しかったでしょうね。
矢代 いや、本当は、父は娘には普通に女子校を卒業して、普通にお嫁さんになってほしいって思っていたんです。芸能界とか演劇とかに進んでもらいたいとはまったく思っていなかった。むしろ、女優になりたいとか絶対にダメだっていう家でした。
阿川 でも、お母様も女優さんでしたよね。
矢代 だから両親とも、こういう世界は厳しいことを知っているから、「絶対ダメだ」と言い続けていたんです。むしろ、父が娘に宝塚を見せていたのは、当時のことでアングラ演劇とか盛んだったから、ああいうのを見せるよりは、自分も好きだし、親子で宝塚見に行ったりする方が、いわゆるマトモに育つだろうと思っていたみたいなんです。
阿川 朝子さんは宝塚に入ろうとは思わなかったんですか。
矢代 入りたいなと思ったこともありましたけど、ほら、長女ってそういうところをガマンするわけですよ。うちは絶対に芸能界はダメなんだから、希望を持っちゃダメ、迷惑かけるから、と自制するわけです。
内藤 ああ、長女の発想ですね。わかります。
矢代 次女にはそういう発想がないですもんね。
阿川 お二人は妹が宝塚という共通点があるんですよね。啓ちゃんも宝塚好きだったの?
内藤 いや、好きじゃなかった(会場笑)。一緒に見に行っていた妹は好きになったんですけどね。父は読売新聞に宝塚の劇評を書いていたんで、いいのがあると、妹と一緒に見てこいって勧めてくれて。
矢代 父がよく、「阪田の批評は甘いんだ」って言っていました。「優しいんだよ」って。
内藤 妹が宝塚受験の時、「父親が読売新聞に劇評を書いてます」と言ったら、面接官の先生に「ああ、あの大甘の評の」って大笑いされた(会場笑)。宝塚の大ファンだから、褒めるしかないの。
矢代 新劇の批評って厳しいから、父は劇評で苦労してて、「この一行がなければ客が入るのに」「こいつ、わかってない」みたいな会話をうちでしていたわけです。そこへいくと阪田さんの宝塚評は、本当にいいところをパッと並べ立てて、それこそ「グッジョブ!」みたいに褒めてくれる批評でした。
阿川 それで、啓ちゃんはそんなに興味持たなかったけど、なっちゅんは宝塚好きになったのね。
内藤 そう、彼女はハマっちゃったの。なっちゅんは十歳くらいからクラシック・バレエをやってたんだけど、あの世界はやっぱり三歳の頃から始めた人にはどうやってもかなわないのね。だけど、「宝塚なら同じスタートラインから立てるから」とか言って、親をうまいことごまかして。それでも、「あんな厳しいところで、甘ったれの泣き虫がやっていけるのか」って両親は心配していましたけどね。
阿川 毬谷友子さんの場合は?
矢代 妹は音楽的才能もあったし、とにかく「絶対、入る!」って宣言したら、次女は長女と違って、何を言われても聞かないですから。「入れないなら、もう死ぬから!」みたいな感じで。それで、うちの両親は根負けして、しょうがないなと。
すると長女としては、「え? この家さ、そういうのダメなんじゃないの? いいわけ?」ってなったんですよ(会場笑)。でも、やっぱり長女だから、「ああ、妹が芸能の世界へ行ったら、私はますます真面目にちゃんと普通に勉強しなきゃいけないな」って思っちゃうんですよねえ。
阿川 それも妹さんと年が離れていればいざ知らず……。
矢代 私が四月生まれで、妹が翌年の三月生まれで、同じ学年なんですよ。しかも深く考えずに同じ学校に通わせたものだから、同級生が戸惑ってた(会場笑)。
阿川 姉妹とはいえ同級生なのに、姉ちゃんは我慢し、妹のワガママは通用するという、この扱いはどう思ってたの?
矢代 これはねえ、話し出すと長いので話しませんが――。
阿川 私の胸で泣いていいよ(会場笑)。
矢代 要するに、同じ学年で姉のポジションをこの家で守るためには、ひたすら大人になるしかなかったんです。少なくとも妹よりガマンすることなんですね。
阿川 姉の威厳を保つために……。たくさんガマンしてきた?
矢代 うーん、多分そうだと思います。それで、私は普通に大学でも行こうかなと思っていたんですが、父が「おまえ、将来何になりたいんだ?」と訊くから、「私は大学へ行きたいけど、でも、たぶん大学を出ても、やりたい仕事は演劇とか芸術的なことだと思う」って答えたんです。私の子どもの頃から、矢代家の幸せな日って、父が原稿を脱稿した日と、舞台の初日が無事に開いた日で、それで回ってきた。そして、なぜ母があんなに父をサポートしたかといったら、結局、いい芝居を書かせるためじゃないですか。
でも、幸せな日の合間には、書けなくて周囲に当たりまくる日もあれば、才能に絶望して「もう死ぬ」みたいな日もあれば、ひどい劇評が出て、荒れる日もあるわけじゃないですか。そんな家で育ったから、頭で考えたというより、もう感覚的に、演劇的な方面で働きたいなって思うようになってたんですね。
阿川 朝子さんも文学座へ入って、女優になられた。
矢代 いま思うと、このままだと一生、自分は長女としてガマンして、父に振り回されて終わるような感じがしていたんでしょうね。でも私が演劇界に入ったら、父とは〈演劇人同士〉になれるんじゃないかっていうのはどこかにありました。「父の人生に巻き込まれたくない」って思ったことが高校生の頃にあったんですよ。
阿川 そうね、文士の家って、父を中心とする円があって、その円周を家族は回るだけ、という感じになるんですよね。
矢代 いくら父がいい作品を書くためにって言っても、母は奥さんだからいいけど、娘はそこまでやらなくていいじゃない、って思ったのね。