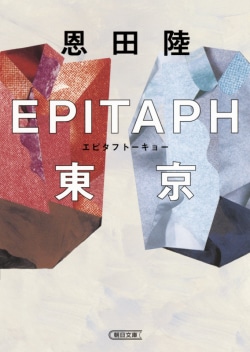書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ひとつの土地が抱き込む無数の「喪失」の物語
[レビュアー] 倉本さおり(書評家、ライター)
それが「名づけられた場所」である以上、土地には人びとの営みの記憶が確かに眠っている。けれど、人の生はあまりに短く、土地の姿も永遠には留まれない――そのことの意味を、露ほども損なうことなくまるごと小説の形へと変換させた傑作が梨木香歩の『海うそ』だ。
舞台は昭和初期、南九州の海に浮かぶ島のひとつ。古代から修験道のために開かれたその地に本土の若い学者が降り立ち、植生や人びとの暮らしぶりを綴りながら、点在する「歴史」の痕跡を辿っていく。
作中には生き物たちの気配が濃密にひしめいている。はちきれんばかりに生命力を横溢させている植物や動物の姿はもちろん、例えば、向こう岸の温泉に浸かるために連れ立ってたらい舟に乗り込む爺さんと婆さんの後ろ姿、ずっしりと密度のある握り飯、案内役の青年が焚いてくれた自家製の蚊よけの独特の香り……確かな手応えを伴う人びとの生活の細部が、島の全景をくっきりと立ち上らせていく。だからこそ、その場所でかつて喪われた者たちの痛みや悲しみがリアルに胸に迫る。ところが終章に至り、その鮮やかな地図は無惨な形で塗り替えられるのだ。
〈喪失とは、私のなかに降り積もる時間が、増えていくことなのだった〉――切り取った状態でも美しさが際立つその一文は、けれど本書を読了したときに初めて、全き質量でそこに現れる。その、かけがえのない瞬間をぜひ体感してほしい。
「喪失」を体験によって留める。恩田陸の『EPITAPH東京』(朝日文庫)は、徹底的に記号化された都市としての「東京」をモチーフに、その難題に挑んだ異色作だ。エピタフ(=墓碑銘)の名のとおり、作中で模索されるのは、破壊と再生を永遠に繰り返す大きな営みのなかで、ひっそりと完結していくひとりひとりの生に向けるべき言葉のありようであり、柴崎友香が『わたしがいなかった街で』(新潮文庫)等を通じて緻密に描き出してきた風景ひとつひとつとも重なる。すなわち、誰かが生きた場所を生きるということ――それは本来、途方もない輝きを含み込んだ営為なのだ。