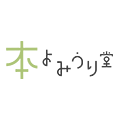記憶を失くしてまでも、誰かに恋い焦がれる想いを抱えることの哀しさ。
[レビュアー] 吉田伸子(書評家)
ある飲み会でのことだった。その場で友人Aが語った内容が、私が記憶しているのと違っていたので、そのことを告げた時のことだ。友人Aは、え、なに言ってるの? という感じで、自分の記憶が正しい、と。私は私で、自分の記憶を信じていたので、飲み会の後も、ずっと心の中に?マークが残っていた。それで、そのことについて考えていたのだが、! と閃いた。「私の記憶」と「彼女の記憶」は違うことに。
もちろん、雨が降っていた、とか当日の曜日とか、そういう「事実」が違ったりということはない。けれど、その時の口調とか態度とかは、受け取る側によって補正されることもあるのだ、と。似たようなことは、家族の間でも時々あって、そういう時は改めてこちらの意図を伝えるようにはしているのだけど、記憶というのは面白いなぁ、と思う。そして、大事だなぁ、とも。
だから、本書の冒頭で目覚めた主人公が、自分の記憶がすっぽりと失われていることに気付くシーンは、ぞわりと怖い。名前も、年齢も、職業も思い出せない、彼女は一体誰なのか。彼女がいるところはどこなのか。そして、何故、彼女はそこにいるのか。
この冒頭がスタートで、物語は少しずつ彼女=三笠南の全貌を明らかにしていくのだが、明らかになっていくことで、怖さが薄れていくどころか、ますます不穏さは増してくる。そこには、南の記憶が完璧に戻らず、欠片、欠片のはぎ合わせの状態のままである、ということが大きく関与している。このあたりの筆さばき、物語巧者の作者ならではだと思う。
意識が戻った南に会いに来たのは、夫のシンヤで、南は自宅の階段から落ちて気絶して、入院したのだということ。二人には子どもはいないこと。家は二世帯住宅になっていて、一階にはシンヤの母と姉が住み、二階に南とシンヤ、キッチンと風呂は一緒であること、等々、南は教えられるものの、全くイメージが浮かばない。何しろ、夫と名乗られたものの、名前さえ覚えていなかったのだ。記憶を失くした南にとって、シンヤは見ず知らずの他人と同じである。けれど、今の今は、目の前の「事実」を受け入れるしか、南にはできない。今は働いていないこと、小雪という名の仲の良い妹がいること、歳は二十六歳であること、結婚したのは八ヶ月前の四月だということ……。
検査の結果、脳に問題はなさそうだ、ということで退院することになった南だが、不安は抑えきれない。そんな南に会いに来た女性は、自分のことも忘れられていることに不快さを隠そうとはせず、言い放った。ちょうどよかったじゃない、と。「なにもかも忘れて、実家に帰っちゃえば?」彼女の物言いから、南はその女性がシンヤの姉のユミだと推測する。そして、全てを忘れてしまったように振る舞うのではなく、覚えていることと覚えていないことがあるように振る舞った方がいい、と考える。「わたしがときどき思い出したり、覚えていることがあるようなふりをしていれば、簡単に嘘はつけないだろう」
物語は、家に帰宅した南が、少しずつ記憶を蘇らせていく過程と、時折夢に見る男性――シンヤではないその男性に、夢の中の南は強く、強く恋い焦がれていた――の謎、を解き明かしていく。
ここから先は、何の情報も持たずに読んだ方が、より一層物語を楽しめると思うので触れないが、記憶を失くすことの根源的な怖さと同時に、記憶を失くしてまでも、誰かに恋い焦がれる想いを抱えることの哀しさが、きりきりと胸に迫ってくる。
それにしても、随所に光るのは、近藤さんの確かな描写力だ。南に戻ってくるのは、良い記憶ばかりではない。思い出さなければよかった、という記憶も、ある。そのあたりの南の複雑な想い、この先自分はどうなってしまうのだろう、とか、このままでいいのか、という不安までもがリアルに伝わって来て、読み手もまた、南と同じように気持ちが揺れてしまう。でも、だからこそ、南の選んだ答えが、切なく響く。辛い経験をきっかけにして、そこから先へと進んでいく彼女のこの先に、光があるように、と思わず願ってしまう。そこが本当に巧い。
作者の近藤さんは、一九九三年にデビューされた方なので、今年で作家生活二十五年。二〇〇八年に大藪春彦賞を受賞した『サクリファイス』では、自転車競技の世界を描いて、さらにファン層を広げた。歌舞伎を題材にした作品や、「清掃人探偵・キリコ」シリーズ、「ビストロ・パ・マル」シリーズ、等々、作風は多岐にわたるのだが、何と言っても、近藤さんの魅力は、登場人物の細やかな心理描写にある。本書は、そんな近藤さんの魅力をたっぷりと味わえる一冊でもある。冒頭からラストまで貫かれる緊迫感も、ご堪能あれ!