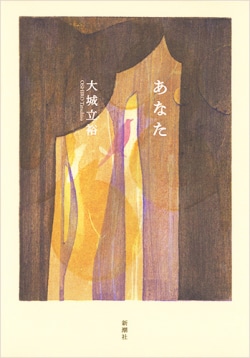『あなた』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
沖縄に生きる九十二歳の現在
[レビュアー] 川本三郎(評論家)
沖縄に生まれ育ち、この九月に九十三歳になる作家が、辿ってきた道を振返る。個人史であり、市井の人から見た沖縄現代史にもなっている。
長く一緒に暮し、先に逝った妻のこと。辺野古(へのこ)のこと。旧友たちのこと。女を作って家を出たことのある父のこと。田舎で過ごした子供時代のこと。そして次々に先立ってゆく友人たちのこと。
老いの身には、過去が鮮明になってくる。生きるとは思い出を重ねてゆくことだ。そこには悲しみがあり、悔いがあり、感謝がある。まして高齢になってからは、妻が、兄が、身近かの友人たちが亡くなってゆく。もう思い出のなかにしか生きていない。
表題作「あなた」は、六十年以上連れ添った亡き妻へ捧げられている。一九五四年に見合いで結婚した。戦後のまだ貧しい時代。公園らしい公園もなく、記念運動場と呼ばれたところで初夏の夜、「デート」をした。その時「あなた」が言った言葉を「私」はいまも憶えているという。「わたし、一所懸命やるわ」。戦後のつましい青春が泣かせる。
奥さんはいまふうにいえば専業主婦としてよく働いた。二人の子供(男の子)を育て、公務員と作家の二足わらじで苦労する夫を支えた。「あなた」は、その奥さんが亡くなったあとに書かれた思い出の記だが、ひとりよがりの感傷はない。淡々と事実だけを書き込んでゆく。それだけに、老いた夫婦に必ず訪れる別れ、どちらかが先に逝く終末の悲しみが迫ってくる。奥さんは脳梗塞で倒れ、やがて肺癌にもなる。その頃から、記憶も薄れてゆく。
だから、死に接して「私」は思う。「あらためて有難く思うのは、病気の発症から終末にいたるまで、あなたがまったく痛みを訴えることがなかったことだ。自分が肺癌の終末を看取ってもらっているのだということさえ、意識していないことを、私は感謝したい」
認知症が進んだためだろうか。奥さんの意識がないことを幸いにする。
感謝ではあるが、それがつらいことであるのは言うまでもない。死を見送る側には、自分だけが生き残っていることへの罪の意識がある。その生存罪責感が「あなた」の文章を引締めている。
収録作の「御嶽の少年」では昭和のはじめ、中城村という田舎の祖父母の家で過ごした夏休みの日々が牧歌的に描かれる。集落どうしの大綱引き、パッカラーという粘土の遊び(めんこを思わせる)、村にいたフラーと呼ばれる狂女、朝鮮飴売り。田舎の子供時代が豊かに思い出されてゆく。とりわけ、牝山羊を牡山羊のところに「つけ」に行く話はおおらかで面白い。大城立裕はよく沖縄の民俗を主題にした小説を書いたが、こういう野育ちの影響もあったかもしれない。
「拈華微笑(ねんげみしょう)」は父親の思い出。この父親は「私」も含め、三人の子供がいながら、遊女あがりの女と一緒になって家を出た。富裕な家の生まれだが、遊び好きで財産を蕩尽した。
どうしようもない父親だが、作者はそれなりに面白い人物だったと、愛情をこめて描いている。思い出のなかで父親は許されている。
老いてゆくと現在が遠ざかり、過去が近づいてくるという。しかし、「辺野古遠望」を読むと決してそうではない。大城立裕は、沖縄の厳しい現在、とりわけ辺野古基地建設問題に関心を持たざるを得ない。
大城立裕は、政治問題を生の言葉で小説のなかで語るのを避けてきた。日常を生きる生活者の落着いた言葉で小説を書いてきた。
しかし、「辺野古遠望」には、随所に熱い言葉が出てくる。沖縄の現状への怒り、憂い、不安が表現される。
「普天間あたりも基地を造る前はのどかな村落と田園であったが、あの辺野古に同じものを造るというのか」
「(以前は)アメリカだけを相手にした時代であったが、いまは日本政府をあらたな相手として加えなければならなくなった」
そして、老作家はこう呟かざるを得ない。
「私が年来考えてきたのが、生きているうちに沖縄の問題は片付くだろうか、ということである。思いついたときにはいくらか期待感もあったが、このごろではほとんど絶望している」
この原稿を書いているさなか、翁長(おなが)知事死去の報を聞いた。