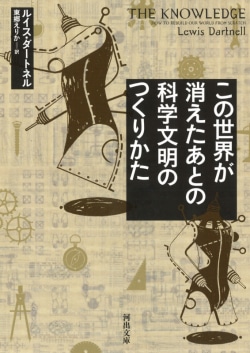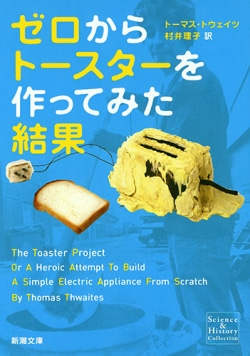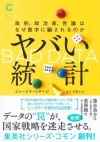『この世界が消えたあとの 科学文明のつくりかた』
- 著者
- ルイス・ダートネル [著]/東郷 えりか [訳]
- 出版社
- 河出書房新社
- ジャンル
- 自然科学/自然科学総記
- ISBN
- 9784309464800
- 発売日
- 2018/09/06
- 価格
- 1,078円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『ゼロからトースターを作ってみた結果』
- 著者
- トーマス・トウェイツ [著]/村井 理子 [訳]
- 出版社
- 新潮社
- ジャンル
- 文学/外国文学、その他
- ISBN
- 9784102200025
- 発売日
- 2015/09/29
- 価格
- 990円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
現代文明を再構築するためのスリリングな思考実験
[レビュアー] 倉本さおり(書評家、ライター)
文明崩壊後の無法地帯を魅力たっぷりに描き出すのはフィクションの得意技だろう。けれど世界的なベストセラーとなったルイス・ダートネル『この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた』(東郷えりか=訳)がスポットを当てるのは、崩れ落ちたものの中身のほう。居住空間、食料、医療、動力、コミュニケーション――それらを再建するために何が、どれだけ必要なのか。スリリングな思考実験を重ねながら、現代人の生活を支えている技術の原点まで遡り、再構築の可能性をとことん検証していく。
一読して痛感するのは、私たち個人の知識や能力と、身のまわりにある製品や技術の複雑さがあまりにもかけ離れているということ。そうした「生活の中のブラックボックス」にユニークな形で挑んだドキュメンタリーがトーマス・トウェイツ『ゼロからトースターを作ってみた結果』(村井理子=訳、新潮文庫)だ。表題どおり、著者は原材料から電気トースターを製作するべく鉱山に分け入って鉄鉱石を入手し(!)、七転八倒しながら(そして諦めてズルをしながら)プラスチックづくりにいそしむ。結果、4ポンド以下で買えるはずの代物が、実に1200ポンド弱、時間にして9ヶ月のコストに化ける。その抱腹絶倒のプロセスが消費社会の危うさを鮮やかに穿(うが)つ。
『オデッセイ』の邦題で映画化もされたアンディ・ウィアーの『火星の人』(小野田和子=訳、ハヤカワ文庫SF、上下巻)も同様の興奮に満ちた傑作。火星に取り残されてしまった植物学者にしてメカニカルエンジニアの男が、知識と技術を総動員してサバイバルに挑む。といっても謎の生物に出くわすわけでも隕石が落ちてくるわけでもない。やることといえば、水素と酸素から水を生成したり、排泄物を利用してジャガイモを栽培したり。だがそうしたトライ&エラーの過程こそがたまらなく胸を躍らせるのだ。
解説で紹介されている作者のコメントが最高にかっこいい。曰く〈科学がプロットを創りだすんだ〉。その言葉は、これまで人類が切り拓いてきた途方もない道のりを清冽に照らす。