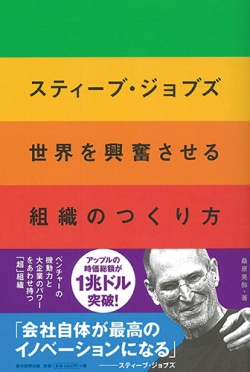スティーブ・ジョブズに学ぶ「創造的組織をつくる真のリーダーシップ」
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
スティーブ・ジョブズについてはこれまで、既成概念に縛られることのないビジョナリー、あるいは聴衆の心を的確に捉えるプレゼンターとしての側面に焦点が当たることが圧倒的に多かったのではないかと思います。
そんななか、『スティーブ・ジョブズ 世界を興奮させる組織のつくり方』(桑原晃弥著、朝日新聞出版)が特徴的なのは、「イノベーティブな企業、成長し続ける企業をつくりあげた経営者としてのジョブズ」にスポットを当てている点です。
イノベーションを起こすためには普段あまり顔を合わせることのないさまざまな部署の社員が偶然顔を合わせ、何気ない会話を交わし、そこからいろいろなアイデアや創造性が生まれることが必要だとジョブズは考え、ピクサーなどではそれを可能にするオフィスをつくり上げています。
環境もチームを構成する要素の1つであり、協働と創造性を促進するオフィスをつくってこそイノベーションは生まれるとも説いています。(「はじめに」より)
ジョブズのこうした考え方は、当時としては突飛なものであったはず。しかし現在では、イノベーションを生む組織やオフィスのあり方として広く理解されています。だからこそ、組織論的な意味合いにおいて見るべきものがあるということです。
そして、ジョブズが試み、成果を上げた組織のつくり方は、新しい働き方やイノベーションが求められている日本の企業に対しても多くの示唆を与えてくれるのだと著者はいいます。
「会社自体が最高のイノベーションになる」はジョブズの言葉ですが、ジョブズは「すぐれた製品」をつくるためには、「すぐれた人材」だけでも「すぐれた技術力」だけでもダメで、会社という組織そのものを「すぐれた組織」にすることがイノベーションを起こし続けるためには必要だと早くから気づいていたのです。(「はじめに」より)
この点に基づいて書かれた本書のなかから、6「創造的組織をつくる真のリーダーシップ」を見てみることにしましょう。
「CEOの私が、これは可能だと思うからさ」
革新的ななにかをつくろうとするとき、その妨げになるのは、多くの人の「そんなのできっこないよ」「そんなの無理に決まっているよ」というような反対の声。多くの場合、そうした声に押し切られる形で、「やめる」か、あるいは「ほどほどのところで妥協する」ことになるわけです。
しかし、それでは革新的なものが生まれることはあり得ません。そのことに関し、ここではソニー「ウォークマン」の話題が引き合いに出されています。
ソニーを世界的ブランドにした「ウォークマン」の開発を主導したのが、ジョブズも敬愛する盛田照夫氏(ソニー共同創業者、当時会長)。
ちなみにウォークマンのヒントになったのは、同じく創業者の井深大氏が音楽を聴くために自作して楽しんでいた「改造したソニーの小型テープレコーダーに大きなヘッドホンをつけたもの」でした。
それを見た盛田氏は1979年、会議室に担当者を集め、「若者が音楽を外に持ち出せるヘッドホン付き再生専用機」の商品化を指示。発売は夏休み前で、値段は4万円以下、開発期間4カ月という短さだったといいます。
しかし、ほとんどの担当者は「使ってみたい商品だ」と感じながらも、「録音機能のないレコーダーを買う人はいない」「月に3万台売れないと原価割れするが、そんな台数は不可能だ」と反対。盛田氏はそのひとつひとつに反論しますが、それでも迷う担当者にこう厳命したそうです。
「3万台売れないんだったら、俺は会長を辞めてもいい。会長命令だ。やれ。問答無用でやれ」
その結果、ウォークマンが音楽の聴き方を大きく変え、世界的大ヒット商品になったことはご存知のとおり。そのすごさは、ジョブズがiPod発売に際し、「これは21世紀のウォークマンだ」と呼んだことからも明らかです。
新しい挑戦にはいつだってリスクが伴うものですが、そんなときに人を動かすのは、徹底した理解と納得、そしてトップの有無を言わさぬ一喝だと著者。たとえば、こうした一喝が必要な理由について、ジョブズはこう話していたのだそうです。
「展示会で披露される試作車を見ると、『素晴らしいデザインだ。曲線美が素晴らしい』と思う。4、5年後に、その車がショールームに並び、テレビで広告されるけれど、ひどい姿に変わり果てている。いったいなにが起きたのか。アイデアを練って練って、結局ダメになってしまった」
こうなってしまう理由について、ジョブズは次のように推理しています。
素晴らしいデザインを思いついた設計者が、それを製造担当者に見せると、「無理。こんなのはつくれない。不可能だ」と突っぱねられることに。しかもエンジニアは、「可能」と思えるものに変更します。
次にエンジニアがそのデザインを製造担当者に見せると、製造担当者は「こんなもの、製造不可能だ」と言ってさらなる変更を要求します。その結果、「成功」を可能かどうかという基準でこねくり回され、どんでもない「失敗」に仕上がってしまうということ。
しかしジョブズによれば、革新的な製品をつくるために必要なのは、「このアイデアが現実的に可能かどうか」を議論することではなく、「なにがなんでも最高の製品をつくろうと必死で取り組む」こと。
おそらく世の中には、この自動車会社のように「素晴らしいアイデア」を思いつく人がたくさんいるはず。ところがそれだけではだめで、なにがなんでもそのアイデアを実現しようと、アイデアを積極的に支え、あらゆる反対を押し切って、最後まで信念を貫きとおすことが大切だというわけです。
ところが、たいていの企業では「素晴らしいアイデア」が生まれたとしても、「可能かどうか」の議論を繰り返すことによって「現実的なもの」「現状よりちょっといいもの」に落ち着いてしまいます。
それを打破できるかどうかが、「重力」の有無によって決まるのだと著者は記しています。
ジョブズがアップルに復帰したのち、最初に手がけたのはiMacです。従来のパソコンのイメージを大きく変えた製品ですが、当然、エンジニアたちからはたくさんの反対の声が上がりました。
放っておけばジョブズの言う「成功をこねくり回して失敗に仕上げる」ことになったはずですが、なぜそうはならずに大ヒットしたのでしょうか。反対の声に対してジョブズはこう言いました。 「CEOの私が、これは可能だと思うからさ」(195ページより)
新しい挑戦には、いつだってリスクがつきもの。しかし、だからといってリスクを避けていたのでは、企業としての革新など不可能です。「やるかやらないか」「可能かどうか」という段階でトップがあえて「リスクをとる」姿勢を強く打ち出すことで、企業の風土、文化は大きく変わることができるわけです。
つまり「私がCEO」だという発言は、ワンマンぶりを示すということではなく、「自分たちはリスクをとる会社である」ことを社員に知らしめる「重力」の役割を果たしているということです。(192ページより)
「他人の機嫌を損ねたり、怒らせたりしないようにするからリーダーシップが発揮できないんだ」
「人がどうふるまうかを大きく左右するのは、内なるスコアカードがあるか、それとも外のスコアカードがあるかということなんだ。内なるスコアカードで納得がいけば、それが拠り所になる」とは、アメリカの投資家、ウォーレン・バフェットの言葉。
多くの専門家、評論家がいる投資の世界には、「この株が上がる」「この株は下がるから買わないほうがいい」といった多くの声が渦巻いています。そんななか、しばしばこうした専門家の声を無視した行動をとるのがバフェットだということ。
でも、99%の人が右に向かっているときに、なぜひとりだけ左に向かうことができたのでしょうか。
その理由を問われ、バフェットが挙げたのが「内なるスコアカードーー長年の経験によって培った投資判断にまつわる強靭な信念」。周囲がどう考えるかではなく、自分がどう考えるかが大切で、その考えが理論的に正しいものなら、決して揺らぐことはないという考え方です。
ジョブズも、やはり「内なるスコアカード」のタイプ。そのため、「外のスコアカード」が強すぎる人に対しては、ときに辛辣な言葉を口にしているそうです。
2011年2月、ジョブズはグーグルやヤフー、フェイスブックの代表者たちとオバマ大統領(当時)を囲む少人数のディナーに出席しました。「アメリカにとってなにが大事なのか」というテーマで話し合おうというもの。
その席でジョブズは、アメリカの製造業を強くするためには、圧倒的に不足している熟練エンジニアの育成が急務だとして、「エンジニアの教育をしていただければ、もっと多くの工場を動かせます」と提案したそうです。
しかし、オバマ大統領の反応は芳しいものではなく、ジョブズはのちにこんな感想を口にしたといいます。
「大統領はたしかに頭がいいと思うけど、できない理由を説明してばかりなんだ。あれは頭にきたよ」
「オバマにはがっかりだ。他人の機嫌を損ねたり、怒らせたりしないようにするからリーダーシップが発揮できないんだ」
ジョブズのやり方は正反対のもので、こう追い切っているのだとか。
「僕は自分を暴虐だとは思わない。お粗末なものはお粗末だと面と向かって言うだけだ。本当のことを包み隠さないのが僕の仕事だからね。自分が何を言っているのかいつも分かっているし、結局、僕の言い分が正しかったってなることが多い。そう言う文化をつくりたいと思ったんだ」(202ページより)
ジョブズが「世界を変える」と自信満々で発表したMacintoshは、すぐれたコンピュータとして高く評価されました。しかしその一方、容量不足やソフトウェアの不足、昨日の拡張性への疑問などマイナスの評価をする人も少なくありませんでした。
しかし、「きちんと市場調査をして開発したのか?」という声に対し、彼はこう切り返しています。
「グラハム・ベルは、電話を発明する前に市場調査などしましたか?」
たとえば、既存のApple IIやIBM PCなど、当時すでに存在した製品について市場調査をするならともかく、世の中にまだ存在しないものについて市場調査をしても意味はないわけです。
ジョブズがよく使った例えのひとつが、ヘンリー・フォードがT型フォードをつくったときの話。当時、一般の人にとって自動車は夢のまた夢の存在。
そんな人たちに「乗り物になにを望むか」と市場調査をしたとすれば、返ってくるのは「もっと速い馬が欲しい」という意見。自動車について「ああしてほしい、こうしてほしい」と答えられる人は、ほとんどいなかったわけです。
新製品の開発などでは市場調査が重視されがちですが、そこから生まれるのは「いまよりちょっといいもの」であって、「ものすごくいいもの」が生まれることはありません。
だからこそジョブズは「外のスコアカード」には気もとめず、「内なるスコアカード」を信じることによって、世界に衝撃を与えるものをつくり続けたということです。
周囲の声に耳を傾けることは、もちろん大切。しかし最後に決めるのは自分であり、その決断を最後まで完徹するためには、多少のことでは揺るがない自信が必要だということです。(200ページより)
「ロックバンドみたいな大企業 アップル」「組織のメンバーはみなアーティストである」など、他の章の着眼点もそれぞれがユニーク。
そしてそれらは、ジョブズの人間性と、そこから生み出されたイノベーションの実像を浮かび上がらせてもいます。特に、組織のあり方についてのヒントを探している方にとっては、大きな収穫となるかもしれません。
Photo: 印南敦史