『はんぷくするもの』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
困難を生きる倫理
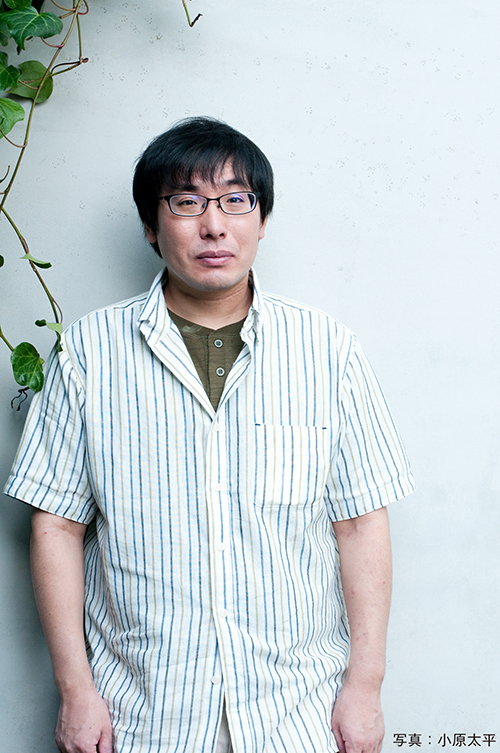
日上秀之さん
田中康夫、山田詠美、綿矢りさ、羽田圭介、若竹千佐子……新しい才能を世に送り出す、新人作家の登竜門「文藝賞」(選考員:磯崎憲一郎/斎藤美奈子/町田康/村田沙耶香)。第55回文藝賞は『はんぷくするもの』(日上秀之)、『いつか深い穴に落ちるまで』(山野辺太郎)の2作が受賞しました。両作品の単行本は11月中旬発売予定です。
***
倫理的な小説
町田 このたびは受賞おめでとうございます。
日上 ありがとうございます。
町田 今日はいろんな話をしたいんですが、まずはやっぱり、作品の話をしたいと思います。「毅(つよし)は手を洗わなければならなかった」からはじまるこの小説を読んで僕が思ったのは、倫理的な問いの厳しさについてです。それはどんな問いかというと、いま生きているこの状況を、個人的な感覚で徹底的に考える、ということです。
主人公である毅は、何度も手を洗います。家の中の埃や街の汚れが印象的に描かれていて、それはもちろん震災後のいろんな物事を象徴してもいるのだと思いますが、それを手の汚れという、主人公の個人的感覚を通して描いています。そして、手を洗うことでその汚れをなんとか除去しようとするけれど、すぐにまた汚れてしまい、何度も洗うことになる。そうした主人公の不安定さが、家や街の不安定さとして印象に残ってゆく。そのようにして、毅の感覚と周囲の状況がすべて一本の糸で繫がっているわけです。そのことに日上さんの、文章を書くことに対する決意のようなものを感じました。
日上 私にとっては、やはり震災という出来事が大きかったんです。津波によって、家の中のものはぜんぶ泥で汚れてしまいました。それらを拾ってきて洗って使うことになった時、自分の中で、どうしても拒絶するような感覚があったんです。私の親は、あまりそういうことは気にしない性格だったんですが。
町田 そうですか。僕がこの小説の文章から感じたものは、もしかしたら日上さんにもともと備わった考え方の癖みたいなものなのかもしれませんね。このようにしか書けないのだという、それを決意と感じたのかもしれません。「はんぷくするもの」は、毅という人物の内面を描いています。毅が頭の中で思ったり考えたりしたことを通して話が進んでゆく。この書き方は、ヘタに書くとただ自意識の垂れ流しのようにもなってしまいかねません。でもこの作品がそうなっていないのは、自分の考えや行為について、正しいか誤っているかという基準で判断するのではなく、それが一体何なのかを、毅はまず自分に問うているからなんです。人間というのは立派なことばかり考えるわけではないから、ひとりの人間が思っていることを書くとなると、考えとして駄目なことも書くことになる。そしてここで描かれる毅の考えというのは、正しさや誤りによる選別以前に、全部が問いとして自分にはね返ってくるものです。だから、これは非情に倫理的な小説なんです。
日上 なるほど。
町田 まず、毅は仮設店舗で商店を営んでいますよね。店舗の中の様子や、外の風景、街を流れる川、そして毅が持っている車、そうした毅の視点から見えているものたちが、毅自身が自分に対して激しく問うている倫理と見事に重なっています。たとえば、店舗の床は常にたわんでいる。「板敷きで一歩ごとにボフと音がし、それでも踏み抜いたことはない。しかしいつか足が床を突き破るさまを毅は思い描いてしまう」と。それは、このいつ潰れてもおかしくない商店を、自分の存在意義のために続けるという毅の倫理的な問いと重なってきます。こうした描写は、「足が床を突き破るさま」を思うという妄想も含んでいるから、一歩間違えると狂気として描くことになってしまいます。しかし狂気へ逃げることなく踏みとどまり、主人公や作者の考える倫理的問題、いわば生きるうえで直面する困難を描いている。狂気として描くなら話も派手になるけど、それは安易なことなんです。
日上 じつは、それは強く意図したというよりも、私が現実に経験していることを書いたら、こういう書き方になったんです。私は実際に仮設店舗で商店をしていました。震災後にプレハブを買って、土台などを作らずにそのまま地面にプレハブを置いて、お店をやっていたんです。すると、店舗内を歩いた時、実際にドスドスと音がして、床がたわむんです。
町田 実際に経験したことだから、迫力があるんですね。この仮設店舗の常に軋む床という描写は、毅をとりまく状況の不安定さを迫力をもってよく表していると思います。また、「見なし仮設」の床も軋んでいますよね。これは親戚から借り受けた家で、毅とその母親は生活の場として使っている。そして、ここでも台所の床が浸水で腐っていて崩落しそうだという。
これらの床の軋みが状況の不安定さ、いわば現実の軋みを表すとともに、毅個人の内面の軋みとも重なっている。こうした現実と内面の二重の配置が、この小説では常になされていますね。主人公の不安や鬱の垂れ流しではないというのは、そういうことなんです。毅という主人公の内面を、説明する言葉ではなく、小説内に配置されたイメージで描いているんです。
感覚に根拠はない
日上 私にも毅のもつ強迫神経症みたいなものがあって、それも毅という人物を描く際には影響していると思います。
町田 手を洗うこともそうですし、ツケの取り立てで古木さんの家へ行こうとして猫に車の発進を阻まれてしまうことも病的ですね。毅は、もし猫が車の下にいて、それを知らずに発進させてしまったらと心配しては何度も車の周囲を探します。さらにはボンネットまで空けて、いないことを確認して閉めるけれど、閉める寸前の目を離した隙に入り込んだかもしれないと思ってまた空ける。このくだりは面白かったです。
日上 ボンネットに猫が入ったまま死んでしまったという話を、現実に近所の人から聞いたんです。私はそういうことが気になってしまう性格で、ちゃんと家の鍵をかけただろうかとか、台所の火は消してきただろうかとか。そう思うのは一体なぜだろうと、難しい本を読んで理解しようとするんですが、なかなか……。だから小説を書いているんだと思います。
町田 猫だけでなく、車が汚れていて出かけられなかったり、さらには石ころまでもが、出かけるなと毅に命令しているかのように考えますね。
日上 毅の困難を突き詰めると、石ころという存在がその行動に大きな影響を及ぼすこともあるんじゃないかと思って書きました。
町田 これは、書き方によっては暗くなってしまうんです。それでは面白くない。でも日上さんの場合は笑える文章になっていて、これは純粋に文章の技によるものです。それを身につけているということが、いちばん大きい。これは単にテクニックとかそういうものではありません。困難があって、それを突き詰めて考えるというのは、日上さんの思考の癖みたいなものだと思います。
毅の困難な状況について、こうしたイメージを使わずに事情や経緯を書いたり、毅の気持ちを説明したりすることで描くこともできたと思います。しかし、それでは話が簡単に終わってしまう。この小説が良いのは、困難へと至った事情を書かず、そして毅が気持ちを語らないことです。たとえば、毅は自営業であることにこだわるけれど、自分ではそれがなぜなのか説明できません。
日上 はい。
町田 毅は自分の考えに、論理的な根拠をもっていないんです。そして、それが自分の弱さであることを認めていながら、改めることもできない。もちろん毅は自分の状況について、その根底に何があるのかは知っている。そしてそれを語ると、全部が自分にはね返ってくるということも、おそらくわかっている。責任感と正義感と罪悪感が全部混ざった感覚を毅は生きている。毅が根拠を語らないからこそ、こうした感覚まで描ける。そして、それはまさに、僕らが生きている状況でもあるんです。

町田康さん
生きる義務、生きる責任
日上 この小説を書く時に考えていたのは、ジャック・デリダの『パッション』に出てくる「義務と責任」という言葉のことなんです。私自身生きることに困難を感じていて、その理由を知りたいと思っていました。デリダの『パッション』を読んで、その義務と責任に対する応答のようなものを意識せざるを得なくなったのです。こうした義務と責任について、自分の店を舞台に描いてみようと思いました。
町田 日上さんの言う「義務と責任」ということで考えると、武田という人物が思い浮かびます。この小説はすべての登場人物が魅力的なんですが、僕は特に武田が好きで、正義を声高に主張して理想を掲げるけれども、現実においてはことごとく負けている奴ですよね。煙草のポイ捨てを注意することにすら、失敗します(笑)。武田は、負けつづけの自分を「正しい」主張に仮託することで、負けの現実を生きる責任のようなものから逃れようとしている。そういう武田のあり方は、語らない毅とは正反対ですよね。対比になっています。だから、武田の存在は、この小説ではとても大事なんだと思います。
他の登場人物に、古木さんや風峰さん、そして毅の母親といった人々がいますが、彼らもそれぞれ特徴的ですよね。彼らの人物造形は、どういったところから着想を得ているんでしょうか?
日上 これまで私が出会った人々から着想を得たところもありますが、武田については、創作的な部分が多いんです。正義を語っていながら、その存在が悪である、という人を考えていました。つまり、武田は万引きという悪の行為をしながら、それを正義として語ります。正義なのか悪なのか判断がつかない事柄を描きたかったんです。
町田 答えがなくわからないことを、わからないままに書く。それは小説を書くうえでいちばん大事なことだと思います。しかも武田という人物は、現実にこういう奴おるよな、と笑える奴にもなっている。それが素晴らしいと思います。
日上 ありがとうございます。
町田 俺は絶対に正しいなんて言う奴は、どう考えたって正しいわけがないですからね(笑)。
日上 そうですね(笑)。
「震災文学」と一線を画すもの
町田 この小説にあるのは、当然ですが毅の困難だけではありませんね。つまり震災から何年かが経っているけれど、まだ思うように社会が回っていないという、社会的な困難が背景にあります。そうなると、いわゆる「震災文学」として読まれうるんですが、この作品が他の「震災文学」と決定的にちがうのは、毅がそれらの困難のすべてを、自分の個人的困難として捉えようとしていることなんです。
天変地異というのは社会全体が負ったものだから、それを描く時には社会的困難として描かれることが多い。あるいはさらに現実の状況に寄ることで、政治的困難として描く人もいる。武田みたいな人は、この状況を政治的困難として捉えていますよね。だから、武田のことは笑えないんです。これは「震災文学」を笑えないのとおなじことです。
しかし毅は、震災を社会全体が負ったものとすることにためらいを感じている。それは、ツケの金を返さない古木さんから「あなたは津波に家を流されたじゃないですか」「我が家はね、全く無事だったんですよ。波の飛沫すら一滴もかかりはしなかったですよ」と言われて、毅はそれ以上金を返せと言えなくなってしまうことに、あらわれていると思います。震災や津波を社会的困難として考えたなら、家を流されなかったお前こそ恵まれているんだから金を返せ、と言い返せます。家を流された方がひどい目にあっている、そんな人に、どうして恵まれている方が金を返さないんだ、というのが普通のロジックです。しかし津波を個人的困難として捉えた時に、逆転が起きるんです。つまり古木さんの言葉は、あなたは天変地異に罰せられたのだから不正義なのだ、自分は罰を受けていないから正しい、だから返さなくていいじゃないかと、そういうことですよね。毅はこれを自分に対して本気で問うてしまう。これは、とてつもなく厳しいことじゃないですか。
日上 震災という出来事に対して、武田みたいな正義のあり方が挫折してきた、というのが最近のことなんじゃないかと考えています。それを個人の問題として考えたときに、たとえば、震災についての報道ってたくさんありましたよね。もちろん今でもありますし、今もたくさんの被災者がいます。そして、被災者はどんな目にあったのかということが報道されます。一方で古木さんのように、被災地にいながら被災をしていない人というのは、被災者よりも多くいるわけです。
町田 家も体も無事だった人たちですね。
日上 そうです。この小説を書いている時、そうした非被災者たちについて考えていました。災害を目にしていながら、しかし被災者として主題化され得ない人たちの内面についてです。彼らには、報道によって主題化されることで得られる救いやカタルシスみたいなものがなくて、その方が実は救いがないことなのかもしれないと。
町田 マスコミが取りあげるものもありますが、もっと一般的に文学などの表現も含めて、被災した人たちは主題化されることで気持ちが伝えられている、ということでしょうか?
日上 はい。それによって浄化されるものはもちろんあると思うんです。しかし、それを見て非被災者たちは傷ついているんじゃないか。彼らは、肉親を失ったわけでも家屋を失ったわけでもないから主題化されることがなく、語る言葉を持たない。それでも被災地で、震災後を生きなければならないんです。
町田 そうした人たちに言葉を与えたかったということですね。それはとても厳しいことですよね。そのことは作品を通じてすごく伝わりました。やはりこの作品はバックグラウンドが大きいんですよね。小さい世界を描いているようで、広く深い根を張っている。
日上 ありがとうございます。
町田 一つだけ、わからなかったことがあります。最後にまた振り出しに戻りますよね。毅は古木さんの問題に集中しはじめてからあまり手を洗わなくなります。しかし、古木さんが金を返したとたんに、また手を洗いたくなってくる。そしてまた古木さんがツケで買い物に来て、毅はそれを受け入れてしまいます。「はんぷくするもの」という、このタイトルは後で決めたんでしょうか?
日上 そうです。タイトルがすんなり決まる時とそうでない時があって、この小説はなかなか決まらなかったんです。
町田 なぜこういう構造にしたんでしょうか?
日上 最後にまた古木さんがツケで買い物に来ることで、除去が不可能な反復強迫みたいなものを描きたかったんです。そこにどう立ち向かうのか、ということを考えていました。
町田 なるほど。僕は、ラストでおなじポイントに戻るのなら、スパイラル状にさらにもっと怖い状況へと行けるならさらに良いと思ったんです。
日上 毅は未熟な人間で、彼にとって成熟するというのは寛容になる、ということなんだと思いました。しかしその寛容さはやっぱり偽装であって、だからこそ、ぽんと同じ地点に戻ってしまうんです。毅の周囲には緊張関係がありながらもどこか笑える、そういった世界が延々と連なってゆく、そんな感覚があったのかもしれません。しかしたしかに、この反復を悪循環と捉えれば、スパイラル状に別の状況へと行く方がより効果的だと思います。

日上秀之さん
困難を抱え書いてゆく
町田 日上さんは、これまでどんな小説を読んできたんでしょうか?
日上 ロシア文学の持っているユーモアが好きなんです。私にとって、癒されるところがあるんです。
町田 そうしたユーモアが好きな点は、この小説の軽みに繫がっていると思います。日本の作家ではどうですか?
日上 大江健三郎さんや古井由吉さんが好きで、彼らの文体にのめり込む時期がありました。町田さんの小説にも影響を受けました。それから金井美恵子さんや中上健次さんも好きです。どれも文章がいいなと思っていて、でも、私にはそうした文章が書きたくても書けないということがわかったんです。
町田 まあそれは、それぞれが独自にやっていることですからね。
日上 町田さんの小説では『ホサナ』がすごく好きなんですが、この小説では「光の柱」をはじめとして、現実世界を超越したものが描かれていますよね。私は以前、そうした超現実的なもの描こうとして失敗したことがあって、ある新人文学賞に応募したけど落選したんです。そうした現実を超えたものを破綻なく描くにはどうすればいいのか、今日は伺いたいと思っていたんです。
町田 それは、日上さんが社会的困難を個人的困難に結びつけたことと、おそらくおなじだと思います。現実を超えたものだって、結局は人間の考えることですから、何か根拠はあるんです。たとえば「光の柱」なら、そういうものを見たいと思う気持ちや怖いと思う気持ちが、自分の中にある。ごくシンプルなことなんですよね。それを自分の心の中に探し当てれば、小説の中でどこまでぶっ飛んでも必ず一本の糸で自分の中の根底と結びつく。そして、自分の中にあるそうした根底は、死ぬまでなくならないんです。つまり、嫌でも付き合わなければいけないものです。逆に言うと、自分の心の中にないものは書かない、ということでもあります。
日上 なるほど。
町田 思ってもいないことを書くなということですね。これはウケる! とかいって書いても限界がありますよ。そういうものを書いてちゃんと読まれている人はいますが、その世界は競争が激しいですからね(笑)。
日上 そうなんですね(笑)。町田さんの文体には強いオリジナリティを感じるんですが、そうした文体はどうやって身につけるものなんでしょうか?
町田 文体よりも中身が大切ですよ。もちろん、パッと読んだだけでその人の文章だとわかるものはあるし、文体そのものが訴える何か、というものは確かにあります。でもそれよりも重要なのは、ある文章を書いた時に、その言葉の背景にどれだけの思考や体験を持っているかということだと思います。たとえば、日上さんの小説の冒頭に、「毅は手を洗わなければならなかった」という文章がありますが、同じ文章を別の人が書いても、伝わり方が違うと思うんです。たとえばひたすら潔癖で神経症の主人公で小説を書いたら面白いかなと思ってこの文章を書くのと、自分の困難のあらわれだと思って書くのとでは、おなじ一行でもまったく違うと思うんです。
気の利いた表現をしようとか、自分らしい特徴を出してやろうとか、いい人だと思われようとか、そういった意識が働くと、たちどころに文章が渋滞して穢れてきてしまいます。それは読んでいてわかるんです。先ほど話題になった、猫が車の下に入り込んでいると毅が思い込むくだりも、これは笑わせてやろうと思って書いたのなら、違うものになっているはずです。このくだりは笑えるけど、これは、日上さん自身が本気でそう思ったことがあって、そのうえで書くことで達成される笑いなんです。
日上 なるほど。
町田 あとは数ですね。今後作家として読者の目に晒されたうえで、どれだけ多くの文章が書けるか。ちなみに日上さんは、毎日書いているんですか? それとも休みの日に一気に書くタイプでしょうか?
日上 アルバイトが休みの日に書いています。でも書きはじめようとするといつも、もう書けないんじゃないかというプレッシャーに駆られて、なかなか書き出すことができません。文学に捨てられるんじゃないか、という恐れがいつもあるんです。
町田 それは誰でも一緒ですよ。書きはじめる時というのは。だから心配する必要はありません。でも、書きはじめてからどれだけ早く文章に入り込めるかが勝負です。常にそうした恐れとバランスを取りながら書いているから、日上さんの小説には迫力があるんだと思います。調子に乗ってへらへら書くのではなく、ぎりぎりのところでバランスをとっているんですね。
日上 どうなんでしょうか。
町田 きっとそうですよ。まあ、一年後に会ったら六本木あたりに住んで、調子のいい兄ちゃんになってるかもわからないですけどね(笑)。
日上 (笑)。書き続けていくための秘訣などはあるんでしょうか?
町田 やっぱり結局は、自分が書いていて面白いと思うことを書く、ということですね。面白いといってもいろんな面白さがあると思うんですが、たとえば、苦労して嫌で嫌でたまらなかったけど、出来上がって嬉しいっていうのは違うんです。そうではなく、書いていて面白い、日々面白い、ということが大切ですね。そう感じられる素材や題材を、自分で見つけられるといいと思います。
もちろん、生きるからには困難があります。それは死なない限りなくならない。それをいかに文学にして遊べるか、いかにその困難を面白がることができるかが問題なんです。日上さんはそのための道のりを、だいぶ摑んでいると思います。でも、ひとつ道ができたからといって、スイスイ行けるというわけではありません。以前通ったところは雑草が生えてしまうし、毎日同じところを通ったら踏み跡だらけになってしまうから、一回ごとに新しく道を作るんです。だからこそ、面白いことがないと道を作れない。そのためには、ぜひ自信を持ってやってください。
(二〇一八年九月八日)


































