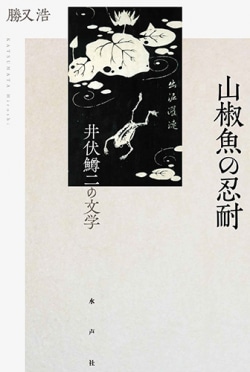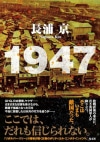『山椒魚の忍耐』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
山椒魚(さんしょううお)の忍耐 井伏鱒二(いぶせますじ)の文学 勝又浩著
[レビュアー] 葉名尻竜一(立正大准教授)
◆無力さに立ち会う「私」
文学理論や専門用語に頼らなくても、ふだん使う実感のともなった言葉で、作品とそれを書き上げた作家に肉薄できることを改めて気づかせてくれる文芸評論だ。とくに感触で人間を捉え、描き続けてきた井伏文学にあって、与えられた運命を泥まみれで精いっぱい生きる登場人物たちの「忍耐」に論及できないとしたら、それは評論の役目を果たしていない。
著者は近代文学でも私小説を、日本の伝統文化に根差した代表とみなす立場をとる。基本的に井伏鱒二は私小説作家ではないが、双方に通じることとして、確かに自分がここにいると思い知らされた自身の読書体験があるようだ。
その上で、私小説が私の体験や見聞を加工潤色するのに対して、井伏の小説は聞いた話や空想された話のなかに、現実には立ち会っていない「私」を創作し、立ち会わせてしまうと看破する。他用に押され、井伏文学と向き合う時間が途切れ途切れになりながらも、半世紀近くの熟慮を経てこの読解に至る。
さらに「美しい日本の私」と述べた川端康成の文学が平安王朝文学につながるのなら、井伏は『今昔物語集』『鳥獣人物戯画』に息が通じるとし、「社会化した私」を論じた小林秀雄が自意識に振り回されたとしたら、井伏はパロディーによって応じたとする。また、英雄話や恋愛小説へ傾かなかった文学姿勢によって、身分意識を超えた美しい主従関係を描き得たと説き、隠れた名作『へんろう宿』の宿縁に作家二十歳の体験の影を見る。
世界文学と言ってよい『黒い雨』には、不安そうな顔つきで死んだ母親の乳房を握りしめる幼女が登場する。そんな場に行きあたって先へ進めなくなった姪(めい)に、被爆者の閑間重松(しずましげまつ)は「勇気を出して、そっと跨(また)いで来るんだ」と励ます。著者は「原爆という事実の後になお生き続ける人間全体に語りかけている」と読む。井伏文学のなかには、自らの無力さ、みじめさ、情けなさを身に沁(し)みて感じつつ、それでも寄り添う人間が隠されていることを見つけ出す。
(水声社・3024円)
1938年生まれ。文芸評論家。著書『中島敦の遍歴』『私小説千年史』など。
◆もう1冊
井伏鱒二著『荻窪風土記』(新潮文庫)。東京・荻窪での暮らしや交友を描く。