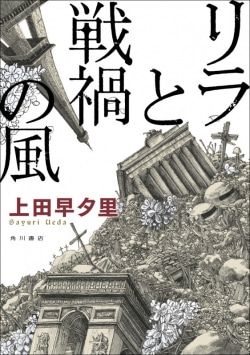【ニューエンタメ書評】“共通するテーマを異なる手法で描く作品”4組8作品 葉真中顕『Blue』上田早夕里『リラと戦禍の風』青柳碧人『むかしむかしあるところに、死体がありました』ほか
レビュー
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
エンタメ書評
[レビュアー] 大矢博子(書評家)
今回ご紹介するのは、“共通するテーマを異なる手法で描く作品”4組8作品。注目の新刊をより楽しむヒントがいっぱいです!
***
「平成、という時代があった」
という書き出しからいきなり掴まれた。葉真中顕『Blue』(光文社)である。その国に暮らす多くの人々にとっては、意味のある時代だった──と続けたあとで、著者は(語り手は、というべきか)平成をこう説明する。
「内戦も戦争もなかった平和な時代として。いくつもの天災に見舞われた災害の時代として。バブル経済の崩壊に始まり格差拡大と貧困問題が可視化された衰退の時代として。行政と社会のシステムが制度疲労を起こす中さまざまな対立が鮮明になった分断の時代として。あるいは困難の中からそれでも次世代に何かを残そうとした希望の時代として。
そんな平成という時代が始まった日に生まれ、終わった日に死んだ一人の男がいた」
いやあ、これで読みたくならない方が嘘だろう。二〇一九年上半期の書き出し大賞をあげたい。
物語は平成十五年、青梅で起きた一家四人惨殺事件から始まる。風呂場で死んでいたこの家の次女に外傷がなかったことと覚醒剤の多量摂取が見られたことから、この次女が犯人なのは間違いないと思われたが、現場には共犯者の痕跡が残っていた。しかも高校時代からひきこもっていたはずの次女に、意外な事実が判明して……。
平成元年に生まれた男と、平成十五年の殺人事件、そして平成最後の年に起きた殺人事件を一本の糸でつなぐダイナミックなクライムノベルである。その間には、その時どきの文化や風俗、出来事、流行などが細やかに、具体的に描きこまれる。SMAP、たまごっち、ITバブル、児童虐待、オザケン、リーマンショック、子どもの貧困、SPEED、仮設住宅、外国人労働者……。そんな平成の光と闇の中で、なぜ「彼」は殺人者になったのか。高所から時代を総括するのではなく、あくまでも地面に近いところから社会をえぐる葉真中顕の真骨頂だ。
作中、特にフォーカスされるのが親と子の関係だ。我が子を愛せない、愛さない親が複数登場する。それが大きく物語を動かしていくのだが、読みながら思い出したのが、まさきとしか『ゆりかごに聞く』(幻冬舎)である。
新聞社で働く柳宝子のもとに、父親が亡くなったという連絡が入る。だが宝子の父は二十一年前に、すでに亡くなっているのだ。これはどういうことか? というところから始まった物語は、血の繋がらない子を愛した親・血の繋がった子を愛せないことに悩む親・悩まない親という、さまざまなタイプの「親」を描き出していく。
父の死の真相と、そこから次々判明する意外な事実の連鎖にはページをめくる手が止まらなかった。物語の序盤で起きる殺人事件、別の事件との思わぬリンクなど、ミステリとしての吸引力は実に強い。だがそれ以上に、人はどうすれば「親」になれるのか、親を親たらしめているものは何なのかというテーマが重く胸に刺さる。
思えば『Blue』と『ゆりかごに聞く』は同じテーマを扱っているのである。だがアプローチも、そのテーマの表現の仕方も、まったく異なる。ひとつのテーマを描くのに作家によってこういう違いが出るのか、と実に興味深かった。
今月は他にも「同じテーマなのに手法が異なる」作品があった。いくつかセットで紹介しよう。たとえば上田早夕里『リラと戦禍の風』(KADOKAWA)と天野純希『もののふの国』(中央公論新社)だ。
まず『リラと戦禍の風』は第一次世界大戦中の欧州が舞台。長引く消耗戦の中、砲弾の攻撃を受けたドイツ兵のイェルクは謎の紳士に助け出される。なんとその紳士は四六〇年も生き続けている魔物で、イェルクの本体は今も戦場にあり、ここにいるのは精神の半分だというのだ。戦争は嫌だという半分がここに来て、「仲間を見捨てて自分だけ逃げられない」というもう半分は動かないという。
はっきり白黒に分けられない人間の多面性を突きつけられながら、読者は半分のイェルクとともに戦時下の欧州を俯瞰する。飢餓に苦しむ人々がいる一方で、戦争に生きがいを見出す者もいる。そしてイェルクはある決断をする──。
一方、『もののふの国』は九百年以上続いた武士の時代の変遷を描いた歴史小説である。武士というものが台頭するきっかけとなった平将門の乱に始まり、源平合戦、南北朝、本能寺、江戸幕府、大塩平八郎、そして倒幕、西南戦争。武士の時代のターニングポイントを描くことで、どのように武士が続いてきたか、武士とはどのような存在だったのかを描く壮大なクロニクルだ。
ただ時系列に出来事を並べただけではなく、すべての時代に登場する「すべてを見通す存在」がポイント。伝奇要素を取り入れたことで、なぜこれほどまでに武士の時代が続いたかが明らかになるのである。
かたや欧州の歴史ファンタジー、かたや日本の歴史小説。まったく違うジャンルに見えるが、ところがこの二冊、どちらも「なぜ戦いは繰り返されるのか」というテーマを、ファンタジックな要素を用いて描いた小説なのである。私はたまたまこの二冊を続けて読んだのだが、これほどかけ離れたモチーフの小説が同じ骨を持っていたことに実に驚いた。そしてやはり、同じテーマでも作家によってここまで料理の仕方が違うということに感じ入ったのだ。
続いてのペアは本格ミステリとSFだ。青柳碧人『むかしむかしあるところに、死体がありました。』(双葉社)は、日本の昔話に題材をとったトリッキーな短編集だ。一寸法師が殺人の疑いをかけられるが、その事件が起きた時刻には鬼の腹の中にいたという鉄壁のアリバイがあった……という「一寸法師の不在証明」。花咲か爺さんが何者かに殺され、飼い犬がそのダイイングメッセージを解く「花咲か死者伝言」など、お馴染みの昔話の設定をうまくトリックに組み込む手腕はさすが。中でも感心したのは、鶴が恩返しにやってきた弥兵衛はその直前に人を殺していたという「つるの倒叙がえし」である。最後まで読んで明かされる仕掛けに「え?」と思い、慌てて読み直し、仰天した。うわあ、そういうことか!
これとセットで読んでほしいのが菅浩江『不見の月 博物館惑星Ⅱ』(早川書房)である。日本推理作家協会賞を受賞した『永遠の森 博物館惑星』から実に十九年ぶりの続編だ。
月と反対側の重力均衡エリアに浮かぶ博物館惑星には、地球で生まれた古今のあらゆる芸術や動植物が収められている。そこで働く警備員を主人公に、彼や学芸員が直面する事件を連作形式で綴ったSFミステリだ。盲目の演劇評論家が触覚でミュージカルを「見る」という最先端技術がある一方で、二十世紀の手回しオルガンをそのまま保存したりもする、テクノロジーとノスタルジーが絶妙に融合した連作である。
面白いのは学芸員や警備員の脳がデータベースと直結しているという設定。彼らは必要とあらば脳内でデータベースに接続して検索し、そのデータをコンタクトレンズに投影させたり、人工知能に命じて車を呼んだりドアを開けたりする。SiriやAlexaの超進化系のような設定が、「ググる」という言葉すら聞かなかった二〇〇〇年刊行のシリーズ第一作から存在していたことがすごい。当時は完全にSFの話として読んでいたのに、今や「もうすぐできそう」と思えるんだから。科学の進歩がすごいのか、SF作家がすごいのか。
さて、この『不見の月』と『むかしむかしあるところに、死体がありました。』は、それこそまったく毛色の違う話だ。だがこの二冊を読むと「芸術を味わう・芸術を解釈する」とはどういうことか、というテーマが浮かび上がるのである。古より語り継がれる昔話に、現代ミステリの趣向をまぶして別の物語を生み出す。今、私たちが楽しんでいる芸術を、別の技術や方法で味わう未来を描く。その両方に共通しているのは、小説を含むあらゆる芸術はいつの世も不変であり、それを味わう楽しみもまた、時代ごとに形を変えながらもずっと続いていくという心強いメッセージなのだ。
最後のセットとして降田天『偽りの春 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』と柚月裕子『検事の信義』(ともにKADOKAWA)を挙げておこう。
二〇一八年の日本推理作家協会賞短編部門の受賞作を含む連作ミステリ『偽りの春』には、犯人側の視点で描かれた五つの物語が収められている。それを、たまたま出会った(あるいは捜査していた)神倉駅前交番の狩野によって見破られるというシリーズだ。どの短編も実に上質の「騙し」が味わえるが、ただトリッキーなだけでなく、なぜその犯行を起こしたのかの物語が圧巻。狩野が犯罪を見破るきっかけは物理的なものが大半だが、犯行に至った心情こそ本書の読みどころだ。
その心情を正確に掴もうとする捜査側を描いたのが『検事の信義』。佐方貞人シリーズ第四弾となる短編集である。たとえ裁判で検察側に不利な判決が出ようとも、犯罪者の事情をとことん汲み上げ、その上で正当な裁きを受けさせようとする佐方。終盤に大逆転のある展開はミステリとしても上質でエキサイティングこの上ない。
『偽りの春』『検事の信義』の両方に、警察の捜査上の問題が登場する。セットで読むとその問題のありようが多面的に浮かび上がるとともに、犯罪を起こす側・捜査する側のドラマがいっそう強く味わえるはずだ。
小説はもちろんそれ単体で充分楽しめる。だがまったく違う話に思わぬ共通項があったり、ひとつのテーマを別の視点から描いていたりということに気づくと、その楽しみはさらに豊潤になる。ぜひお試しいただきたい。