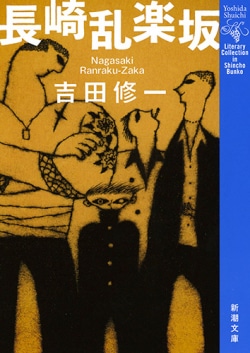書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【特集 吉田修一の20年】吉田修一、新潮文庫の自作を語る【前篇】
[文] 新潮社
『7月24日通り』(2004年)
地味で目立たぬOL本田小百合は、港が見える自分の町をリスボンに見立てるのが、ひそかな愉しみ。異国気分で「7月24日通り」をバス通勤し、退屈な毎日をやり過ごしている。そんな折届いた同窓会の知らせ。高校時代一番人気だった聡史も東京から帰ってくるらしい……。もう一度恋する勇気がわく傑作恋愛長篇。
――『7月24日通り』は仕掛けを思いついたときに、それこそ半分出来た感じではなかったですか?
吉田 長崎をリスボンに見立てながら暮らしている地味な女の子が主人公ですが、最初にあったのはそれだけで、ラストの方で十項目のリストを出すなんてのは、最初は考えていませんでした。どの作品でもそうですけど、小説を書いている時は、「これ、最後で化けてくれないかな」と願いながら書き進めているんです。あれこれ手さぐりでやっているうちに、鍵穴に鍵がカチッと嵌まるみたいな時があって、「ああ、来た来た」(笑)。これは快感ですよ。
でも、「東京湾景・立夏」は短篇だから別ですが、長篇の場合は、書き始める前に「嵌まった!」と思うアイデアが浮かんだとしても、わりと……。
――捨ててしまう? 人工的な感じがするんですかね?
吉田 うん、なんか窮屈というか、書く前に思いついたものには、単純に興味がなくなってしまうんですね。で、『7月24日通り』は、執筆の途中で浮かんだリストのアイデアがうまく嵌まったと思います。
――リスボンの街と長崎を重ね合わせるというアイデアはこの小説のために思いついたんですか?
吉田 長崎の子どもは学校で習うんですよ。長崎の街はポルトガルの街に似てるって。坂があって、石畳があって、港に向って開けてて、みたいに。
――リスボンへ行かれたことは?
吉田 書き終えた後で行ったんです。7月24日通りなんて、地図で見つけただけだったから、実際に行ってみましたよ。普通の産業道路です(笑)。
『7月24日通り』は「小説新潮」と同時にドコモのケータイ小説として配信もされたんですよ。ケータイ小説の走りの時期でした。僕はけっこう媒体を気にするので、ポップに書こうという意識はあったと思います。女子の一人称というのも、これで初めてやりました。語り手の性別は、実際にやってみると、そんなに意識せずに書けました。
――『東京湾景』は連続ドラマになったし、『7月24日通り』は映画になりました。映画の試写にご一緒した時、吉田さんが「ひとりで見ます」って、サッと少し離れた席に行かれた。映画好きとしては、いろんな感慨があったのでは、と……。
吉田 あの頃を思い出すと恥ずかしいんですよ。なんか作家としてセルフプロデュースしなきゃいけない、と思い込んでいたフシがあるんです(笑)。山本賞と芥川賞を連続でもらって、本当にガラッと景色が変わったんです。それまでは作家と名乗っていても、「文學界」に半年に一つ短篇を書くくらいですから、人に見られることも、写真を撮られることもない。そんな生活を五年くらい続けていたのがガラリと一変した時に、これからどうするか、自分でちゃんと考えなきゃいけないんだなと思って……ほら、何て言いましたっけ、キャラ作りに迷うのって?
――えーと、迷走?
吉田 そう、明らかに迷走してた(笑)。作家としてどう見られたらいいのか、なんて悩んでいました。作品というより、作者が迷走してた。原作の映画もひとりで見た方がいいのかなとか、作家なんだから夜眠れないとか言ってみようかとか……無茶苦茶よく眠れてるのに(笑)。
――あの頃は、周りの人が信用できないぐらいの感じでした?
吉田 逆なんですよ。だから、かえって迷いが(笑)。でも、よく覚えているのは、二つの文学賞をもらった時、ある人に、「これでもう吉田君、十年大丈夫だよ」って言われたんです。それを聞いた瞬間、「あ、失敗できる」と思った。十年大丈夫ということは、十年も失敗できるんだって(笑)。だから、この時期はいろんな小説を書いているんですよ。『東京湾景』に『日曜日たち』(03年)、『7月24日通り』、『長崎乱楽坂』、『ランドマーク』、『春、バーニーズで』(すべて04年)、みんなバラバラでしょ?
――しかも面白い小説ばかりですよ。さすが、作者は迷走しても作品は迷走してない(笑)。もうひとつ、作品の文体ではなくて、ヴォイスというんでしょうか、作品が読者に対して出す声が、この時期に厚く安定してきたというか、変化したように思ったんです。
吉田 あ、それは本当にそうですね。余裕とも違うけれど……『パレード』以前、「文學界」で短篇をこつこつ書いていた頃って、もうこの一作で生きるか死ぬかだったんですよ(笑)。いや真面目に、いま書いているこの小説がダメだったら、もう本当に終わりだと思っていました。新人賞を取って、何とか雑誌に新作が掲載され続けて、必死に戦っている作家って、二作続けて失敗作を書いたらもう載らなくなるわけです。野間新人賞、三島賞、芥川賞なんかの候補になったら、次も書けるけど、二作空振りしたら、間違いなく消えていく。またそれを周囲がみんな、わかっているわけです。ギリギリで書いていましたよ。
――ボツになった作品も?
吉田 いっぱいあります。ただ、芥川賞の後で文春の編集者の方々から言われたんですけど、「吉田さんはボツになっても凹まなかったね」って。僕は、「このへん変えましょう」と言われると、一回くらいは書き直しますけど、わりとあっさり、もういいやと思っちゃうんですよ。「あと二週間ください」つって、まったく新しい短篇を書いちゃう。書きたいことは変わらないので。そっちの方が勢いも出るのかな、そのまま掲載されたりして。
――ギリギリだけれども、「この作品だけは!」みたいには執着せずに……。
吉田 執着はあまりしないんですね。これは人間のタイプなんでしょうけど、「これを何とか」と思っても、どうにもならない場合ってあるじゃないですか。例えば、担当編集者が異動するとかね、外的な要因もあるかもしれないし。