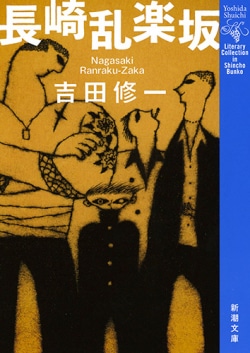書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【特集 吉田修一の20年】吉田修一、新潮文庫の自作を語る【前篇】
[文] 新潮社
『長崎乱楽坂』(2004年)
荒くれどもの棲む大家族に育った幼い駿は、ある日、若い衆が女たちを連れ込んでは淫蕩にふける古い離れの家の一隅に、幽霊がいるのに気づく――。湾の見える町に根を下ろす、昭和後期、地方侠家の栄光と没落のなかに、少年の繊細な心の成長を追う傑作長篇。
――『長崎乱楽坂』刊行の頃のインタビューも読み返しますと、『東京湾景』『パーク・ライフ』『ランドマーク』と書いてきたから、都会系の作家と思われないように云々と。
吉田 ほら、またキャラの迷走が(笑)。
――都会的な恋愛小説家とか括られると、あまりいいことなさそうだなと思ってらしたんですか?
吉田 いや、そこまで性格ひん曲がってないです(笑)。たぶん、少しビックリ状態だったんですよ。『パーク・ライフ』書いたあと、本当に雑誌なんかの紹介で都会派作家って書いてあって、そりゃビックリしますよ。自然と「いやいや、違うんですよ」ってなるじゃないですか。それで『長崎乱楽坂』を書いた(笑)。「いや、こっちなんです」って。
――「こっちなんです」というのは、「こっちもできます」とはちょっと違いますよね?
吉田 全然違います。「こっちもできます」じゃないです。「いやもう、僕はこれなんですよ」っていう感じ(笑)。実際、『乱楽坂』にでてくる人物や風景は、僕が見てきたものばかりです。
――今は〈反社〉なんて新語もありますが……。
吉田 長崎の実家は酒屋だし、そんな家に生まれ育ったわけではないけれど、わりと身近にその手の人たちがいたんですよ。親戚には肉体労働者も多くて、気性の荒い男たちがたくさんいました。
――それを吉田さんは物語の豊かな水源にされていますね。『国宝』(18年)の最初の方、久しぶりに『長崎乱楽坂』の世界だと嬉しくなりました。
吉田 『乱楽坂』は連作だから、『国宝』のような大きな物語じゃなくて、男の子が少しずつ大きくなりながら、その年齢なりの視線で周囲を徐々に見回していく。もちろん小説だから事実とは違うのですが、自分が本当に見たものを思い出しながら書いたという点で、ほかの作品とはハッキリ異なります。
――『長崎乱楽坂』にせよ『7月24日通り』や『悪人』(07年)にせよ、長崎があるのはやっぱり得ですよね、作家として。
吉田 これはもう本当に得。で、いま思うと、肉体労働者の生活が近くにあったのも得。やはり、地方の街で、ああいう人たちの近くで育つと、人間の生っぽい感じがよくわかるんですよ。もちろん東京のサラリーマンの家庭にも生っぽいところはあるのでしょうけど。
作家になってしばらく経った時、東京の都心の道を歩いていたら、いわゆる肉体労働系のお兄ちゃんたちが屯ってた。そしたら、そのお兄ちゃんたちを「怖い」と言う人がいたんです。逆に僕は、背広のサラリーマンの人たちが集まっていると体が固まるんですよ。もし、こっちに肉体労働者の人たち、あっちに丸の内のサラリーマンたちがいて、どちらかに混じって弁当を食べなきゃいけないと言われたら、間違いなく肉体労働者の方で食べます。刷り込みみたいに馴染みがあって、落ち着くんですよね。
その彼らを「怖い」と言われた時、「あ、なるほど」と思った。もう作家になっていたから、「こういうことをちゃんと書いていけばいいんだな」って。
あと、長崎を書いていて楽なのは全然遠慮しなくていいこと(笑)。『ランドマーク』の大宮でも、『湖の女たち』の琵琶湖でも、少しは遠慮して書いているんですよ。長崎はどんなに悪く書いても平気……僕が勝手にそう思っているだけですかね?
(次号後篇につづく)
※【特集 吉田修一の20年】吉田修一、新潮文庫の自作を語る【前篇】――「波」2019年9月号より