『ツナグ 想い人の心得』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【『ツナグ 想い人の心得』刊行記念対談】辻村深月×松坂桃李 「ご縁」が繋ぐ、出会いと想い。
[文] 立花もも(ライター)
「ご縁」が物語を繋いでいく
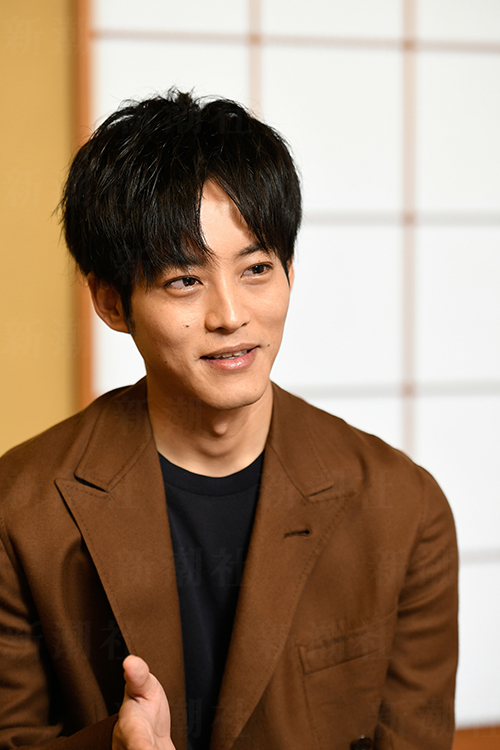
松坂桃李さん
辻村 逆に、事実をベースにしたお話が第三話の「母の心得」。ドイツ留学した娘が癌になってしまい、若くして亡くなった後、ドイツに行ってみたら……というくだりは『東京會舘とわたし』の取材で出会った方にお聞きしたことなんです。
松坂 娘に会いたいと依頼する小笠原さんですね。品のある、素敵なおばあさん。
辻村 お話を聞きながら「この二人を会わせたい」という気持ちがふつふつと湧いて出て、改めて『ツナグ』のために取材し、思い出を預けていただきました。第三話には、幼い子供を事故で亡くした重田夫妻も登場します。『ツナグ』が再会以前に別離の話である以上、親が子供を送らなきゃいけないつらさについてもいつか書かねばならないと思っていたのですが、重田夫妻単体では私が苦しすぎて書くことができなかった。そんなとき小笠原さんのモデルとなった方と出会い、その力を借りることで、「母の心得」のあのラストを書くことができました。
松坂 ご縁ですね……。
辻村 そうなんです。小説の前作と映画を通じて、『ツナグ』とは「ご縁」が存在する世界なのだと、確信をもつことができたんです。このタイミングでこんなことが起きるなんて、という奇跡のような瞬間を、『ツナグ』の世界観であればためらいなく書くことができる。
松坂 今作を読んで、歩美の負うツナグの役目は、生と死だけでなくご縁を繋ぐものなのだという印象が強くなりました。
辻村 「ツナグに繋がらない人は繋がらないし、繋がる人にはちゃんと繋がるようになっている」というようなセリフを、映画で樹木さんにおっしゃっていただいたことでさらに強い説得力をもちましたし、私自身が年をとって、そういうこともあっていいんじゃないか、現実にはなかったとしても私が書くことで信じたいと思っている人たちに届いてくれたら、と思えるようにもなりました。だから『ツナグ』では、他の小説よりも、ベタな感情をためらいなく書いています。
松坂 僕も、仕事をするうえではすべてがご縁だと思うようにしているんです。やりたいなと思っていた作品がタイミングが合わずできなかったことも、まさかこんなところでこの作品に巡り合えるとはと思えることも。だから『ツナグ』の世界観にも、自然と心をシンクロさせられるのかもしれない。
辻村 先ほど映画は七年前というお話が出ましたが、実はこの小説における時間の経過も、前作から七年なんです。
松坂 ……! そういえば!
辻村 これもまたご縁なのかも。ただ、この感覚には必ず人のエゴがまじっている。前作を書いていたときにいちばん意識し、歩美自身も葛藤していたのが、死者の存在を生きている人間が勝手に自分のための美しい物語に変換していいのか、というところだったし、そもそも死んだ人に会いたいと願うことじたいがエゴだと思うんです。本当はもっと再会するにふさわしい人がいるかもしれないのに、自分が願い、それを受け入れてもらうことで、相手のチャンスを潰してしまう。そのことを決して忘れてはいけないなと思います。
松坂 最終話「想い人の心得」の依頼人・蜂谷はまさに、望まれていないとわかっていながら依頼し続けた人でした。
辻村 彼も当然、自分のエゴはわかっている。蜂谷は想い人・絢子に「私が会いたいのはお前じゃない」と怒られるその瞬間こそが欲しかったのでしょうね。鮫川老人にしても、きっと、真実を知っているのがこの世界で自分だけという特別感を手に入れたかった。それは仕方のないことだし、それでいいのだと私が覚悟を決めたことで、歩美の出会う依頼人のバリエーションもかなり広がったんじゃないかと思います。
相対する死者に映し出されるもの
松坂 今回、七年が経過して、歩美はすでに就職しているし、生涯の伴侶になるであろう女性にも出会う。ちょっと気恥ずかしかったですが、歩美ならそうするよなあということばかりで嬉しかったし、演じやすそうだなとも思いました。全部のシーンを歩美を通して体験してみたいです。
辻村 そう言っていただけてほっとしました。たぶん映画がなかったら私は続編を書かなかったと思うんです。完結した物語のその先を、というのはあまりイメージがわかなくて、シリーズものに対して憧れはあっても、自分はやらずに終わるのだと思っていた。でも映画のプロデューサーの方に「いつか歩美くんが誰かと結婚をして、その相手に自分がツナグであることをどんなふうに話すのだろう」と言われて、初めて歩美の未来を想像し、書いてみたい、と思いました。だから今回、このラストシーンにするというのは最初から決めていたんです。
松坂 そういう骨子がしっかりしているからなのかな。仮に映画の続編をやるとしたら、きっとみんな「ばあちゃんがいないのにどうするの?」って思うはず。でも、作中ではばあちゃんはすでに亡くなった後で、希林さんももういないけれど、それでもすごく面白い映画になるという確信をもって読み終えました。
辻村 前作でもそうでしたが、『ツナグ』では歩美の人生で大きく動く瞬間というのははっきり描かれていないんです。ツナグの役目を完全に引き継いだり、就職を決めたりという転機はリアルタイムで描かず、その間に焦点をあてる。完全に独り立ちした、おばあちゃんのサポートがない状態でどうツナグとしての役目に向き合っているのか。第四話「一人娘の心得」で書いたように、身近にいる大切な人を突然失ってしまったときはどうするか。大事なことは転機そのものではなく、間に流れる時間のほうで描けたらと思っているので、次にまた書くとしたら、結婚後の話になるんじゃないのかな。
松坂 聞きたいと思っていたんですが、続編を書かれるご予定はあるんですか。
辻村 十年に一冊ペースになるかもしれないですが(笑)、ライフワークのように、歩美の人生を追っていけたらいいなと感じています。人生ってわかりやすい断層で分かれているわけじゃなくて、グラデーションで積み重なっていくようなものだろうから、今は抜けたと思っていた葛藤にふたたび直面する日がくるかもしれない。そのとき彼を助けてくれるのはきっと、おばあちゃんや依頼人たちを通じて触れてきた「心得」なんだろうなと思います。
松坂 ……ああ、それはとてもよくわかる気がします。新人の頃は「帰れ!」って気持ちいいくらい怒鳴ってくれる監督もいたし、優しいだけじゃない教えの数々が僕を成長させてくれた。でも今は監督にさえ敬語を使われることもあって、それが淋しくも怖くもあります。だから僕、自分の中に、勝手に脳内監督を召喚して怒ってもらうようにしているんです。これまで僕を導いてくれたたくさんの人たちが、今の自分を見たらどう思うだろう、なんて言うだろう、って。
辻村 すごくよくわかります。私も「こんなもの書いてたら〇〇さんに怒られるよ!」って自分を叱咤しますし、今作での歩美も、悩むたび「おばあちゃんだったらどう言うかな?」って考えますよね。
松坂 似たくないと思っていた人の教えが、いつのまにか心に住み着いているってこともありますよね。僕の父はどちらかというと聞き上手で、一家の大黒柱らしい漢気溢れるタイプ、とは真逆の人。幼いころはそれがちょっといやだったりもしたんですが、いま僕もお仕事していて「相槌がうまい」と言われることがあって。今作の一話目「プロポーズの心得」で、父と息子の見えない部分で影響を受ける関係が描かれるのを読んだときも、なんかわかるなあって思いました。
辻村 そういう、誰かの心に残った想いのかけらを寄せ集めて一晩だけ人の形に保たせたものが、ツナグの呼び出す死者の姿なのかもしれないと思うことがあるんです。相対しているのは死者本人ではなく、自分の心に映ったその人。だからツナグは鏡を使うのかもしれない、と。
松坂 ああ……。
辻村 人はそうして生きているのだろう、と思います。だから私も、歩美に自分の心を映しながら、長く書いていけたらと思っています。今回、歩美以上に泰然とした杏奈という八歳の親戚の少女が出てきますが、彼女が年相応の顔を見せた恋の話も書いてみたいし、彼女が歩美に依頼をもちこむというのもおもしろそう。
松坂 映画化するときは杏奈のキャスティングがいちばん難しそうですね(笑)。
辻村 それこそご縁のタイミングで、まだ見ぬスターに期待を(笑)。けれど歩美はまたぜひ松坂さんに演じていただきたいな。今日お伝えしたとおり、続編となる今作は“松坂さんが演じた歩美”の影響を強く受けています。書き始めた当初は、原作での歩美が叔父さん夫婦とも暮らしていることを忘れ、映画のようにおばあちゃんと二人暮らしだと思い込んでいた(笑)。スタッフ・キャストの皆さんが世界観を作りこんでくれたからこその、幸福な経験をさせてもらいました。
松坂 身に余るお言葉です。むしろ僕以外がキャスティングされそうになったら全力で止めます(笑)。『ツナグ』がなかったら出会えなかった人たちがたくさんいて、歩美が依頼人たちとの出会いを通じて成長しているのと同じように、僕も『ツナグ』に生かされているような気がしているから。平川監督の撮る世界観でぜひ実現してほしいですね。


































