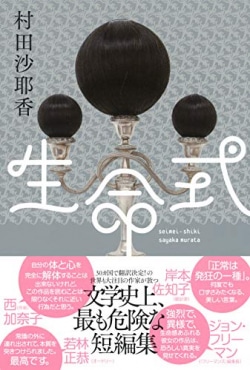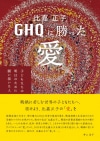『生命式』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
他では決して味わえない「常識」を突き崩す十二の短篇
[レビュアー] 伊藤氏貴(明治大学文学部准教授、文芸評論家)
かつて大航海時代に新世界と接した西欧の人たちは、自分たちとあまりに異なる風俗を持つ他者を、果たして同じ「人類」として扱っていいかどうかにさえ悩んだ。その問いから、文化人類学がはじまる。異なる「常識」を前にして、相手の側から自分の「常識」を捉えなおす学問だ。
しかし村田沙耶香は、一切のフィールドワークなしに、われわれの「常識」を根底から揺るがす。しかも民族レベルでなく、人類としての「常識」をだ。
十二の短篇のどれをとっても信じがたい「常識」が披露されるが、なかでも表題作「生命式」では、死者を送る儀式をそう呼ぶ。故人を偲ぶ式で、その人の肉を皆で食べ、新しい命を生み出すべく、そこで知り合った異性とペアになり、子作りに出かける。人口が急激に減って、たかだか三十年ほどの間に人肉食の禁忌が解かれ、性交は快楽よりも生殖のためのものとなり、子育ては政府が完璧に面倒を見てくれる。この異文化は一種の近未来とも読める。
あるいは同様に、人の死体を日用品の材料として活用する、「素敵な素材」の世界。
あるいは、栄養オタクの夫と、魔界の食べ物を想像で作る妹と、フライドポテトとお菓子しか食べないその妹のフィアンセと、昆虫食のその両親とが一堂に会する「素晴らしい食卓」。現在もどこかで起こりえないとは言えない異文化交流の姿だ。
あるいはまた、アイデンティティを一切持たず、ただ目の前の人間の期待に応えるかたちでキャラを作る女性を主人公とする「孵化」の世界。
死と生と性と食と自我と、人間にとっての根源に関わるわれわれの「常識」どもが次々に突き崩されていくこの感覚は、他では決して味わうことができない、村田の発見した「新世界」体験だ。村田の想像力の船に乗って、「常識」を揺るがす大航海に出かけよう。ただし、片道切符かもしれないが。