『約束された移動』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「空想と現実が断絶しないでうまくつながる瞬間があって、そうすると書けるんです。」小川洋子インタビュー【第1回】
[文] 河出書房新社

小川洋子さん
この11月に『約束された移動』を上梓した小川洋子さん。同書は2009年から2019年までに発表された“移動する”物語6篇を収録した傑作短篇集で、ハリウッド俳優Bと客室係、ダイアナ妃に魅せられたバーバラと孫娘など、ユニークで密やかな物語が収録されている。同書に収録する各作品について、短篇を書くことなど、さまざまな観点から小川洋子さんに話をうかがった。<全2回>
(インタビュー 五所純子)
***
——1年10ヵ月ぶりの短編集『約束された移動』が発表されました。小川さんは長編も短編もお書きになりますが、短編となると、発想のユニークさが際立ち、モチーフがより鮮やかに凝縮されていると感じます。短編を書くとき、どんなことを意識されていますか?
自分でも驚くくらい、短篇と長篇の違いは意識していないんです。短編でも長篇でも、まず書きたいもののイメージが浮かんで、それが動くのを待ちます。動きはじめたら、それを追うように書いていき、書いているうちに長さが決まっていきます。ですから短編か長篇かは、私でなく、題材が決めているんですね。
短編の場合は「○字くらいで、○日までに」という依頼をされます。そういう面で作品のかたちは、私の意思でなく、外的な要因が決めているわけです。
——表題作の「約束された移動」は原稿用紙50枚ほどの短編で、これまでの小川さんの短編よりも長いですね。
ええ、これまでは20から30枚でした。50枚をどう書いていいのかわからなくて戸惑ったんですけれども、50枚という分量が私の細胞のなかにこだまして、書いてみたら本当に50枚にしあがっていました。
——文章を短く刈り込むのと、長く膨らませるのと、どちらが好きですか?
文章がもつ特質として、刈り込むほうがいいものになる気がします。読み返して直していくと、短くなることが多いです。
削らなければと思うのは、自分の願望があらわれてしまっているところです。この登場人物にはこんなふうに言ってほしいとか、あるいは文章が上手だと思われたいなんて私の邪心が出ているところ。できるだけ作者の影を削っているんだと思います。
——作家の意図や外連味が除かれているから、小川さんの作品は透明度が高いと感じるのかもしれません。それに通じるのですが、登場人物に名前があたえられませんね。せいぜい俳優Bや歌手Jといったイニシャルです。
名前をつけることがもう、作家の手出しそのものですよね。生まれ出てきたものに名札がついていることはありません。イメージのなかではみんな名前がなくて、その状態のまま書き写したいという思いがあります。猥雑なものを排除していって、硝子や鉱物みたいに、これ以上は分解できないところまで凝縮したものとして描きたい。そうすると名前は必要ないということかもしれません。
年を取ると人の名前が思い出せなくなります。その人の表情や言葉、まわりの風景は憶えているのに、なぜか名前だけは出てこないということがあります。本当に大事なら忘れないと思うんですけど、忘れてしまうでしょう? 絶対的なようでありながらじつは名前って、はかないものですね。
——「約束された移動」は、ハリウッド俳優Bと客室係の「私」が失われた本のなかで合流し、記憶の旅をするような小説です。“本が読まれる風景”が美しく描かれています。いっぽう「ダイアナとバーバラ」では、“本が読まれない風景”が祖母と孫娘を美しく引き立てています。なぜ本と人との関わりを書くのでしょう。
私の小説にはよく本が出てきます。そもそも私は、人間どうしが面と向かって言葉で気持ちをぶつけ合うというシーンを書くのが得意じゃないんです。できるだけ人が言葉を交わさないですむ状況にもっていったほうが、物語がきちんと見えてきます。その典型が『猫を抱いて象と泳ぐ』のチェスでした。チェス盤を挟んで向かい合っていれば、口をきかなくても間がもちますね。
「約束された移動」のふたりは直接言葉を交わさないけれど、本を間に挟むとなぜか心が通じ合ったかのようになる。「ダイアナとバーバラ」は、相手への愛情や理解のしるしのように本が置かれている。
本がある。それだけで許される。未熟な言葉を相手にぶつけなくてすむ。そんな世界ですね。
——人が普段交わしている言葉自体に、あまり意味はないですよね。
ええ。親しい間柄であればあるほど、本質的なことって喋らないと思うんですよ。じゃあ登場人物のなにを描写すべきかというと、意味もない言葉をどういう表情で喋ったか、そこはどんな部屋だったか、どんな音が鳴っていたか。言葉よりももっと描写すべきものがある気がします。
私が書きたい本質的なものを、登場人物たちに喋らせたら、たぶんそれは伝わらなくなるんだと思います。
——たとえば幼少期などに、言葉に意味がないと思った体験はありますか。
私は学校にあまり友達がいなかったんです。クラスの人たちが輪になっておしゃべりしているでしょう。それを見て、いったい何を話しているのだろう、なぜ自分がそこに入っていけないのか、同じ言葉をしゃべっているのだろうか、と謎でしたね。
——その子たちを描写してみたいとか、その会話を想像で書いてみたいとか思いましたか?
自分が理解できない人物でも、お話のなかに出てくると会話できるんですよね。価値観が違う、生きている時代が違う、現実とは違うところに生きている。そういう人々が本のなかにはたくさんいて、本を読むと彼らと声にならない言葉で会話ができる。ですから友達はいなくても、図書館には居場所がありました。
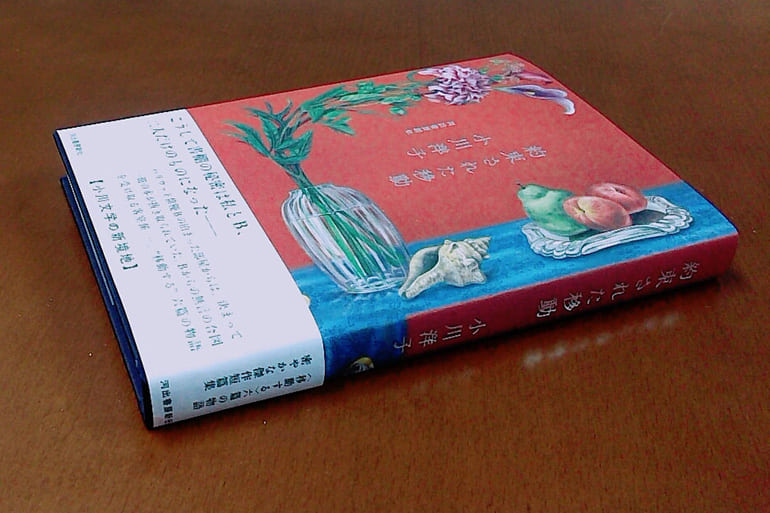
小川洋子さん、1年10ヵ月ぶりの短編集『約束された移動』
——子どもの頃から大切にされている本をおしえてください。
岩波少年文庫が大好きで、『長くつ下のピッピ』『二人のロッテ』『くまのプーさん』などです。本好きの子なら誰しも読むものからスタートして、『アンネの日記』に出会って私も文章を書こうと思いました。中学二年生のとき、ちょうどアンネが日記を書いていた年齢ですね。
——「約束された移動」にはいくつもの書名が出てきます。ガルシア=マルケス『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語』、ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』、アントニオ・タブッキ『インド夜想曲』など。
人の名前は出てきませんが、本の名前ならこのお話の世界にすんなりおさまります。すべて私の本棚に並んでいる小説です。書いているときになんとなく目に入ったタイトルで、こういう本を読んでいる男の人が私は好きだなと思えるものを選びました。
——6篇のどれにも、まるで本のような語り部がかならず出てきます。「約束された移動」のマッサージ師はリクエストに応じて同じ話をくりかえし語り、「ダイアナとバーバラ」のバーバラは実在のダイアナ妃について語り、「寄生」の老女はいわば嘘の語り部です。
物質としての本が目の前になくても、それぞれの人間の心のなかに、本の形をした記憶や体験があって、それを語るということはおたがい一冊の同じ本を読んだのと同じ関係になれる。そういうことなんでしょうね。
「約束された移動」のマッサージ師のおばさんは、いつもキッシンジャー兄弟の話をしてくれる。「黒子羊はどこへ」の園長さんが、昔話のように羊のことを語ってくれる。心地よい声をもった誰かが朗読してくれている。読んでいてそう感じられるように、文章のリズムはいつも気にかけています。
——小川さんご自身は人と話すことは好きですか?
私は余計なことまでべらべら喋るたちなんですけれども、それよりインタビューするのが、とくに自分と分野のちがう方に話を聞くのがとても好きです。できるだけ小説から遠い場所にいる人の話を聞いて、その言葉がぐるっと旅して小説に帰ってくる。それがすごくダイナミックな体験なんです。外側から言葉を投げかけてもらうことで小説のことが理解できたり、すぐには消化しきれなかった言葉が何年もたってから光を放ち出したりします。
数学者の藤原正彦さん(『世にも美しい数学入門』)や、人類学者の山極寿一さん(『ゴリラの森、言葉の海』)。その他、多くのすばらしい方々との出会いが、私にとっての財産となっています。
——先ほどキッシンジャーの名前が出ました。作品内では名前は明らかにされていませんが、他にも「約束された移動」では大阪万博の象、「ダイアナとバーバラ」ではダイアナ妃など、史実にもとづくイメージがときおり導入されています。
私が思い浮かべて書こうとするのは空想ですけれども、キッシンジャーやダイアナは現実にいた人ですね。空想と現実が断絶しないでうまくつながる瞬間があって、そうすると書けるんです。空想だけだとふわふわと地に足につかないけれど、現実的な助けが空想を確かなものにしてくれる。現実が錨となって私のところにおりてくる感じです。
大阪万博のとき、象を乗せた船が神戸港に着いた。象は博覧会場まで国道2号線を歩いていく途中で、武庫川の河川敷で子どもを産んだ。これは実際にあった話で、私は古い新聞を読んでたまたま見つけました。おもしろいお話だと思って。
象と同じ道を若者が歩いていくシーンのある映画、こっちは私の空想がこしらえたものです。でも書いたとたんに、現実なのか空想なのか、自分でもわからなくなってしまうんです。きっと同じことなんですよね。
——現実が残した話が組みこまれているように、人間が落としていったものが流れこんでいるのが小川さんの小説だと感じます。「約束された移動」の「私」はホテルの客室係として、宿泊客の忘れ物だけでなく、毛や爪や匂いから想像をめぐらせていく。肉体そのものじゃなく、肉体の痕跡です。
そうですね。私が書いているのは生身の人間じゃなくて死んでいる人で、履かれていた靴とか残された足跡とか、その人の欠片みたいなものを拾い集めているんでしょうね。だから、人に名前がないし、生な言葉も発しないんでしょう。
失われたものをこの本のなかだけで蘇らせて、本を閉じるとまた欠片に戻る。そういう小説であればいいと思います。


































