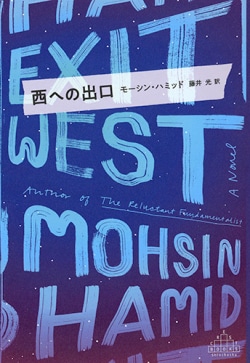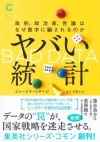『西への出口』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
西への出口 モーシン・ハミッド著
[レビュアー] 師岡カリーマ(文筆家)
◆移民を同じ人間として
イスラム圏のどこか、内戦が激化する架空の「町」で出会い、ともに「西」を目指す若い男女の物語。読者はきっと、中東の国を思い浮かべるだろう。確かに内戦のおぞましい様相はシリアと似ているが、ちょっとしたディテールが私のような中東育ちには「どうやら中東ではなさそうだ」と思わせ、現実と空想が入り組む流動的な世界観が、かえって登場人物の主体性をくっきりと浮かび上がらせる。
中東やイスラム圏の出身者または移民二世の多くは、特に作家や芸術家などの表現者であれば、誤解と差別の源となる人々の先入観や固定観念を打破したいという、漠然とした使命感を抱えている。固定観念の打破とはすなわち、一見みんな同じに見える他者の、個々の内面や価値観の多様性と、それが意味する人間性-彼らもあなたと同じ人間であるということ-の発見だ。そんな思いが、この小説にも切ないほどに、デビュー作と見紛(みまが)うほどの熱意で、でも決して被害者意識に陥らないクールな文体から溢(あふ)れ出る。
自らの選択で黒いローブに身を包みながら、バイクに乗りマリファナを吸う女性主人公の人物像は、冒頭から読者の先入観を壊しまくる。一方、内戦による経営難で社員解雇を余儀なくされて涙を流す上司や、レモンの木を見て久しぶりに微笑(ほほえ)む男性の姿は、彼らの人間性を読者に突きつける。それはまさに不法移民として蔑(さげす)まれ、密航船もろとも地中海に沈む人々の普遍的な人間性なのだ。
物語の難民たちは、船では密航しない。逃亡先の平和な国は、噂(うわさ)の「扉」のすぐ向こうにある。戦禍の人々がスマホを開けばそこに、飽食と娯楽に耽(ふけ)る幸運な人々の姿があるように。両者を隔てるのは薄い扉と、運の良し悪(あ)しのみ。逆に両者を結ぶものは無数にある。単独の存在の無力さや命のはかなさ。愛するものを失う悲しみ。たとえ住処(すみか)は変わらずとも社会は変わり、人は誰もが時代から時代への移民であるという真実。これは移民の物語であると同時に、抗(あらが)っても移ろいゆく心の、そしてあなたの物語。
(藤井光訳、新潮クレスト・ブックス・1980円)
1971年、パキスタン生まれの英語作家。同国と米国、英国を行き来し創作。
◆もう1冊
ニケシュ・シュクラ編『よい移民-現代イギリスを生きる21人の物語』(創元社)