『東京クルージング』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
伊集院静が描く「生きる」とは。男と女の“出逢いと別れ”を凝縮した極上の恋愛小説『東京クルージング』
[レビュアー] 池上冬樹(文芸評論家)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(評者:池上 冬樹 / 文芸評論家)
深い感動につつまれながら、本書を読まれたことだと思う。目頭をおさえながら本をとじた人もいるだろう。ストーリーもいいが、場面や台詞もいい。文学作品にはストーリーで読ませる小説もあれば、場面や台詞で読ませる小説もあり、作家はみなどちらでも読ませようと試みるものだが、得手不得手もあり、たいていどちらかに傾かざるをえない。二つをかねそなえることは、とても難しいからである。
だが、本書『東京クルージング』は、その両方の魅力をかねそなえている。前半は場面や台詞で読ませ、後半は波瀾にみちたストーリー展開で読者を惹きつける。だがその後半でも、一つ一つの場面が印象的で忘れがたい。それは至るところに箴言がちりばめられているからである。箴言が大げさなら、人生の妙味を解きあかす言葉といってもいい。その言葉に頁を繰る手がとまり、思いをめぐらせてしまう。頭の中に知識として入るのではなく、心で感じて読んでしまうのである。そして覚えた感慨が心を占めて離れない。
本書を読むあいだ、僕はずっとある詩句を思い出していた。それは「過ぎ去ってしまってからでないと/それが何であるかわからない何か/それが何であったかわかったときには/もはや失われてしまった何か」という黒田三郎の詩句(「ただ過ぎ去るために」)である。過ぎ去ってはじめてわかるものがあり、それが何であるかをわかったときにはすでに失われているという、誰もが思い至る人生の真実をついている。この後悔と諦念と失意をめぐる詩句は、哀しみを主題にする伊集院静の小説やエッセイによく似合っている。事実、伊集院静は、この後悔と諦念と失意をめぐって、作品の中で、曖昧な何かについてきちんと的確に言葉をあてはめ、人生の複雑な機微と消息を掴みとり、肯定してくれる。だから感動する。本書『東京クルージング』も例外ではない。
物語は二部構成である。第一部は、作家の私を主人公にしたもので、第二部はヤスコという女性の視点になる。この二人は直接的には関係がないが、それでも大きく太いつながりがある。
作家の私は、ドキュメンタリー番組の仕事で、三阪剛という青年と出逢う。珍しく瞳の澄んだ純粋な青年だった。松井秀喜のアメリカでの活躍を追うドキュメンタリー番組は、締め切りに追われる多忙な生活でも愉しく有意義で成功をおさめる。ただひとつの心残りは、青年に投げかけた言葉だった。三阪には将来を誓い合った女性がいたが、十二年前に突如三阪の前から消えてしまった。それでも忘れられないでいるという。私は「その人は、今も、どこかで生きていて、三阪君、君以外の人と暮らしています」(*1)といってしまったのである。考えてみれば酷い言葉だった。
三阪との付き合いは続いたが、彼は病魔に襲われていたことを私に知らせなかった。若くして彼は亡くなり、彼の死後に手紙を受け取った私は、三阪の過去を辿りながら、行方をくらましたひとりの女性の姿に思いをはせる──。
ある種実験的な作品といえるかもしれない。詳しく説明すると、前半は若きディレクター三阪剛との交流を中心とした作家の私小説であり、後半はディレクターと愛し合った女性ヤスコの苦難と絶望の物語である。分離しているようで、話はきちっとかみあい、前半のテーマがすべて後半で変奏されていく。前半の向日的で明るく語られる事柄が、後半の暗く罪悪感の濃い世界で捉え直される。具体的にあげるなら、ディレクターと語り合った「神さま」や「天使の分け前」、奇跡という言葉、さりげなく語られる棺にまつわる箴言(「人間は棺の中に入ってから、その人の真の価値や人間としての品格が出る」*2)、カザルスの「鳥の歌」、さらには教会、樹木、星、夕陽のイメージ、繰り返されるヤッターや大丈夫という言葉、そして前半で大きな比重を占める松井秀喜の活躍などが、別の場面、別の文脈で捉え直されて、苦く、ときに厳しい事実をつきつけて、より深い意味合いを付与するのである。
おそらく読者は第二部の中盤の物語にたじろぐかもしれない。女性が味わうことになる残酷で、理不尽で、あまりにも無慈悲な運命が辛すぎるからだ。でも、読まされてしまう。読まされ、体を熱くして、ひとりの女性の受難の物語を自らにひきつけてしまう。どんなに悲惨で残酷な運命でも、そこには意味があることを教えてくれるからである。
作者は、あるインタヴューで、本書執筆について次のように語っている。「人間は遥か昔から、“自分と共に人生を歩んでくれる人との出会い”を繰り返し求め続けています。本書に登場する青年・三阪剛と、三阪と将来を誓い合ったヤスコも、それぞれが未来への希望を持ち、いつか伴侶となる相手とめぐり逢えたらと願いながら生きてきました。異なる場所に生まれ育った二人が、数カ月だけでも気持ちを通じ合わせ、そのあともずっと相手を思い、また人生の支えとして感じられるほどの出会いをすることができた。“生きる”ことをテーマにした物語では、どんな結末を迎えるかが重要と思われがちですが、“もしかしたら最初の出会いが、生きることのすべてなのではないか。そして、そんな出会いができたというだけで、生きるという物語になるのではないか”と考え、本書を書きました」
この言葉が示すように、本文のなかにも「人と人が出逢うことは、人間がこの世に生きていることの中で、一番不思議で、一番魅力があって、そして何よりも“奇跡”に近い出来事だと、私は信じている」(*3)とある。「世界は新しい出逢いであふれているんだ。その出逢いをこころの隅で待ち望んでいるのが人間という生きものさ。私であり、君ということだよ」(*4)とも。
このように出逢いの奇跡を謳った物語といえるが、ふたりの人生は決して幸福ではなく、むしろ不幸だろう。男は病気で早く亡くなり、女は犯罪者に拉致されて一時期苦海に身を落とすからである。二人は別れ別れになるが、それでも、作者はそれを“ごく普通の出来事”といいきる。「近しい人との別離を否応なしに迎えると、最初は自分だけに哀しみが襲ったと思うのだけど、やがて歳月を経たことで、それがごく普通の出来事だとわかってくる」(*5)と。何と冷徹な見方だろう。でも、それが生きることなのだ。
ある場面では、「私は誰でも他人には見えない傷や痛み、つまり切ないものをかかえて生きていると思う。いや、それをかかえることが生きることだとも思っている。……三阪君、君も、私も、そんなことを平然とかかえて生きていきたいよね」(*6)と作家の私が三阪君に語りかけるのだが、それはかつて恩師のいねむり先生から言われたことでもある。「生きて行けば悲しいこととめぐり逢うのが、私たちの“生”です。でも人間がこうして何千、何万年と、泣いたり、笑ったり、怒ったりしているのは、悲しみが終わりを迎える時があるからです。どうかそれを信じて下さい」(*7)と。
ただ、誤解してほしくないのは、“悲しみが終りを迎える”のであって“悲しみが消える”といっているわけではないことだ。個人的なことになるが、老夫婦が食事の席で偶然、四十年前に三歳で病気で亡くなった長女の話に及んだとき、二人ともご飯を食べながら涙ぐんだのを見たことがある。いまはなき僕の両親の姿だ。悲しみは消えるのではなく、心の奥底に深く沈殿するだけなのである。歳月が悲しむ経験にとりあえずの終わりをつけてくれるだけである。
実は、冒頭で紹介した黒田三郎の詩句には続きがあり、「それが何であるかわかっていても/みすみす過ぎ去るに任せる外はない何か」と歌っている。多少ニュアンスは異なるけれど、辛い現実を乗り切るには「過ぎ去るに任せる外はない」のである。時間の経過だけしかない。でも、自ら進んで何か求める姿勢をなくしてはいけない。何故なら「差しのべた手の中にしか、葡萄の果実は落ちてこない」(*8)からである。本書には未来を幻視するかのような啓示的場面がいくつかあるが(祈りに似た敬虔な書き方が素晴らしい)、幸福を掴むのは、未来へと大きく開かれた心でもあるだろう。
このように、本書『東京クルージング』は、まことに多くのことを教えてくれる小説である。波瀾にとんだ男と女の悲劇的な物語であるにもかかわらず、読後感が温かいのは、人物たちの潔く力強い生き方が、静かに、熱く、胸を揺さぶるからである。伊集院静の代表作のひとつといえるだろう。
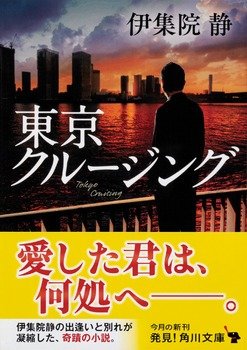
伊集院静が描く「生きる」とは。男と女の“出逢いと別れ”を凝縮した極上の恋愛…
▼伊集院静『東京クルージング』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000290/



































